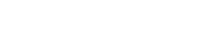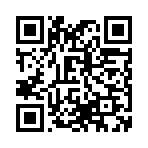2012年06月20日
玉の柄と竿掛けの製作
6月20日(水)
以前に玉枠を製作しましたが、柄を作っていないので、いまだにデビューできていませんでした。今回はせっかくなので、玉の柄と竿掛けをセットで作ってみることにしました。
今回の竹材はこちら・・・。

そう、良材とはとても言えない、節がボッコリの2m弱の竹・・・ 。おまけに節間も40cmくらいあって、まったく様にならないので、とりあえず火入れをしてまっすぐに、そして半分に切って節の出っ張りを削ってみた。
。おまけに節間も40cmくらいあって、まったく様にならないので、とりあえず火入れをしてまっすぐに、そして半分に切って節の出っ張りを削ってみた。

もうこれは、節巻きにしてごまかすしか方法はないと思い、ヒーヒー言いながら糸を巻き続けた(・・・といっても治具とドリルを利用して巻いているので、実は大した作業ではないんです )。込みも削り、これで基本は完成。
)。込みも削り、これで基本は完成。

ここからは塗り。口巻き部は以前ウキで使った研ぎだしを竿でもやってみることにした。ただ、研ぎだしは塗りの回数が多いので、結構大変なんです 。おまけに節巻きにしたので、細いところの塗りも多く、やけに時間がかかりました。しかも後半は4号竿の製作と被ってしまい、いつも作業場としていた風呂場は週末は大変な状況に・・・
。おまけに節巻きにしたので、細いところの塗りも多く、やけに時間がかかりました。しかも後半は4号竿の製作と被ってしまい、いつも作業場としていた風呂場は週末は大変な状況に・・・ 。
。

そんな中、なんとか仕上がりました・・・ 。
。

口巻き部のアップ・・・

まあそれなりに研ぎだしはできたのですが、節巻きと研ぎ出し模様の相性がいまいちな気がします・・・ 。
。
竿掛けとしたら、以前に製作したものの方が、アンティークな雰囲気で好きだったりします。でもこちらはセット物なので、気分次第で使い分けようかと思います 。
。
以前に玉枠を製作しましたが、柄を作っていないので、いまだにデビューできていませんでした。今回はせっかくなので、玉の柄と竿掛けをセットで作ってみることにしました。
今回の竹材はこちら・・・。

そう、良材とはとても言えない、節がボッコリの2m弱の竹・・・
 。おまけに節間も40cmくらいあって、まったく様にならないので、とりあえず火入れをしてまっすぐに、そして半分に切って節の出っ張りを削ってみた。
。おまけに節間も40cmくらいあって、まったく様にならないので、とりあえず火入れをしてまっすぐに、そして半分に切って節の出っ張りを削ってみた。
もうこれは、節巻きにしてごまかすしか方法はないと思い、ヒーヒー言いながら糸を巻き続けた(・・・といっても治具とドリルを利用して巻いているので、実は大した作業ではないんです
 )。込みも削り、これで基本は完成。
)。込みも削り、これで基本は完成。
ここからは塗り。口巻き部は以前ウキで使った研ぎだしを竿でもやってみることにした。ただ、研ぎだしは塗りの回数が多いので、結構大変なんです
 。おまけに節巻きにしたので、細いところの塗りも多く、やけに時間がかかりました。しかも後半は4号竿の製作と被ってしまい、いつも作業場としていた風呂場は週末は大変な状況に・・・
。おまけに節巻きにしたので、細いところの塗りも多く、やけに時間がかかりました。しかも後半は4号竿の製作と被ってしまい、いつも作業場としていた風呂場は週末は大変な状況に・・・ 。
。
そんな中、なんとか仕上がりました・・・
 。
。
口巻き部のアップ・・・


まあそれなりに研ぎだしはできたのですが、節巻きと研ぎ出し模様の相性がいまいちな気がします・・・
 。
。竿掛けとしたら、以前に製作したものの方が、アンティークな雰囲気で好きだったりします。でもこちらはセット物なので、気分次第で使い分けようかと思います
 。
。2012年05月08日
へら玉枠の製作
5月7日(火)
以前に工作予定を書いた中で、玉網の枠と絞り台の作業をGW中に進めて、まず玉網の枠が完成しました。絞り台はもう少しですので、今回は玉網の枠の製作過程を少々記録しておきます(絞り台はこちら)。
まず、材料ですが、工作予定に書いたように100円で購入した玉枠の輪の部分と木から削って作る込みの部分を合体させることにしました。いわゆる合成木枠というやつです。
込みの部分の木は、ホームセンターで見つけた栂(ツガ)。特にこだわったわけではなく、単に思っていたサイズの木材がこれしかなかったからなんですが、作業を進めていくとどうやら割れやすい材質のようで、カンナをかけてひっかかると簡単に割れてしまいました。それゆえ、結構苦労することに・・・・ 。とにかく、この木材をだいたいの形にのこぎりで切りました(右は絞り台用です)。
。とにかく、この木材をだいたいの形にのこぎりで切りました(右は絞り台用です)。

次にカンナ、平ヤスリ、ナイフを使って形を整えていきます。

そして、穴をあけて輪の部品を差し込み合体 。接着はエポキシボンドを使用しました。単純に差し込んだだけですが、隙間をすべてエポキシで埋めたこともあり、結構な強度があるような気がします
。接着はエポキシボンドを使用しました。単純に差し込んだだけですが、隙間をすべてエポキシで埋めたこともあり、結構な強度があるような気がします 。
。

込みの部分をアップにした写真ですが、ここも割れました。瞬間接着剤で補修しています。これ以外にも細かい部分がパキパキと・・・ 。そのために予定より横幅が小さくなりました。輪の部分との段差を小さくして継ぎ目をスムーズにするつもりだったのですが、これだけパキパキと割れると間違いなく更に割れそうだったので、強度重視で厚みを残しました
。そのために予定より横幅が小さくなりました。輪の部分との段差を小さくして継ぎ目をスムーズにするつもりだったのですが、これだけパキパキと割れると間違いなく更に割れそうだったので、強度重視で厚みを残しました 。
。

そして、塗りですが、まずウレタンで下塗りしてから、うるしの紅溜(ベニダメ)を3度、そして仕上げに再度ウレタンを塗り、竿同様に金属磨きのピカットで表面のざらつきを取り、コンパウンドで磨いて仕上げました 。
。

そして、網を取りつけて完了です。この玉網枠の強度もわからないので、網はとりあえず安価なもの(確か600円程度だったかと・・・)を使っています。取り付け糸は、イカリ印竿巻糸の2号(中)が家にあったので、それを使用。

輪部分との段差を目立たなくするために境目に籐を巻こうかと思っていましたが、強度には関係ないので、まずはシンプルにこのままで使ってみようと思います。ただ、この枠に合う玉網の柄を作らないとデビューできないのですが・・・ 。
。
以前に工作予定を書いた中で、玉網の枠と絞り台の作業をGW中に進めて、まず玉網の枠が完成しました。絞り台はもう少しですので、今回は玉網の枠の製作過程を少々記録しておきます(絞り台はこちら)。
まず、材料ですが、工作予定に書いたように100円で購入した玉枠の輪の部分と木から削って作る込みの部分を合体させることにしました。いわゆる合成木枠というやつです。
込みの部分の木は、ホームセンターで見つけた栂(ツガ)。特にこだわったわけではなく、単に思っていたサイズの木材がこれしかなかったからなんですが、作業を進めていくとどうやら割れやすい材質のようで、カンナをかけてひっかかると簡単に割れてしまいました。それゆえ、結構苦労することに・・・・
 。とにかく、この木材をだいたいの形にのこぎりで切りました(右は絞り台用です)。
。とにかく、この木材をだいたいの形にのこぎりで切りました(右は絞り台用です)。
次にカンナ、平ヤスリ、ナイフを使って形を整えていきます。

そして、穴をあけて輪の部品を差し込み合体
 。接着はエポキシボンドを使用しました。単純に差し込んだだけですが、隙間をすべてエポキシで埋めたこともあり、結構な強度があるような気がします
。接着はエポキシボンドを使用しました。単純に差し込んだだけですが、隙間をすべてエポキシで埋めたこともあり、結構な強度があるような気がします 。
。
込みの部分をアップにした写真ですが、ここも割れました。瞬間接着剤で補修しています。これ以外にも細かい部分がパキパキと・・・
 。そのために予定より横幅が小さくなりました。輪の部分との段差を小さくして継ぎ目をスムーズにするつもりだったのですが、これだけパキパキと割れると間違いなく更に割れそうだったので、強度重視で厚みを残しました
。そのために予定より横幅が小さくなりました。輪の部分との段差を小さくして継ぎ目をスムーズにするつもりだったのですが、これだけパキパキと割れると間違いなく更に割れそうだったので、強度重視で厚みを残しました 。
。
そして、塗りですが、まずウレタンで下塗りしてから、うるしの紅溜(ベニダメ)を3度、そして仕上げに再度ウレタンを塗り、竿同様に金属磨きのピカットで表面のざらつきを取り、コンパウンドで磨いて仕上げました
 。
。
そして、網を取りつけて完了です。この玉網枠の強度もわからないので、網はとりあえず安価なもの(確か600円程度だったかと・・・)を使っています。取り付け糸は、イカリ印竿巻糸の2号(中)が家にあったので、それを使用。

輪部分との段差を目立たなくするために境目に籐を巻こうかと思っていましたが、強度には関係ないので、まずはシンプルにこのままで使ってみようと思います。ただ、この枠に合う玉網の柄を作らないとデビューできないのですが・・・
 。
。 タグ :玉枠
2012年04月25日
竿掛けの製作 (後編)
4月25日(水)
さて、竿掛けの後編(前編はこちら)です。
【塗装3日目】
この前乾漆粉がうまくいかなかったので、再挑戦です。今度は、黒色の乾漆粉も作りました。作り方は黄色の時と同じです。これで下地の黒が乾漆粉の隙間から見えなくとも、色に黒が混じります。事前にすべての色を混ぜました。金粉も少し多めに・・・ 。
。

そして、乾漆粉の接着材としての役割の黒うるしですが、これも今回は一液性の透明ウレタンに変えてやってみることにしました。うまく着いたような気がします 。
。

【塗装4日目】
翌日の朝には乾漆粉の隙間を埋めるためにウレタンを塗って、昼には乾いていたので、もう一度塗りました。そして、夕方に400番で水研ぎ。そしてその上から、再度ウレタンを塗って本日終了。
【塗装5日目】
次の日の朝、まずは400番で水研ぎです。

曇ったようになった部分はほぼ平らになっているところです。赤マル部分には光った部分がありますが、これはまだ段差がある部分です。機能的には問題ないのですが、もう少しきれいに仕上げるために、あと1~2回は塗装と水研ぎをやる必要がありそうです。
水研ぎで籐の部分の色が少し剥げすぎましたので、うるしを指先につけて塗布。それ以外の竿全体にうるしの本透明を塗りました。そして夜になり、乾燥しているようなので、早速1000番のサンドペーパーで軽く水研ぎをするとまだ少し段差がありますが、この程度でOKでしょ・・・ということで、仕上げにうるしの本透明を竿全体に塗って就寝 。
。
【塗装6日目】
いよいよ最終仕上げです。このままだとピカピカ過ぎるので、七分程度程に上品に 光らせようと、家にあった金属磨きのピカット(よく皆さんがつかっているにはピカールというもののようです)でさーっとこすると簡単につや消しになりました。このままでも結構いい感じなのですが、もう少し光沢を出すために研磨フィルムの4000番と8000番で水研ぎ(今回は研磨フィルムを使いましたが、竹はデコボコのある曲面なのでコンパウンドの方が使いやすいです)。そして、塗装はこれにて完了。最後に口栓は竹を2重にして木工用ボンドで接着し、削って作成。竿掛けの完成です
光らせようと、家にあった金属磨きのピカット(よく皆さんがつかっているにはピカールというもののようです)でさーっとこすると簡単につや消しになりました。このままでも結構いい感じなのですが、もう少し光沢を出すために研磨フィルムの4000番と8000番で水研ぎ(今回は研磨フィルムを使いましたが、竹はデコボコのある曲面なのでコンパウンドの方が使いやすいです)。そして、塗装はこれにて完了。最後に口栓は竹を2重にして木工用ボンドで接着し、削って作成。竿掛けの完成です 。
。
まずは全体像の写真 。
。

そして手元のアップの写真 。
。

3号竿の持ち手と同じ色目にする予定ではなかったのですが、やはり赤色は塗装をしていくと存在感がなくなってしまい、3号竿の時とほぼ同じになってしまいましたので、並べて写真を撮りました。少し暗い赤を使っているからでしょう。次の機会にはもう少し派手な赤を混ぜてみたいと思います。
口糸を巻いた部分ですが、糸決めでウレタン1回、糸目を消すために黒色うるしを3回、乾漆粉を接着するのにウレタン1回、隙間を埋めるのに2回、そして水研ぎ、さらにウレタンを1回と水研ぎ、そして仕上げにうるしの本透明を2回と水研ぎ・・・と合計で10回も塗ったことになります。かなり手間がかかりました 。
。
わたしのように乾燥が待てない人は、薄く塗ること(薄く何度も塗る方が厚く塗るより乾燥もはるかに早いし、仕上げもきれいです)とウレタンを要所要所で使うことで(うるしよりも乾燥が早いので)、少しは早く仕上がります。でも乾燥する前に重ね塗りすると塗装がしわになったりするようなので、ご注意ください。塗装も慣れてくると、一回の作業が準備から片づけまで10~15分ほどしかかかりませんので、朝と夜に塗って、昼と夜中に乾燥させれば、作業が結構進みます。
ところでこの竿掛けはテーパーのない竹なので、どちらかというと玉網の柄向きだったかもしれません。改造しようかな・・・ 。
。
さて、竿掛けの後編(前編はこちら)です。
【塗装3日目】
この前乾漆粉がうまくいかなかったので、再挑戦です。今度は、黒色の乾漆粉も作りました。作り方は黄色の時と同じです。これで下地の黒が乾漆粉の隙間から見えなくとも、色に黒が混じります。事前にすべての色を混ぜました。金粉も少し多めに・・・
 。
。
そして、乾漆粉の接着材としての役割の黒うるしですが、これも今回は一液性の透明ウレタンに変えてやってみることにしました。うまく着いたような気がします
 。
。
【塗装4日目】
翌日の朝には乾漆粉の隙間を埋めるためにウレタンを塗って、昼には乾いていたので、もう一度塗りました。そして、夕方に400番で水研ぎ。そしてその上から、再度ウレタンを塗って本日終了。
【塗装5日目】
次の日の朝、まずは400番で水研ぎです。

曇ったようになった部分はほぼ平らになっているところです。赤マル部分には光った部分がありますが、これはまだ段差がある部分です。機能的には問題ないのですが、もう少しきれいに仕上げるために、あと1~2回は塗装と水研ぎをやる必要がありそうです。
水研ぎで籐の部分の色が少し剥げすぎましたので、うるしを指先につけて塗布。それ以外の竿全体にうるしの本透明を塗りました。そして夜になり、乾燥しているようなので、早速1000番のサンドペーパーで軽く水研ぎをするとまだ少し段差がありますが、この程度でOKでしょ・・・ということで、仕上げにうるしの本透明を竿全体に塗って就寝
 。
。【塗装6日目】
いよいよ最終仕上げです。このままだとピカピカ過ぎるので、七分程度程に上品に
 光らせようと、家にあった金属磨きのピカット(よく皆さんがつかっているにはピカールというもののようです)でさーっとこすると簡単につや消しになりました。このままでも結構いい感じなのですが、もう少し光沢を出すために研磨フィルムの4000番と8000番で水研ぎ(今回は研磨フィルムを使いましたが、竹はデコボコのある曲面なのでコンパウンドの方が使いやすいです)。そして、塗装はこれにて完了。最後に口栓は竹を2重にして木工用ボンドで接着し、削って作成。竿掛けの完成です
光らせようと、家にあった金属磨きのピカット(よく皆さんがつかっているにはピカールというもののようです)でさーっとこすると簡単につや消しになりました。このままでも結構いい感じなのですが、もう少し光沢を出すために研磨フィルムの4000番と8000番で水研ぎ(今回は研磨フィルムを使いましたが、竹はデコボコのある曲面なのでコンパウンドの方が使いやすいです)。そして、塗装はこれにて完了。最後に口栓は竹を2重にして木工用ボンドで接着し、削って作成。竿掛けの完成です 。
。まずは全体像の写真
 。
。
そして手元のアップの写真
 。
。
3号竿の持ち手と同じ色目にする予定ではなかったのですが、やはり赤色は塗装をしていくと存在感がなくなってしまい、3号竿の時とほぼ同じになってしまいましたので、並べて写真を撮りました。少し暗い赤を使っているからでしょう。次の機会にはもう少し派手な赤を混ぜてみたいと思います。
口糸を巻いた部分ですが、糸決めでウレタン1回、糸目を消すために黒色うるしを3回、乾漆粉を接着するのにウレタン1回、隙間を埋めるのに2回、そして水研ぎ、さらにウレタンを1回と水研ぎ、そして仕上げにうるしの本透明を2回と水研ぎ・・・と合計で10回も塗ったことになります。かなり手間がかかりました
 。
。わたしのように乾燥が待てない人は、薄く塗ること(薄く何度も塗る方が厚く塗るより乾燥もはるかに早いし、仕上げもきれいです)とウレタンを要所要所で使うことで(うるしよりも乾燥が早いので)、少しは早く仕上がります。でも乾燥する前に重ね塗りすると塗装がしわになったりするようなので、ご注意ください。塗装も慣れてくると、一回の作業が準備から片づけまで10~15分ほどしかかかりませんので、朝と夜に塗って、昼と夜中に乾燥させれば、作業が結構進みます。
ところでこの竿掛けはテーパーのない竹なので、どちらかというと玉網の柄向きだったかもしれません。改造しようかな・・・
 。
。 2012年04月18日
竿掛けの製作 (前編)
4月17日(火)
へら釣りを始めたのが年末の12月、そしてへら道具の製作を始めたのも12月。何もわからない中、始めて作ったのがこちらの竿掛けです。がんばって作ったのですが、今見ると、竹の曲がりは上手く取れてないし、火入れの焼きもムラだらけ。節は抜いてないので重く、込みの作りもガタつきあり。その上、塗りも適当、選んだ竹も節間が長く、節も出っぱっていてブサイク・・・と、まあ使っているのもはずかしくなってきました ・・・ので、新しく作ることにしました
・・・ので、新しく作ることにしました 。
。
管理池用に90cm程度の短めのものを製作したいと思います。万力との継ぎ口の塗装は、前回3号竿の握り手に籐と乾漆粉(本漆ではなく合成うるしの粉)を使いましたが、いくつか改善できそうな点があったので、それを試してみたいと思います。
【竹材選定】
竹材は、前回購入したホームセンター竹(直径15mm程度、篠竹10本入350円程度)の残りから探しました。そして、表面は少々傷みがあり、テーパーがほとんどないのが難点ですが、節間も長くなく、節も低い矢竹のような一本を発見 。90cmで6節なので、まあ良い感じです。
。90cmで6節なので、まあ良い感じです。
【火入れ】
弓型に曲がっていましたので、火入れは結構苦労しましたが、三度やって、なんとか使える程度にはまっすぐに。曲がりを取るには、竹を火で炙ってやわらかくしてから、矯め木(下写真)という道具を使って矯正するのですが、なかなか難しい作業です。まずすべて節間をまっすぐに、その後節前後の曲がりを取ると上手くいくようです。

この矯め木、作るのは簡単です。竹の太さに合わせて何種類か必要になります。太い用は木もしっかりしたものを選ばないと折れそうになります。ちなみにわたしのは折れそうです・・・ 。
。
火入れはキッチンの普通のガスコンロの上に耐火レンガを二つ乗せてやってます。下の写真のような感じです(写真の竹は今回のものではありません)。

【節抜き】
火入れのあとは節抜きです。錐をベンチバイス(万力)に挟んで、竹を両手のひらで挟み、キリモミのようにすると簡単に節が抜けます。この節抜き用の錐は先日記事にした平キリ製作とまったく作り方は同じですが、長さ1m、直径2.5~3mmのピアノ線を使い、両端に0.5mm差で刃を付けています。刃の形は平キリよりも穴を開けやすいように細長く作りました。4.5mm~8mmまで、0.5mm毎に8タイプ(4本)製作しました(8mmのものは3mmのピアノ線では細くてたたくと薄くなり過ぎるので、作りやすい平キリと同じ刃型になっています)。

【下処理】
枝が出ていた節の芽を電動ルーターを使ってきれいに、そして塗装がのるように竹全体の表面を600番程度のサンドペーパーでさっと水研ぎしました。また、糸を巻くところをナイフを使って、竹表面を削ります。削ると言っても、刃をあててスーッとこする感じです。キシャギというそうです。
【糸巻きと込み口削り】
面倒なので仮巻きはせずに、本番の糸や籐を巻いて、マスキングテープでほどけないように端をとめてから、込み口を削りました。込み口は、弓と万力の込みにあわせて開けますが、前回作成した平キリは、竿用に7.6mm程度までしか作っていなかったので、今回は木工用ドリルと棒ヤスリを使って削りました。

【塗装1日目】
本来なら下塗りのウレタン塗装から始めるのですが、籐部分は隙間にウレタンが入りこむと籐の隙間にうるしを入れ込むスペースがなくなり、3号竿の時のように塗りにムラがでるので、先に籐部分から塗りました。うるしは透と本透明に少量の黒を混ぜました。両サイドをマスキングテープでとめて、2時間ほどして表面が固まってきた頃にテープを剥がし、つまようじを使って際の処理をしました。結構きれいにできました。

次に続けて、糸巻き部分は糸決め(糸を固める目的)のために、竹表面がでている胴部分は下塗りのためにウレタンを薄く塗りました。ウレタンは一般的には2液性が良いとのことですが、面倒なので、1液性を愛用しています。そして数時間乾燥させてから(薄塗りなのですぐ乾く)、口糸巻き部分と節の芽部分には黒色のうるしを塗り、1日程度乾燥です。なお、塗装や乾燥は風呂場を使っています。ホコリが少ない上に換気扇もあり、また浴室乾燥をONにすると乾きも早く最高です 。
。

【塗装2日目】
そして、2日目の塗装です。今回は口糸巻き部分と籐部分に前回同様の色を、そして胴部分に透明と本透明のうるしを混ぜたものを塗りました。なんとなく雰囲気がでてきました。

本当は、1日待つつもりだったのですが、いつもの如く、待てず・・・ 。半日乾燥させたので、まず胴に透明を塗りました。そして次に口糸巻き部分にまず黒色を塗り、その上から乾漆粉を混ぜたものをパラパラと・・・。最後は紙で押さえて、しっかりと粉をうるしにつけます。
。半日乾燥させたので、まず胴に透明を塗りました。そして次に口糸巻き部分にまず黒色を塗り、その上から乾漆粉を混ぜたものをパラパラと・・・。最後は紙で押さえて、しっかりと粉をうるしにつけます。

見てお分かりのように、色が超ケバイ 。前回、赤色が少な過ぎて、イメージと違ったので、今回は赤を大量に入れたんですが、入れ過ぎたかも・・・。おまけに丁寧に粉を撒きすぎて隙間がなく、下地の黒色が見えない・・・
。前回、赤色が少な過ぎて、イメージと違ったので、今回は赤を大量に入れたんですが、入れ過ぎたかも・・・。おまけに丁寧に粉を撒きすぎて隙間がなく、下地の黒色が見えない・・・ 。でも、これはこれでええっか~と、しばらく乾燥させました。・・・が、少し下地を出せないかなと表面をそっと擦ると、なんとボロボロと粉が落ちるではありませんか・・・
。でも、これはこれでええっか~と、しばらく乾燥させました。・・・が、少し下地を出せないかなと表面をそっと擦ると、なんとボロボロと粉が落ちるではありませんか・・・ 。どうやら黒のうるしを少し薄めて塗ったのがいけなかったようで、粘度が落ちてしっかりとひっついていないようです。
。どうやら黒のうるしを少し薄めて塗ったのがいけなかったようで、粘度が落ちてしっかりとひっついていないようです。
少しハゲてしまった場所もあり、「もうこうなったら、全部落としたろ~ 」とやってしまいました
」とやってしまいました 。そして、全部は取れなかったので、サンドペーパーで水研ぎしました。
。そして、全部は取れなかったので、サンドペーパーで水研ぎしました。

まだ少し粉が残ってますが、これ以上研ぐと糸まで到達してしまうので、ここらでやめて、再度黒色を塗って原状回復。ちょっと焦りましたが、何とか元通りになりました 。
。
さて、続きをやりたいところですが、しばらく時間がないので、週末以降に・・・ 。後編はこちら。
。後編はこちら。
へら釣りを始めたのが年末の12月、そしてへら道具の製作を始めたのも12月。何もわからない中、始めて作ったのがこちらの竿掛けです。がんばって作ったのですが、今見ると、竹の曲がりは上手く取れてないし、火入れの焼きもムラだらけ。節は抜いてないので重く、込みの作りもガタつきあり。その上、塗りも適当、選んだ竹も節間が長く、節も出っぱっていてブサイク・・・と、まあ使っているのもはずかしくなってきました
 ・・・ので、新しく作ることにしました
・・・ので、新しく作ることにしました 。
。管理池用に90cm程度の短めのものを製作したいと思います。万力との継ぎ口の塗装は、前回3号竿の握り手に籐と乾漆粉(本漆ではなく合成うるしの粉)を使いましたが、いくつか改善できそうな点があったので、それを試してみたいと思います。
【竹材選定】
竹材は、前回購入したホームセンター竹(直径15mm程度、篠竹10本入350円程度)の残りから探しました。そして、表面は少々傷みがあり、テーパーがほとんどないのが難点ですが、節間も長くなく、節も低い矢竹のような一本を発見
 。90cmで6節なので、まあ良い感じです。
。90cmで6節なので、まあ良い感じです。【火入れ】
弓型に曲がっていましたので、火入れは結構苦労しましたが、三度やって、なんとか使える程度にはまっすぐに。曲がりを取るには、竹を火で炙ってやわらかくしてから、矯め木(下写真)という道具を使って矯正するのですが、なかなか難しい作業です。まずすべて節間をまっすぐに、その後節前後の曲がりを取ると上手くいくようです。

この矯め木、作るのは簡単です。竹の太さに合わせて何種類か必要になります。太い用は木もしっかりしたものを選ばないと折れそうになります。ちなみにわたしのは折れそうです・・・
 。
。火入れはキッチンの普通のガスコンロの上に耐火レンガを二つ乗せてやってます。下の写真のような感じです(写真の竹は今回のものではありません)。

【節抜き】
火入れのあとは節抜きです。錐をベンチバイス(万力)に挟んで、竹を両手のひらで挟み、キリモミのようにすると簡単に節が抜けます。この節抜き用の錐は先日記事にした平キリ製作とまったく作り方は同じですが、長さ1m、直径2.5~3mmのピアノ線を使い、両端に0.5mm差で刃を付けています。刃の形は平キリよりも穴を開けやすいように細長く作りました。4.5mm~8mmまで、0.5mm毎に8タイプ(4本)製作しました(8mmのものは3mmのピアノ線では細くてたたくと薄くなり過ぎるので、作りやすい平キリと同じ刃型になっています)。

【下処理】
枝が出ていた節の芽を電動ルーターを使ってきれいに、そして塗装がのるように竹全体の表面を600番程度のサンドペーパーでさっと水研ぎしました。また、糸を巻くところをナイフを使って、竹表面を削ります。削ると言っても、刃をあててスーッとこする感じです。キシャギというそうです。
【糸巻きと込み口削り】
面倒なので仮巻きはせずに、本番の糸や籐を巻いて、マスキングテープでほどけないように端をとめてから、込み口を削りました。込み口は、弓と万力の込みにあわせて開けますが、前回作成した平キリは、竿用に7.6mm程度までしか作っていなかったので、今回は木工用ドリルと棒ヤスリを使って削りました。

【塗装1日目】
本来なら下塗りのウレタン塗装から始めるのですが、籐部分は隙間にウレタンが入りこむと籐の隙間にうるしを入れ込むスペースがなくなり、3号竿の時のように塗りにムラがでるので、先に籐部分から塗りました。うるしは透と本透明に少量の黒を混ぜました。両サイドをマスキングテープでとめて、2時間ほどして表面が固まってきた頃にテープを剥がし、つまようじを使って際の処理をしました。結構きれいにできました。

次に続けて、糸巻き部分は糸決め(糸を固める目的)のために、竹表面がでている胴部分は下塗りのためにウレタンを薄く塗りました。ウレタンは一般的には2液性が良いとのことですが、面倒なので、1液性を愛用しています。そして数時間乾燥させてから(薄塗りなのですぐ乾く)、口糸巻き部分と節の芽部分には黒色のうるしを塗り、1日程度乾燥です。なお、塗装や乾燥は風呂場を使っています。ホコリが少ない上に換気扇もあり、また浴室乾燥をONにすると乾きも早く最高です
 。
。
【塗装2日目】
そして、2日目の塗装です。今回は口糸巻き部分と籐部分に前回同様の色を、そして胴部分に透明と本透明のうるしを混ぜたものを塗りました。なんとなく雰囲気がでてきました。

本当は、1日待つつもりだったのですが、いつもの如く、待てず・・・
 。半日乾燥させたので、まず胴に透明を塗りました。そして次に口糸巻き部分にまず黒色を塗り、その上から乾漆粉を混ぜたものをパラパラと・・・。最後は紙で押さえて、しっかりと粉をうるしにつけます。
。半日乾燥させたので、まず胴に透明を塗りました。そして次に口糸巻き部分にまず黒色を塗り、その上から乾漆粉を混ぜたものをパラパラと・・・。最後は紙で押さえて、しっかりと粉をうるしにつけます。
見てお分かりのように、色が超ケバイ
 。前回、赤色が少な過ぎて、イメージと違ったので、今回は赤を大量に入れたんですが、入れ過ぎたかも・・・。おまけに丁寧に粉を撒きすぎて隙間がなく、下地の黒色が見えない・・・
。前回、赤色が少な過ぎて、イメージと違ったので、今回は赤を大量に入れたんですが、入れ過ぎたかも・・・。おまけに丁寧に粉を撒きすぎて隙間がなく、下地の黒色が見えない・・・ 。でも、これはこれでええっか~と、しばらく乾燥させました。・・・が、少し下地を出せないかなと表面をそっと擦ると、なんとボロボロと粉が落ちるではありませんか・・・
。でも、これはこれでええっか~と、しばらく乾燥させました。・・・が、少し下地を出せないかなと表面をそっと擦ると、なんとボロボロと粉が落ちるではありませんか・・・ 。どうやら黒のうるしを少し薄めて塗ったのがいけなかったようで、粘度が落ちてしっかりとひっついていないようです。
。どうやら黒のうるしを少し薄めて塗ったのがいけなかったようで、粘度が落ちてしっかりとひっついていないようです。少しハゲてしまった場所もあり、「もうこうなったら、全部落としたろ~
 」とやってしまいました
」とやってしまいました 。そして、全部は取れなかったので、サンドペーパーで水研ぎしました。
。そして、全部は取れなかったので、サンドペーパーで水研ぎしました。
まだ少し粉が残ってますが、これ以上研ぐと糸まで到達してしまうので、ここらでやめて、再度黒色を塗って原状回復。ちょっと焦りましたが、何とか元通りになりました
 。
。さて、続きをやりたいところですが、しばらく時間がないので、週末以降に・・・
 。後編はこちら。
。後編はこちら。 2012年01月18日
玉網と玉の柄の自作
1月18日(水)
気合を入れて、玉網と玉の柄一気に作ってしまいました 。
。

枠はゆっくり炙りながら曲げないといけないので、最初にトライした時は強く曲げ過ぎて折れたり 、焦げてしまったりしましたが
、焦げてしまったりしましたが 、直径7~8mm程度の細めの竹を使い、慎重にやるとうまくいきました。籐を巻いている部分の内側にはパテを埋め、またエポキシで固めて更に強化しました。かなり頑丈にできました。
、直径7~8mm程度の細めの竹を使い、慎重にやるとうまくいきました。籐を巻いている部分の内側にはパテを埋め、またエポキシで固めて更に強化しました。かなり頑丈にできました。
網を枠に編んで行くいくのに針のようなものが必要ですが、ちょうど良いサイズの針がなかったので、糸の先を瞬間接着剤で固めてみるとバッチリ 。網はケチって600円くらいの安物にしてしまいましたが、せっかくなのでヘラ用の普通のやつにすればよかったです。でも網だけで5000円くらいするんです
。網はケチって600円くらいの安物にしてしまいましたが、せっかくなのでヘラ用の普通のやつにすればよかったです。でも網だけで5000円くらいするんです 。いくらなんでも高すぎるでしょ
。いくらなんでも高すぎるでしょ 。
。
さて、玉の柄ですが、握り手は木を削って作ってみました(上部の差し込み口は上の写真に写ってます)。

ちょうど使えそうな円筒型の木材をコーナンで見つけたので、穴は竹のサイズに合わせて大きくし、竹も少し削って調整、木工ボンドで接着。外側はカンナで大まかに削り、ヤスリで仕上げ。水性絵具で色付けをして、ウレタンで塗装しました。糸や籐を巻くのとはまた違った雰囲気になります 。
。
思ったよりうまくできました 。まだいろいろと作りたいものがあるのですが、まずは一昨日の竿とあわせて使ってみます(竿の曲がりが不安
。まだいろいろと作りたいものがあるのですが、まずは一昨日の竿とあわせて使ってみます(竿の曲がりが不安 )。
)。
気合を入れて、玉網と玉の柄一気に作ってしまいました
 。
。
枠はゆっくり炙りながら曲げないといけないので、最初にトライした時は強く曲げ過ぎて折れたり
 、焦げてしまったりしましたが
、焦げてしまったりしましたが 、直径7~8mm程度の細めの竹を使い、慎重にやるとうまくいきました。籐を巻いている部分の内側にはパテを埋め、またエポキシで固めて更に強化しました。かなり頑丈にできました。
、直径7~8mm程度の細めの竹を使い、慎重にやるとうまくいきました。籐を巻いている部分の内側にはパテを埋め、またエポキシで固めて更に強化しました。かなり頑丈にできました。網を枠に編んで行くいくのに針のようなものが必要ですが、ちょうど良いサイズの針がなかったので、糸の先を瞬間接着剤で固めてみるとバッチリ
 。網はケチって600円くらいの安物にしてしまいましたが、せっかくなのでヘラ用の普通のやつにすればよかったです。でも網だけで5000円くらいするんです
。網はケチって600円くらいの安物にしてしまいましたが、せっかくなのでヘラ用の普通のやつにすればよかったです。でも網だけで5000円くらいするんです 。いくらなんでも高すぎるでしょ
。いくらなんでも高すぎるでしょ 。
。さて、玉の柄ですが、握り手は木を削って作ってみました(上部の差し込み口は上の写真に写ってます)。

ちょうど使えそうな円筒型の木材をコーナンで見つけたので、穴は竹のサイズに合わせて大きくし、竹も少し削って調整、木工ボンドで接着。外側はカンナで大まかに削り、ヤスリで仕上げ。水性絵具で色付けをして、ウレタンで塗装しました。糸や籐を巻くのとはまた違った雰囲気になります
 。
。思ったよりうまくできました
 。まだいろいろと作りたいものがあるのですが、まずは一昨日の竿とあわせて使ってみます(竿の曲がりが不安
。まだいろいろと作りたいものがあるのですが、まずは一昨日の竿とあわせて使ってみます(竿の曲がりが不安 )。
)。