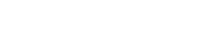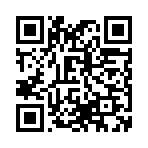2012年07月01日
エサトレイ
7月1日(日)
先週は軽い食中毒になってしまい、しばらく苦しんでおりましたが、何とか復活 。この季節はバイ菌君も活性が高いそうなので、皆様もご注意ください
。この季節はバイ菌君も活性が高いそうなので、皆様もご注意ください 。
。
さて、病み上がりでまだ無理もしたくないところにお天気は雨 。ということで、週末の釣りはお休み
。ということで、週末の釣りはお休み 。なので、工作をやりまくっております・・・
。なので、工作をやりまくっております・・・ 。
。
まずは15分で完了するもっとも簡単なやつから・・・。準備したものはこちら。

100円ショップで見つけたトレイと机面の下に引く緑色のやつ、そしてホームセンターでステイと20mmM5のネジと蝶ナットを購入。あとはカッター、ものさしと瞬間接着剤、そして写真には写ってないですが、5mmの穴をあけるドリル。
まず、トレイの底面にあわせて、緑色のシートをカット、トレイの端の方に穴をあけて、シートを瞬間接着剤で張り付け、ステイとネジでとめるだけ・・・そしてもう完成 。
。

お膳というのか、うどん皿と呼ぶのかよくわかりませんので、エサトレイと呼んでおきます。ステイを万力と角木の隙間にはさんで締めるだけ。うどんだけでなく、ダンゴでも次のエサを置いておくのに便利ですよね 。
。
仕舞う時はネジを緩めて、ステイをトレイの下に格納。

以上です。
なお、ステイを厚みのあるものにしたのですが、ステンレスの薄いものの方がベターだと思います。またトレイはウレタンらしい塗装がすでにされていますので、塗装の必要もなさそうです 。
。
先週は軽い食中毒になってしまい、しばらく苦しんでおりましたが、何とか復活
 。この季節はバイ菌君も活性が高いそうなので、皆様もご注意ください
。この季節はバイ菌君も活性が高いそうなので、皆様もご注意ください 。
。さて、病み上がりでまだ無理もしたくないところにお天気は雨
 。ということで、週末の釣りはお休み
。ということで、週末の釣りはお休み 。なので、工作をやりまくっております・・・
。なので、工作をやりまくっております・・・ 。
。まずは15分で完了するもっとも簡単なやつから・・・。準備したものはこちら。

100円ショップで見つけたトレイと机面の下に引く緑色のやつ、そしてホームセンターでステイと20mmM5のネジと蝶ナットを購入。あとはカッター、ものさしと瞬間接着剤、そして写真には写ってないですが、5mmの穴をあけるドリル。
まず、トレイの底面にあわせて、緑色のシートをカット、トレイの端の方に穴をあけて、シートを瞬間接着剤で張り付け、ステイとネジでとめるだけ・・・そしてもう完成
 。
。
お膳というのか、うどん皿と呼ぶのかよくわかりませんので、エサトレイと呼んでおきます。ステイを万力と角木の隙間にはさんで締めるだけ。うどんだけでなく、ダンゴでも次のエサを置いておくのに便利ですよね
 。
。仕舞う時はネジを緩めて、ステイをトレイの下に格納。

以上です。
なお、ステイを厚みのあるものにしたのですが、ステンレスの薄いものの方がベターだと思います。またトレイはウレタンらしい塗装がすでにされていますので、塗装の必要もなさそうです
 。
。 タグ :エサトレイ
2012年05月15日
ポンプ絞り台の製作
5月13日(日)
先日工作予定を書いた中で、玉網の枠は終了しましたので、次はポンプ絞り台の製作です。
土台と柱の材料は先日玉網の枠に使った割れやすい栂(ツガ)です 。ハンドル部は家に余っていたヒノキの端切れです。土台部分は幅60mm・厚さ24mm・長さ150mmで、底面が30×30mmの角柱を差し込むための穴と、ポンプを置く穴(写真では浅いですが、実際には深い穴、直径40mm)をあけました。写真左は前回の玉枠製作中のものです。
。ハンドル部は家に余っていたヒノキの端切れです。土台部分は幅60mm・厚さ24mm・長さ150mmで、底面が30×30mmの角柱を差し込むための穴と、ポンプを置く穴(写真では浅いですが、実際には深い穴、直径40mm)をあけました。写真左は前回の玉枠製作中のものです。

そして、穴に角柱を差し込んでみると・・・ ・・・角柱の底面が正方形ではなくひし形に歪んでいるではありませんか・・・
・・・角柱の底面が正方形ではなくひし形に歪んでいるではありませんか・・・ 。購入の際にきちんと調べるべきでした。仕方ないので、角柱を削り入るようにして、おがくずとエポキシボンドで大きな隙間を埋めました
。購入の際にきちんと調べるべきでした。仕方ないので、角柱を削り入るようにして、おがくずとエポキシボンドで大きな隙間を埋めました 。
。

可動部分ですが、木に直接ボルトを刺すと木が削れて劣化が早いので、角柱とハンドル部分には5mmの穴をあけて、アルミパイプ(外径5mm、内径4mm)を通しました。芯材は4mmのステンレスボルトと蝶ネジを使用します。仮組みしてみました 。
。

ドリルを手に持って穴をあけているので、穴をまっすぐにあけるのが大変でしたが、少し芯材のボルトの中央部分を削るとスムーズに動くようになりました 。
。
そして次は色塗りです。下の写真はすでに3度塗りを終えたところですが、ハンドル部分と土台部分の色がかなり違います。同じ塗料を塗っているので、おそらく素材の色が少し違うせいだと思います。最終的には5度塗り+ウレタン塗装しましたが、少し色を変えてあわせていきました。

話は少し脱線しますが、わたしが塗りをする時には写真の①~⑥のものを準備しています。これがあるとかなり作業がはかどります。
①風呂のフタの上で塗りをしていますので、新聞紙や広告を広げます。
②絵皿を掃除する際、また万一のはみ出しにも即対応できるようにキッチンペーパーを準備。
③使用後のキッチンペーパーは溶剤の臭いとうるしがついているので、即ビニール袋で処理。
④絵皿で混ぜます。これがあれば後の筆の掃除も楽です。
⑤スポイトを使用するようになってから、無駄もなくなり、濃さの調整も簡単に!
⑥どこを持って塗るか、またどのように乾かすかを事前に決めておきます。そのために必要な持ち手や洗濯バサミ、かける糸なども準備万端にしておく必要があります。これ最重要 。
。
塗りが終わった後は、絵皿や筆を溶剤できれいにして、キッチンペーパーでふき取って終了です。そして出来上がったのがこちら。底面には滑り止めのゴムを貼りました。

ポンプの差し込み穴の底には水抜き穴もあけました。

一番下まで降ろした時の感じです。

対して、こちらは一番上まであげた時。

ヤスリがけで手を抜いてしまったので、少々デコボコがあり、塗装をテカらせると波打って美しくないので、金属磨きのピッカトでつや消しにしました。とりあえず、これで完成です 。
。
今回角柱を使いましたが、市販品と同様に円柱を使った方が簡単だと思います。角柱だとぴったりの穴を土台にあけるのに苦労しますが、円柱だとそのサイズのドリルを買ってしまえば簡単です。おまけにハンドル取り付けの際に側面の抵抗が少ないので、若干穴が曲がっていても問題なく可動すると思います。まあ、次に作ることは当分なさそうですが・・・ 。
。
次の工作は折れた穂先の検証と新たな穂先作りからです・・・ 。
。
先日工作予定を書いた中で、玉網の枠は終了しましたので、次はポンプ絞り台の製作です。
土台と柱の材料は先日玉網の枠に使った割れやすい栂(ツガ)です
 。ハンドル部は家に余っていたヒノキの端切れです。土台部分は幅60mm・厚さ24mm・長さ150mmで、底面が30×30mmの角柱を差し込むための穴と、ポンプを置く穴(写真では浅いですが、実際には深い穴、直径40mm)をあけました。写真左は前回の玉枠製作中のものです。
。ハンドル部は家に余っていたヒノキの端切れです。土台部分は幅60mm・厚さ24mm・長さ150mmで、底面が30×30mmの角柱を差し込むための穴と、ポンプを置く穴(写真では浅いですが、実際には深い穴、直径40mm)をあけました。写真左は前回の玉枠製作中のものです。
そして、穴に角柱を差し込んでみると・・・
 ・・・角柱の底面が正方形ではなくひし形に歪んでいるではありませんか・・・
・・・角柱の底面が正方形ではなくひし形に歪んでいるではありませんか・・・ 。購入の際にきちんと調べるべきでした。仕方ないので、角柱を削り入るようにして、おがくずとエポキシボンドで大きな隙間を埋めました
。購入の際にきちんと調べるべきでした。仕方ないので、角柱を削り入るようにして、おがくずとエポキシボンドで大きな隙間を埋めました 。
。
可動部分ですが、木に直接ボルトを刺すと木が削れて劣化が早いので、角柱とハンドル部分には5mmの穴をあけて、アルミパイプ(外径5mm、内径4mm)を通しました。芯材は4mmのステンレスボルトと蝶ネジを使用します。仮組みしてみました
 。
。
ドリルを手に持って穴をあけているので、穴をまっすぐにあけるのが大変でしたが、少し芯材のボルトの中央部分を削るとスムーズに動くようになりました
 。
。そして次は色塗りです。下の写真はすでに3度塗りを終えたところですが、ハンドル部分と土台部分の色がかなり違います。同じ塗料を塗っているので、おそらく素材の色が少し違うせいだと思います。最終的には5度塗り+ウレタン塗装しましたが、少し色を変えてあわせていきました。

話は少し脱線しますが、わたしが塗りをする時には写真の①~⑥のものを準備しています。これがあるとかなり作業がはかどります。
①風呂のフタの上で塗りをしていますので、新聞紙や広告を広げます。
②絵皿を掃除する際、また万一のはみ出しにも即対応できるようにキッチンペーパーを準備。
③使用後のキッチンペーパーは溶剤の臭いとうるしがついているので、即ビニール袋で処理。
④絵皿で混ぜます。これがあれば後の筆の掃除も楽です。
⑤スポイトを使用するようになってから、無駄もなくなり、濃さの調整も簡単に!
⑥どこを持って塗るか、またどのように乾かすかを事前に決めておきます。そのために必要な持ち手や洗濯バサミ、かける糸なども準備万端にしておく必要があります。これ最重要
 。
。塗りが終わった後は、絵皿や筆を溶剤できれいにして、キッチンペーパーでふき取って終了です。そして出来上がったのがこちら。底面には滑り止めのゴムを貼りました。

ポンプの差し込み穴の底には水抜き穴もあけました。

一番下まで降ろした時の感じです。

対して、こちらは一番上まであげた時。

ヤスリがけで手を抜いてしまったので、少々デコボコがあり、塗装をテカらせると波打って美しくないので、金属磨きのピッカトでつや消しにしました。とりあえず、これで完成です
 。
。今回角柱を使いましたが、市販品と同様に円柱を使った方が簡単だと思います。角柱だとぴったりの穴を土台にあけるのに苦労しますが、円柱だとそのサイズのドリルを買ってしまえば簡単です。おまけにハンドル取り付けの際に側面の抵抗が少ないので、若干穴が曲がっていても問題なく可動すると思います。まあ、次に作ることは当分なさそうですが・・・
 。
。次の工作は折れた穂先の検証と新たな穂先作りからです・・・
 。
。タグ :ポンプ絞り台
2012年05月02日
工作予定
5月2日(水)
最近釣り具の自作にはまっておりますが、作りたいものの待ちの列がずらーっと・・・ 。その一部をご紹介
。その一部をご紹介 。
。
【絞り台】
まずはポンプの絞り台。今はとりあえずのものを作って使っているのですが、もう少しかっこいいやつを作りたいと思っています。適当に木を切って作ろうかと思いましたが、削る工程なども多く、失敗すると時間の無駄になってしまうので、少しだけ下準備を・・・ 。
。

手元にある木材の大きさにあわせて牛乳パックを切って、基本構造の確認です。面倒だったので、かなり適当ですが、イメージはわきました。高さを調整できるようにしようかと思っていましたが、1日の釣りで大量にインスタントウドンを作ることもないので、必要なさそうです。
【平キリ】
以前に作った平キリですが、3号竿を製作/補修するのに必要なサイズのみ作ったので、虫食い状態です。2mmから12mm程度まで0.2mm単位で揃えようと準備中です。8mmまでの不足分はすでに熱して叩いて平らにしています 。
。

太い物は、熱して叩くのも大変なので、後回しになっています。とりあえず、写真の平らにしたものを削って、焼き入れをして、刃を付けることからやろうと思っています。
【玉網の枠】
現在使用しているものは、インターネットの写真と店で実物を見て、適当に考えて作ったものですが、このまえ誤って踏んでしまい、込みの上部に割れが入ってしまいました 。まずはそれを修理してます。
。まずはそれを修理してます。

割れの入った部分に糸を巻いて補強。まあ、そもそも糸を巻いていなかったのが失敗なのですが、製作当時の1月は竹で物を作ることを始めたばかりでしたので、いまいち扱いがわかっていませんでした。あとは網を取り付けている糸を結びなおして、終了です。
最近こどもとも一緒にヘラに行っていることもあり、もうひとつ予備枠を作っておこうと準備中です。

こちらは、上○屋で見つけた100円の玉網の枠(割れが入っていたり、かなりショボい作りのものです)を材料にして、製作予定です。枠が大きすぎるので、柄の部分を切り取り、直径を30cmにして、新たに柄の部分を別の木で作りなおして完成させる予定です。
【その他】
これ以外にも、お膳(すでに万力部分の部品は入手)とか、玉網の柄の作りなおしとか、針はずしとか・・・・いっぱいあり過ぎてどうしていいかわかりません・・・ 。
。
最近釣り具の自作にはまっておりますが、作りたいものの待ちの列がずらーっと・・・
 。その一部をご紹介
。その一部をご紹介 。
。【絞り台】
まずはポンプの絞り台。今はとりあえずのものを作って使っているのですが、もう少しかっこいいやつを作りたいと思っています。適当に木を切って作ろうかと思いましたが、削る工程なども多く、失敗すると時間の無駄になってしまうので、少しだけ下準備を・・・
 。
。
手元にある木材の大きさにあわせて牛乳パックを切って、基本構造の確認です。面倒だったので、かなり適当ですが、イメージはわきました。高さを調整できるようにしようかと思っていましたが、1日の釣りで大量にインスタントウドンを作ることもないので、必要なさそうです。
【平キリ】
以前に作った平キリですが、3号竿を製作/補修するのに必要なサイズのみ作ったので、虫食い状態です。2mmから12mm程度まで0.2mm単位で揃えようと準備中です。8mmまでの不足分はすでに熱して叩いて平らにしています
 。
。
太い物は、熱して叩くのも大変なので、後回しになっています。とりあえず、写真の平らにしたものを削って、焼き入れをして、刃を付けることからやろうと思っています。
【玉網の枠】
現在使用しているものは、インターネットの写真と店で実物を見て、適当に考えて作ったものですが、このまえ誤って踏んでしまい、込みの上部に割れが入ってしまいました
 。まずはそれを修理してます。
。まずはそれを修理してます。
割れの入った部分に糸を巻いて補強。まあ、そもそも糸を巻いていなかったのが失敗なのですが、製作当時の1月は竹で物を作ることを始めたばかりでしたので、いまいち扱いがわかっていませんでした。あとは網を取り付けている糸を結びなおして、終了です。
最近こどもとも一緒にヘラに行っていることもあり、もうひとつ予備枠を作っておこうと準備中です。

こちらは、上○屋で見つけた100円の玉網の枠(割れが入っていたり、かなりショボい作りのものです)を材料にして、製作予定です。枠が大きすぎるので、柄の部分を切り取り、直径を30cmにして、新たに柄の部分を別の木で作りなおして完成させる予定です。
【その他】
これ以外にも、お膳(すでに万力部分の部品は入手)とか、玉網の柄の作りなおしとか、針はずしとか・・・・いっぱいあり過ぎてどうしていいかわかりません・・・
 。
。 2012年03月06日
浮子ケース製作
3月5日(月)
土曜日は、磯の予定、海が荒れていたらへらのつもりでしたが、前夜に突如飲みのお誘いが・・・ 。不覚にも飲み過ぎてしまい、土曜は二日酔い
。不覚にも飲み過ぎてしまい、土曜は二日酔い 。磯は早々にあきらめ、昼まで寝てなんとかへらには行こうと思っていましたが、頭痛と胃の不快感は取れず、釣りはあきらめました
。磯は早々にあきらめ、昼まで寝てなんとかへらには行こうと思っていましたが、頭痛と胃の不快感は取れず、釣りはあきらめました 。せめて、日曜日は子連れでへらに行こうかと思っておりましたが、雨
。せめて、日曜日は子連れでへらに行こうかと思っておりましたが、雨 で、これも実現できず
で、これも実現できず 。
。
・・・ということで、週末は工作することに 。浮子ケースの製作です。木材はホームセンターで、天板および底板用にアガチス600×90×3(長さ・幅・厚さ)を2枚、側面用にヒノキ910×15×9(同)を2本購入。それを切って組み立てました。
。浮子ケースの製作です。木材はホームセンターで、天板および底板用にアガチス600×90×3(長さ・幅・厚さ)を2枚、側面用にヒノキ910×15×9(同)を2本購入。それを切って組み立てました。

写真のように重ねた時の仕上がり寸法は、約380×90×36(長さ・幅・高さ)です。今回側面のヒノキは上下それぞれ15mmのものを使いましたが、本当は30mmのものを使って一旦箱を作り、それを真ん中でフタと底側に切断すると噛み合わせが揃い、また木材のクセが同じ方向になるので、上手く作れるようです。わたしの場合、それを知ったのが材料を購入した後だったこともあり、万力を乗せて、噛み合わせがフィットするように癖をつけました 。
。
天板と底板は木工用ボンドで張り付けただけなんですが、側面は強化するために竹串で2cmほどの釘をつくり、それを打ち込んでいます。

天板の余った材料とマット剤を使い、中の仕切り(ウキ尻を差し込むところやウキのトップを押さえるところ)を作りました。下の写真はウキ尻を差し込む部分です。マット材を2枚に重ねて、上になる方に三角の切りこみ(+縦の切りこみ)を入れています。

これら部材をセットして、木工部分は完了しました 。
。

試しにウキを入れてみると、なかなかいい感じです
 。左右ともに上下7本ずつで合計28本。通常使用で33cmまで、片側の仕切りをはずすと最長35.5cmのウキまで入ります。
。左右ともに上下7本ずつで合計28本。通常使用で33cmまで、片側の仕切りをはずすと最長35.5cmのウキまで入ります。
次に左右の接続ですが、一般的な蝶番と磁石を使おうと思いましたが、蝶番をきれいにつけるのは結構難しい上に、小型の蝶番に合う細い木ネジが見つからなかったので(普通の釘だとすぐに緩んでくるため)、全部磁石で付けることとしました。ただ、使い勝手が悪くなると嫌だなと思って、インターネットで調べてるとプロの作品でも全部磁石のものがあることを発見したので、安心して全部磁石でやることに・・・。使った磁石はこちら 。
。

100円ショップで購入。ピン型になっていますが、ニッパで挟んで力を入れると簡単に割れて、中の磁石だけでてきます。ビニール袋の中に手を入れてこの作業をやらないと、磁石やプラスティックの破片が飛んでいくので、ご注意を 。
。
そして、磁石をつける前に塗装しました。塗装は合成うるしの透と透明を混ぜて1度、本透明を1度、それぞれ拭き塗りをしました。乾燥後、磁石をつけます。一辺3個ずつ左右両面に付けますので、12個の穴を彫刻刀と電動ルーターを使って慎重に開けました。磁石の木部への接着は瞬間接着剤だと不安なので、2液性のエポキシを使いました。水色?緑?のマットは100円ショップの机用マット(発泡材のようなもの)です。

なかなかいい感じに仕上がりました 。磁石の開け閉めも横にずらすようにして開閉するととてもスムーズ。磁石も強力なので、しっかり閉まります。
。磁石の開け閉めも横にずらすようにして開閉するととてもスムーズ。磁石も強力なので、しっかり閉まります。
次におまけですが、ウキもまだ大量に持って行くような釣りもしていないので、片側がハリスケースにもできればいいなと部品を作ってみました。ステンレスのパイプと今回の端材です。

これを組み立ててみるとこんな感じになります 。
。

まずはこれで実戦に投入してみます 。
。
土曜日は、磯の予定、海が荒れていたらへらのつもりでしたが、前夜に突如飲みのお誘いが・・・
 。不覚にも飲み過ぎてしまい、土曜は二日酔い
。不覚にも飲み過ぎてしまい、土曜は二日酔い 。磯は早々にあきらめ、昼まで寝てなんとかへらには行こうと思っていましたが、頭痛と胃の不快感は取れず、釣りはあきらめました
。磯は早々にあきらめ、昼まで寝てなんとかへらには行こうと思っていましたが、頭痛と胃の不快感は取れず、釣りはあきらめました 。せめて、日曜日は子連れでへらに行こうかと思っておりましたが、雨
。せめて、日曜日は子連れでへらに行こうかと思っておりましたが、雨 で、これも実現できず
で、これも実現できず 。
。・・・ということで、週末は工作することに
 。浮子ケースの製作です。木材はホームセンターで、天板および底板用にアガチス600×90×3(長さ・幅・厚さ)を2枚、側面用にヒノキ910×15×9(同)を2本購入。それを切って組み立てました。
。浮子ケースの製作です。木材はホームセンターで、天板および底板用にアガチス600×90×3(長さ・幅・厚さ)を2枚、側面用にヒノキ910×15×9(同)を2本購入。それを切って組み立てました。
写真のように重ねた時の仕上がり寸法は、約380×90×36(長さ・幅・高さ)です。今回側面のヒノキは上下それぞれ15mmのものを使いましたが、本当は30mmのものを使って一旦箱を作り、それを真ん中でフタと底側に切断すると噛み合わせが揃い、また木材のクセが同じ方向になるので、上手く作れるようです。わたしの場合、それを知ったのが材料を購入した後だったこともあり、万力を乗せて、噛み合わせがフィットするように癖をつけました
 。
。天板と底板は木工用ボンドで張り付けただけなんですが、側面は強化するために竹串で2cmほどの釘をつくり、それを打ち込んでいます。

天板の余った材料とマット剤を使い、中の仕切り(ウキ尻を差し込むところやウキのトップを押さえるところ)を作りました。下の写真はウキ尻を差し込む部分です。マット材を2枚に重ねて、上になる方に三角の切りこみ(+縦の切りこみ)を入れています。

これら部材をセットして、木工部分は完了しました
 。
。
試しにウキを入れてみると、なかなかいい感じです

 。左右ともに上下7本ずつで合計28本。通常使用で33cmまで、片側の仕切りをはずすと最長35.5cmのウキまで入ります。
。左右ともに上下7本ずつで合計28本。通常使用で33cmまで、片側の仕切りをはずすと最長35.5cmのウキまで入ります。次に左右の接続ですが、一般的な蝶番と磁石を使おうと思いましたが、蝶番をきれいにつけるのは結構難しい上に、小型の蝶番に合う細い木ネジが見つからなかったので(普通の釘だとすぐに緩んでくるため)、全部磁石で付けることとしました。ただ、使い勝手が悪くなると嫌だなと思って、インターネットで調べてるとプロの作品でも全部磁石のものがあることを発見したので、安心して全部磁石でやることに・・・。使った磁石はこちら
 。
。
100円ショップで購入。ピン型になっていますが、ニッパで挟んで力を入れると簡単に割れて、中の磁石だけでてきます。ビニール袋の中に手を入れてこの作業をやらないと、磁石やプラスティックの破片が飛んでいくので、ご注意を
 。
。そして、磁石をつける前に塗装しました。塗装は合成うるしの透と透明を混ぜて1度、本透明を1度、それぞれ拭き塗りをしました。乾燥後、磁石をつけます。一辺3個ずつ左右両面に付けますので、12個の穴を彫刻刀と電動ルーターを使って慎重に開けました。磁石の木部への接着は瞬間接着剤だと不安なので、2液性のエポキシを使いました。水色?緑?のマットは100円ショップの机用マット(発泡材のようなもの)です。

なかなかいい感じに仕上がりました
 。磁石の開け閉めも横にずらすようにして開閉するととてもスムーズ。磁石も強力なので、しっかり閉まります。
。磁石の開け閉めも横にずらすようにして開閉するととてもスムーズ。磁石も強力なので、しっかり閉まります。次におまけですが、ウキもまだ大量に持って行くような釣りもしていないので、片側がハリスケースにもできればいいなと部品を作ってみました。ステンレスのパイプと今回の端材です。

これを組み立ててみるとこんな感じになります
 。
。
まずはこれで実戦に投入してみます
 。
。 タグ :浮子ケース
2012年03月02日
研ぎ出してみた!
3月2日(金)
前回竹脚のかやウキ2本を下塗りをあわせて6~7回合成うるしを塗った後、乾燥させていましたが、数日そのままにして十分に乾燥させる予定でした。しかし、やはり待ちきれず、「試作だからいいや」と次の日その日の夜には研ぎ出しをやってしまいました・・・ 。水やすりは400番、600番、1000番を使いました。ドキドキしながら・・・
。水やすりは400番、600番、1000番を使いました。ドキドキしながら・・・ 。そして研ぎ出しました。
。そして研ぎ出しました。
「おおーっ、結構いけてるんちゃうん 」
」
思ったより、きれいに模様が出てました 。それから二晩。うるしの本透明を2度塗りして塗りは完了。こちらです。
。それから二晩。うるしの本透明を2度塗りして塗りは完了。こちらです。

ピッカピカ 。前回の竹片の試し塗りとは少し違う塗りをしています。「黒・赤・金
。前回の竹片の試し塗りとは少し違う塗りをしています。「黒・赤・金 」・・・まるで某メーカーのまわし者のようです。
」・・・まるで某メーカーのまわし者のようです。
そして、トップのソリッドを切断の上、パイプトップの内径にあわせてデザインナイフとやすりで削り、ウキを完成させました 。
。

「おー、ワンダフル~! 」
」
ただ、このウキはちょっと傾いてるんです 。こんなに最初からうまくいくはずではなかったので、トップや脚が少し傾いたまま塗装をしてしまいました・・・
。こんなに最初からうまくいくはずではなかったので、トップや脚が少し傾いたまま塗装をしてしまいました・・・ 。
。
脚を瞬間接着剤を使って、いっきに固めるとこんなことになります。せめて接着する前に型をつけるか、あるいはやはり瞬間接着剤ではないものを使って、調整できる余地を残すかが必要です。まあ、次はそうしますです・・・ハイ 。
。
ところで、明日は晴れ 。久しぶりに磯に行きたいのですが、わたしの使っている天気予報では、強風予想・・・
。久しぶりに磯に行きたいのですが、わたしの使っている天気予報では、強風予想・・・ 。この強風予想の時に磯に行くと、だいたいとんでもない目にあうんです
。この強風予想の時に磯に行くと、だいたいとんでもない目にあうんです 。ただ、朝になると強風から弱風に変わっていることもあるので、明朝起きたとき次第かな・・・
。ただ、朝になると強風から弱風に変わっていることもあるので、明朝起きたとき次第かな・・・ 。だめならヘラで、このウキ使ってきます・・・
。だめならヘラで、このウキ使ってきます・・・ 。
。
前回竹脚のかやウキ2本を下塗りをあわせて6~7回合成うるしを塗った後、乾燥させていましたが、数日そのままにして十分に乾燥させる予定でした。しかし、やはり待ちきれず、「試作だからいいや」と
 。水やすりは400番、600番、1000番を使いました。ドキドキしながら・・・
。水やすりは400番、600番、1000番を使いました。ドキドキしながら・・・ 。そして研ぎ出しました。
。そして研ぎ出しました。「おおーっ、結構いけてるんちゃうん
 」
」思ったより、きれいに模様が出てました
 。それから二晩。うるしの本透明を2度塗りして塗りは完了。こちらです。
。それから二晩。うるしの本透明を2度塗りして塗りは完了。こちらです。
ピッカピカ
 。前回の竹片の試し塗りとは少し違う塗りをしています。「黒・赤・金
。前回の竹片の試し塗りとは少し違う塗りをしています。「黒・赤・金 」・・・まるで某メーカーのまわし者のようです。
」・・・まるで某メーカーのまわし者のようです。そして、トップのソリッドを切断の上、パイプトップの内径にあわせてデザインナイフとやすりで削り、ウキを完成させました
 。
。
「おー、ワンダフル~!
 」
」ただ、このウキはちょっと傾いてるんです
 。こんなに最初からうまくいくはずではなかったので、トップや脚が少し傾いたまま塗装をしてしまいました・・・
。こんなに最初からうまくいくはずではなかったので、トップや脚が少し傾いたまま塗装をしてしまいました・・・ 。
。脚を瞬間接着剤を使って、いっきに固めるとこんなことになります。せめて接着する前に型をつけるか、あるいはやはり瞬間接着剤ではないものを使って、調整できる余地を残すかが必要です。まあ、次はそうしますです・・・ハイ
 。
。ところで、明日は晴れ
 。久しぶりに磯に行きたいのですが、わたしの使っている天気予報では、強風予想・・・
。久しぶりに磯に行きたいのですが、わたしの使っている天気予報では、強風予想・・・ 。この強風予想の時に磯に行くと、だいたいとんでもない目にあうんです
。この強風予想の時に磯に行くと、だいたいとんでもない目にあうんです 。ただ、朝になると強風から弱風に変わっていることもあるので、明朝起きたとき次第かな・・・
。ただ、朝になると強風から弱風に変わっていることもあるので、明朝起きたとき次第かな・・・ 。だめならヘラで、このウキ使ってきます・・・
。だめならヘラで、このウキ使ってきます・・・ 。
。 2012年02月28日
ウキを作る ~その後
2月28日(火)
先日作成したウキです。脚を黒く塗ると見た目が少し締まりました 。ウキトップ塗装用の黒いハケ付きラッカーを使いました。
。ウキトップ塗装用の黒いハケ付きラッカーを使いました。

この土日で、すでに実戦にも投入。あたりもばっちりわかりました。ボディー形状はもちろん大切だと思いますが、要はトップの浮力でエサを背負い、あたりを表現するわけなので、素人ウキにはトップの選択が非常に重要だなと思いました。これさえ、間違えなければ、とりあえずあたりを表現できるウキにはなるようです 。
。
さて、機能性は徐々に高めていくこととして、満足度をすぐに高めるには、見た目の改善ですね・・・ 。そこで、まず脚を竹で作成しました。
。そこで、まず脚を竹で作成しました。

左側です。右側はすでに1番目の写真の上端と下端が黒色の長い方のウキに仕上がってます。竹は編み棒0号を削って使いました。竹串でもいいのですが、焼き入れをしたり、曲げをとったりしないといけないので、すでにまっすぐにしてある編み棒は便利です 。
。
そして、やはり塗装です。ウレタン塗っておけば、機能的には問題ないのですが、やはりうるし(合成)を塗ってきれいなウキを作ってみたくなります。単色塗りはすでにやっていますが、研ぎだしなどの塗りはやったことがないので、まずは、不要な竹片で練習がてらに試し塗りをしてみました。

いろいろなホームページを見て、なんとなくこうするのかな?というやり方で実験してみました。とりあえず、それっぽく見えます 。
。
・・・ということで、この手法でいってみようと現在竹脚の2本を乾燥中です。

この次の工程が研ぎだし(水やすりで磨いて、中に重ねた色を出していきます)、それが終わると仕上げ塗りになります。
試し塗りの竹片より丁寧にやってしまったのが、吉と出るか凶と出るか微妙な感じ・・・ 。たぶん、大胆にやる方が、良い結果が生まれそうな気がしてます。
。たぶん、大胆にやる方が、良い結果が生まれそうな気がしてます。
まあ、こればかりは研いでみないとわからないので、後日のお楽しみということで・・・
先日作成したウキです。脚を黒く塗ると見た目が少し締まりました
 。ウキトップ塗装用の黒いハケ付きラッカーを使いました。
。ウキトップ塗装用の黒いハケ付きラッカーを使いました。
この土日で、すでに実戦にも投入。あたりもばっちりわかりました。ボディー形状はもちろん大切だと思いますが、要はトップの浮力でエサを背負い、あたりを表現するわけなので、素人ウキにはトップの選択が非常に重要だなと思いました。これさえ、間違えなければ、とりあえずあたりを表現できるウキにはなるようです
 。
。さて、機能性は徐々に高めていくこととして、満足度をすぐに高めるには、見た目の改善ですね・・・
 。そこで、まず脚を竹で作成しました。
。そこで、まず脚を竹で作成しました。
左側です。右側はすでに1番目の写真の上端と下端が黒色の長い方のウキに仕上がってます。竹は編み棒0号を削って使いました。竹串でもいいのですが、焼き入れをしたり、曲げをとったりしないといけないので、すでにまっすぐにしてある編み棒は便利です
 。
。そして、やはり塗装です。ウレタン塗っておけば、機能的には問題ないのですが、やはりうるし(合成)を塗ってきれいなウキを作ってみたくなります。単色塗りはすでにやっていますが、研ぎだしなどの塗りはやったことがないので、まずは、不要な竹片で練習がてらに試し塗りをしてみました。

いろいろなホームページを見て、なんとなくこうするのかな?というやり方で実験してみました。とりあえず、それっぽく見えます
 。
。・・・ということで、この手法でいってみようと現在竹脚の2本を乾燥中です。

この次の工程が研ぎだし(水やすりで磨いて、中に重ねた色を出していきます)、それが終わると仕上げ塗りになります。
試し塗りの竹片より丁寧にやってしまったのが、吉と出るか凶と出るか微妙な感じ・・・
 。たぶん、大胆にやる方が、良い結果が生まれそうな気がしてます。
。たぶん、大胆にやる方が、良い結果が生まれそうな気がしてます。まあ、こればかりは研いでみないとわからないので、後日のお楽しみということで・・・

2012年02月23日
1日でウキを作る Part3
2月23日(木)
【Part3:塗装】
塗装は、ボディー部だけにします。性能にはほとんど影響ないでしょうから、脚はソリッドむき出しです。パイプトップも今回はすでに着色された既製品を使用することにしました。
まず、上下の絞り部分の溝を隠すために、厚化粧することに・・・ 。合成うるしを塗ればできるのですが、乾燥時間が丸一日かかります。しかも何度か重ね塗りをしなければなりませんので数日かかります。1日でウキを作るのが目標なので、まず家にあったアクリル絵の具を使ってみました。
。合成うるしを塗ればできるのですが、乾燥時間が丸一日かかります。しかも何度か重ね塗りをしなければなりませんので数日かかります。1日でウキを作るのが目標なので、まず家にあったアクリル絵の具を使ってみました。
マスキングをして塗りましたが、マスキングテープとの境目に段差ができてしまうので、乾いてすぐに剥がしました 。でも、あら不思議・・・溝には絵の具がしっかりと入り、パテ埋め状態になってました
。でも、あら不思議・・・溝には絵の具がしっかりと入り、パテ埋め状態になってました (まあ着色する場合には、普通に木材用パテで埋めればいいだけのことなんですけど・・・)。
(まあ着色する場合には、普通に木材用パテで埋めればいいだけのことなんですけど・・・)。

・・・で、もっとも邪道かつ簡単な方法のマジックで塗ることにしました。この前ハンズで購入したCOPICを使いました。自作竿に名入れとかする目的で、衝動買いしたのですが(高いです。1本450円もします・・・ )、水性顔料インクで、乾くと耐水性ということで、製図やマンガを描く人とかが使っているそうです。油性ペンだと塗装と反応して、インク流れが起こるようなので、ご注意ください。ついでにこの段階でウキに名入れをしました。(【後日談】:名入れや水性塗料での着色は、下地用のウレタンを塗って乾燥させ、ヤスリで軽く磨いて、平らにした後がたぶん正解です。)
)、水性顔料インクで、乾くと耐水性ということで、製図やマンガを描く人とかが使っているそうです。油性ペンだと塗装と反応して、インク流れが起こるようなので、ご注意ください。ついでにこの段階でウキに名入れをしました。(【後日談】:名入れや水性塗料での着色は、下地用のウレタンを塗って乾燥させ、ヤスリで軽く磨いて、平らにした後がたぶん正解です。)

水性マジックのため、すぐに乾きますので、次に一番簡単な1液性ウレタン塗料のドブ付けをしました。後ろに写った2本は東京でボディーを作った分です。

早く乾かすために、風呂場の暖房をつけてやりました。2度塗りの予定でしたので、次が塗りたくて我慢してましたが、4時間経ったところで我慢も限界になったので、少し早いかなと思いつつ2度目を・・・。今度はもっと早く乾かしてやろうと暖房用のオイルヒーターの上部に吊るして強制的に乾かしました 。・・・が、同様に4時間待ってウキを見ると表面に泡やブツブツが・・・
。・・・が、同様に4時間待ってウキを見ると表面に泡やブツブツが・・・ 。1度目のが十分に乾いていなかったため、しわが出たのか、熱で気泡でも出てしまったのでしょうか・・・
。1度目のが十分に乾いていなかったため、しわが出たのか、熱で気泡でも出てしまったのでしょうか・・・ 。仕方ないので、表面の泡やぶつぶつを1000番ヤスリで軽く水研ぎし、3度目塗りました。ただ、ちょうど夜でしたので、そのまま就寝しました
。仕方ないので、表面の泡やぶつぶつを1000番ヤスリで軽く水研ぎし、3度目塗りました。ただ、ちょうど夜でしたので、そのまま就寝しました 。
。
そして翌朝になり、しっかりと乾燥しているのを確認。自動車用のコンパウンドで磨き、塗装は完了。次は実際に水に浮かせて最終調整です。そのままだとトップが長すぎてバランスが悪いので、トップを少し切るとともに、もう少しオモリを背負えるように脚も切って、2Bの錘で(フカセマンには、ガンダマがイメージしやすい )バランスするように調整しました。針とサルカンを付けたエサ落ち目盛は、もう1~2目盛上になるでしょうから、ぴったりです。なお、トップを長くし過ぎると、表面張力が勝って、立たないウキになりますので、ご注意ください(石鹸でウキを洗うと大丈夫になるケースもあります)。
)バランスするように調整しました。針とサルカンを付けたエサ落ち目盛は、もう1~2目盛上になるでしょうから、ぴったりです。なお、トップを長くし過ぎると、表面張力が勝って、立たないウキになりますので、ご注意ください(石鹸でウキを洗うと大丈夫になるケースもあります)。

最後にトップを瞬間接着剤でとめて完成です
 。強制乾燥の塗装事故があったので、前日中に完成しませんでしたが、前日は昼から始めたので、24時間以内で完成しました
。強制乾燥の塗装事故があったので、前日中に完成しませんでしたが、前日は昼から始めたので、24時間以内で完成しました 。ウレタン2度塗りなら十分その日の内に完成できたと思います。
。ウレタン2度塗りなら十分その日の内に完成できたと思います。
東京でボディーを作った分は、先週家に戻ってから、エポキシボンドを下塗りと防水のための塗料代わりに、ウレタン薄め液で薄めて塗りました(邪道です )。乾燥させるのに普通10分のものが、丸1日かかりました・・・
)。乾燥させるのに普通10分のものが、丸1日かかりました・・・ )。そして、その上から合成うるしの透と透明を混ぜて、3度塗りしました(3日間)。木工用ボンドを乾かすのにも2晩かかってましたから(最初の接着と修正の接着)、結局約1週間かかったことになります
)。そして、その上から合成うるしの透と透明を混ぜて、3度塗りしました(3日間)。木工用ボンドを乾かすのにも2晩かかってましたから(最初の接着と修正の接着)、結局約1週間かかったことになります 。
。
今回のように瞬間接着剤を使用して製作した場合、失敗すると調整不可で後戻りできませんが、すぐにやり直せるので、作り方に慣れるまではこの方法でやって、上手になったら精度や塗りも意識して、じっくり取り組むのが良いのではと思いました 。
。
以上、「1日でウキを作る」でした。お粗末さまでした 。
。
【Part3:塗装】
塗装は、ボディー部だけにします。性能にはほとんど影響ないでしょうから、脚はソリッドむき出しです。パイプトップも今回はすでに着色された既製品を使用することにしました。
まず、上下の絞り部分の溝を隠すために、厚化粧することに・・・
 。合成うるしを塗ればできるのですが、乾燥時間が丸一日かかります。しかも何度か重ね塗りをしなければなりませんので数日かかります。1日でウキを作るのが目標なので、まず家にあったアクリル絵の具を使ってみました。
。合成うるしを塗ればできるのですが、乾燥時間が丸一日かかります。しかも何度か重ね塗りをしなければなりませんので数日かかります。1日でウキを作るのが目標なので、まず家にあったアクリル絵の具を使ってみました。マスキングをして塗りましたが、マスキングテープとの境目に段差ができてしまうので、乾いてすぐに剥がしました
 。でも、あら不思議・・・溝には絵の具がしっかりと入り、パテ埋め状態になってました
。でも、あら不思議・・・溝には絵の具がしっかりと入り、パテ埋め状態になってました (まあ着色する場合には、普通に木材用パテで埋めればいいだけのことなんですけど・・・)。
(まあ着色する場合には、普通に木材用パテで埋めればいいだけのことなんですけど・・・)。
・・・で、もっとも邪道かつ簡単な方法のマジックで塗ることにしました。この前ハンズで購入したCOPICを使いました。自作竿に名入れとかする目的で、衝動買いしたのですが(高いです。1本450円もします・・・
 )、水性顔料インクで、乾くと耐水性ということで、製図やマンガを描く人とかが使っているそうです。油性ペンだと塗装と反応して、インク流れが起こるようなので、ご注意ください。ついでにこの段階でウキに名入れをしました。(【後日談】:名入れや水性塗料での着色は、下地用のウレタンを塗って乾燥させ、ヤスリで軽く磨いて、平らにした後がたぶん正解です。)
)、水性顔料インクで、乾くと耐水性ということで、製図やマンガを描く人とかが使っているそうです。油性ペンだと塗装と反応して、インク流れが起こるようなので、ご注意ください。ついでにこの段階でウキに名入れをしました。(【後日談】:名入れや水性塗料での着色は、下地用のウレタンを塗って乾燥させ、ヤスリで軽く磨いて、平らにした後がたぶん正解です。)
水性マジックのため、すぐに乾きますので、次に一番簡単な1液性ウレタン塗料のドブ付けをしました。後ろに写った2本は東京でボディーを作った分です。

早く乾かすために、風呂場の暖房をつけてやりました。2度塗りの予定でしたので、次が塗りたくて我慢してましたが、4時間経ったところで我慢も限界になったので、少し早いかなと思いつつ2度目を・・・。今度はもっと早く乾かしてやろうと暖房用のオイルヒーターの上部に吊るして強制的に乾かしました
 。・・・が、同様に4時間待ってウキを見ると表面に泡やブツブツが・・・
。・・・が、同様に4時間待ってウキを見ると表面に泡やブツブツが・・・ 。1度目のが十分に乾いていなかったため、しわが出たのか、熱で気泡でも出てしまったのでしょうか・・・
。1度目のが十分に乾いていなかったため、しわが出たのか、熱で気泡でも出てしまったのでしょうか・・・ 。仕方ないので、表面の泡やぶつぶつを1000番ヤスリで軽く水研ぎし、3度目塗りました。ただ、ちょうど夜でしたので、そのまま就寝しました
。仕方ないので、表面の泡やぶつぶつを1000番ヤスリで軽く水研ぎし、3度目塗りました。ただ、ちょうど夜でしたので、そのまま就寝しました 。
。そして翌朝になり、しっかりと乾燥しているのを確認。自動車用のコンパウンドで磨き、塗装は完了。次は実際に水に浮かせて最終調整です。そのままだとトップが長すぎてバランスが悪いので、トップを少し切るとともに、もう少しオモリを背負えるように脚も切って、2Bの錘で(フカセマンには、ガンダマがイメージしやすい
 )バランスするように調整しました。針とサルカンを付けたエサ落ち目盛は、もう1~2目盛上になるでしょうから、ぴったりです。なお、トップを長くし過ぎると、表面張力が勝って、立たないウキになりますので、ご注意ください(石鹸でウキを洗うと大丈夫になるケースもあります)。
)バランスするように調整しました。針とサルカンを付けたエサ落ち目盛は、もう1~2目盛上になるでしょうから、ぴったりです。なお、トップを長くし過ぎると、表面張力が勝って、立たないウキになりますので、ご注意ください(石鹸でウキを洗うと大丈夫になるケースもあります)。
最後にトップを瞬間接着剤でとめて完成です

 。強制乾燥の塗装事故があったので、前日中に完成しませんでしたが、前日は昼から始めたので、24時間以内で完成しました
。強制乾燥の塗装事故があったので、前日中に完成しませんでしたが、前日は昼から始めたので、24時間以内で完成しました 。ウレタン2度塗りなら十分その日の内に完成できたと思います。
。ウレタン2度塗りなら十分その日の内に完成できたと思います。東京でボディーを作った分は、先週家に戻ってから、エポキシボンドを下塗りと防水のための塗料代わりに、ウレタン薄め液で薄めて塗りました(邪道です
 )。乾燥させるのに普通10分のものが、丸1日かかりました・・・
)。乾燥させるのに普通10分のものが、丸1日かかりました・・・ )。そして、その上から合成うるしの透と透明を混ぜて、3度塗りしました(3日間)。木工用ボンドを乾かすのにも2晩かかってましたから(最初の接着と修正の接着)、結局約1週間かかったことになります
)。そして、その上から合成うるしの透と透明を混ぜて、3度塗りしました(3日間)。木工用ボンドを乾かすのにも2晩かかってましたから(最初の接着と修正の接着)、結局約1週間かかったことになります 。
。今回のように瞬間接着剤を使用して製作した場合、失敗すると調整不可で後戻りできませんが、すぐにやり直せるので、作り方に慣れるまではこの方法でやって、上手になったら精度や塗りも意識して、じっくり取り組むのが良いのではと思いました
 。
。以上、「1日でウキを作る」でした。お粗末さまでした
 。
。 タグ :浮子
2012年02月22日
1日でウキを作る Part2
2月22日(水)
【Part2:ボディー成型】
では、塗装する前までのボディーを成型するところです。まずは、切削が完了したカヤの中心部分にグラスソリッドをゆっくりとまっすぐになるように慎重に差し込んでみます。

今回はウキのボディーが6cmと短いので、通し差しにすることにしましたが、脚には竹やカーボンなど違う素材や違う径のソリッドを使用するケースも多く、おまけにソリッドの通し差しだと少し重くなるので、脚とトップのソリッドは別のものを使うことの方が一般的だと思います。

写真のようにカッティングボードの線などを見ながらやると、わりとまっすぐ入れやすいと思います。なお、写真のカッティングボードはアメリカ在住時に購入したものなので、数字はインチ表示で、cmではありませんのでご注意ください。
次に指し込んだソリッドを一旦抜き、ゼリータイプの瞬間接着剤をボディーの中心部の穴を目がけて垂らします。そしてソリッドを回しながら一気に指し込みます。回しながらすると接着剤が中に入っていきます。ゆっくりやりすぎると途中で瞬間接着剤が固まってしまい、どうしようもなくなります 。わたしは間一髪でした
。わたしは間一髪でした 。
。
そして今度は開いた部分に液体の瞬間接着剤を塗ってから、すばやくタコ糸をグルグル巻きにしました。マスキングテープは巻いたままでOK。糸が滑らないので簡単に巻けます。トップとボトムと順にやります。おそらく状態が見えるからだと思いますが、一般的には細い糸を隙間をあけて巻くようです。太いタコ糸だと状態は見ませんが、瞬間接着剤を使用しているのでいずれにせよ修正は効かないため、全体的に力が入りやすい太いタコ糸を使用しました。

5分もすれば乾いていますので、慎重に糸をほどきます。糸も瞬間接着剤で少し固まっていましたが、それほど苦労せずに取れました。

次にマスキングテープがあるので、それもはずしました。カヤの表面はそれほど瞬間接着剤がついていませんでしたが、少々ガビガビにはなっていました 。
。

そして、全体的に紙やすり400番程度で磨きました。ガビガビは簡単に取れました。・・・が、あわせの部分に隙間がありました。木工用ボンドでつけていると、この程度は瞬間接着剤をつけて再度糸で縛ると簡単に修正できるのですが、最初から瞬間接着剤なので、修正不可です。塗りのところでごまかすことにしました。試しにトップも付けてみました。良い感じです
 。
。

~ 【Part3:塗装】に続く ~
【Part2:ボディー成型】
では、塗装する前までのボディーを成型するところです。まずは、切削が完了したカヤの中心部分にグラスソリッドをゆっくりとまっすぐになるように慎重に差し込んでみます。

今回はウキのボディーが6cmと短いので、通し差しにすることにしましたが、脚には竹やカーボンなど違う素材や違う径のソリッドを使用するケースも多く、おまけにソリッドの通し差しだと少し重くなるので、脚とトップのソリッドは別のものを使うことの方が一般的だと思います。

写真のようにカッティングボードの線などを見ながらやると、わりとまっすぐ入れやすいと思います。なお、写真のカッティングボードはアメリカ在住時に購入したものなので、数字はインチ表示で、cmではありませんのでご注意ください。
次に指し込んだソリッドを一旦抜き、ゼリータイプの瞬間接着剤をボディーの中心部の穴を目がけて垂らします。そしてソリッドを回しながら一気に指し込みます。回しながらすると接着剤が中に入っていきます。ゆっくりやりすぎると途中で瞬間接着剤が固まってしまい、どうしようもなくなります
 。わたしは間一髪でした
。わたしは間一髪でした 。
。そして今度は開いた部分に液体の瞬間接着剤を塗ってから、すばやくタコ糸をグルグル巻きにしました。マスキングテープは巻いたままでOK。糸が滑らないので簡単に巻けます。トップとボトムと順にやります。おそらく状態が見えるからだと思いますが、一般的には細い糸を隙間をあけて巻くようです。太いタコ糸だと状態は見ませんが、瞬間接着剤を使用しているのでいずれにせよ修正は効かないため、全体的に力が入りやすい太いタコ糸を使用しました。

5分もすれば乾いていますので、慎重に糸をほどきます。糸も瞬間接着剤で少し固まっていましたが、それほど苦労せずに取れました。

次にマスキングテープがあるので、それもはずしました。カヤの表面はそれほど瞬間接着剤がついていませんでしたが、少々ガビガビにはなっていました
 。
。
そして、全体的に紙やすり400番程度で磨きました。ガビガビは簡単に取れました。・・・が、あわせの部分に隙間がありました。木工用ボンドでつけていると、この程度は瞬間接着剤をつけて再度糸で縛ると簡単に修正できるのですが、最初から瞬間接着剤なので、修正不可です。塗りのところでごまかすことにしました。試しにトップも付けてみました。良い感じです

 。
。
~ 【Part3:塗装】に続く ~
タグ :浮子
2012年02月21日
1日でウキを作る Part1
2月21日(火)
ヘラ用に竿掛けや玉網、竿まで作ったのだから、やはりウキも作らんとあかんな~と・・・ 。
。
先週ちょっと記事にした通り、東京へ仕事に行っている間にホテルでウキのボディー作りをやってみましたが、結構時間がかかりました。トップと脚の絞り部分の切りだしは刃が一気に入って失敗したり、紙ヤスリで削っているとカヤ素材が割れたりします。その上、木工用ボンドは乾燥に時間がかかるので、修正はしやすいのですが、すぐに次の作業に移れません。釣りをする人は気が短いとよく言いますが、ご多分にもれず、わたしも接着剤や塗装の乾燥待ちが大嫌いです 。
。
もちろん丁寧に作業し、時間も余裕を持って、作る方が良い物ができるのはわかっていますが、もっと簡単に、しかも早く仕上げる方法はないものかと考えながら、1日でウキを作るを目指してみることにしました 。
。
なお、カヤウキ作りの基本は、東邦産業のHPにあるヘラ浮子の作り方を主に参照しました。
まず今回の材料および製作道具です。
・ 5~6mm径のカヤ
・ グラスソリッドの1mm(脚およびパイプトップ固定用ソリッド)
・ 既成のテーパー付き極細パイプトップ(長さ12mm、元外径1.2mm、元内径約0.8mm)
・ 100円ショップの瞬間接着剤(液体とゼリーの2種)
・ OLFAの超極薄0.2mmのカッター(片刃カミソリを見つけられなかったので)
・ マスキング用テープ(医療用の包帯止めるようなやつ)
・ タコ糸
・ 紙ヤスリ(240番、400番、600番、1000番)
・ 1液性ウレタン
・ マジックとアクリル絵の具、定規、はさみ、その他
今回の完成品です 。
。

なお、以下に記載する製作方法はウキ作り初心者によるお試し的なものなので、次回はぜんぜん違う方法で作っているかもしれません。あしからず・・・。経験者の皆様、もっと簡単に作る方法をご存知でしたら、ぜひ教えてください。よろしく~ 。では、ウキ作りのスタートです
。では、ウキ作りのスタートです 。
。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【Part1:カヤ切削】
まずカヤを今回は6cmにカット。前回東京では10cmでやりました。転がしながらカッターで切り、切り口はヤスリで整えました。前回絞り部分を切りこむのに苦労したので、トップと脚ともに絞り予定部分(+α)にテープを貼り、洗面所からメイク用ハサミをこっそり取り出し 、それで切って仕上げることを考えましたが、実験するとやはりカヤが割れてしまいましたので、その方法は却下。
、それで切って仕上げることを考えましたが、実験するとやはりカヤが割れてしまいましたので、その方法は却下。
そこで、テープは鉛筆で線を引けるようにマスキング用テープに変え、普通にカッターで切ることにしました(カッターは極薄刃でないと素材が割れます)。今回は、トップの絞りを8mm、脚の絞りを30mmにしました。

一般的には、テープは貼らずに青線部分のように4分割してから、赤線のところまで、少しずつカッターや紙やすりで整えていくようですが、マスキングテープにきっちりと図面を描いているので、いきなり赤線のところを斜めに刃を入れて切っていきました。少しずつ慎重に削らなくてよい上に、テープで刃が滑らず簡単に切れたので、作業時間は少なく済みました 。おまけに面倒なので、定規などは使わずフリーハンドで線を描いてます
。おまけに面倒なので、定規などは使わずフリーハンドで線を描いてます 。。(【後日談】:定規あるいはプラスティックの板等を使用して、線をきっちり描くと、隙間も少なく、仕上がりがかなりきれいになりますので、こちらがお勧めです。)
。。(【後日談】:定規あるいはプラスティックの板等を使用して、線をきっちり描くと、隙間も少なく、仕上がりがかなりきれいになりますので、こちらがお勧めです。)
これが切った直後の写真です。かなり適当なことがお分かりいただけるでしょう・・・(笑)。

次に溝部分に紙やすりを差し込んで側面にもあてながら前後に軽く往復して削っていきました。

まったく力を入れる必要はなく、無理にワタを取ろうとしなくても簡単に削れました。そして、紙やすりを反対向きにして、反対面も・・・。そして90度回して同様に。深さが予定の絞り幅の線に達するところまで削ります。
削り終えるとこんな感じになりました 。
。

意外とうまくいきました 。
。
脚側の絞りも同様にカッターで切って、紙やすりを差し込んで削って、カヤ切削の工程はあっという間に終了しました 。
。
~ 【Part2:ボディー成型】に続く ~
ヘラ用に竿掛けや玉網、竿まで作ったのだから、やはりウキも作らんとあかんな~と・・・
 。
。先週ちょっと記事にした通り、東京へ仕事に行っている間にホテルでウキのボディー作りをやってみましたが、結構時間がかかりました。トップと脚の絞り部分の切りだしは刃が一気に入って失敗したり、紙ヤスリで削っているとカヤ素材が割れたりします。その上、木工用ボンドは乾燥に時間がかかるので、修正はしやすいのですが、すぐに次の作業に移れません。釣りをする人は気が短いとよく言いますが、ご多分にもれず、わたしも接着剤や塗装の乾燥待ちが大嫌いです
 。
。もちろん丁寧に作業し、時間も余裕を持って、作る方が良い物ができるのはわかっていますが、もっと簡単に、しかも早く仕上げる方法はないものかと考えながら、1日でウキを作るを目指してみることにしました
 。
。なお、カヤウキ作りの基本は、東邦産業のHPにあるヘラ浮子の作り方を主に参照しました。
まず今回の材料および製作道具です。
・ 5~6mm径のカヤ
・ グラスソリッドの1mm(脚およびパイプトップ固定用ソリッド)
・ 既成のテーパー付き極細パイプトップ(長さ12mm、元外径1.2mm、元内径約0.8mm)
・ 100円ショップの瞬間接着剤(液体とゼリーの2種)
・ OLFAの超極薄0.2mmのカッター(片刃カミソリを見つけられなかったので)
・ マスキング用テープ(医療用の包帯止めるようなやつ)
・ タコ糸
・ 紙ヤスリ(240番、400番、600番、1000番)
・ 1液性ウレタン
・ マジックとアクリル絵の具、定規、はさみ、その他
今回の完成品です
 。
。
なお、以下に記載する製作方法はウキ作り初心者によるお試し的なものなので、次回はぜんぜん違う方法で作っているかもしれません。あしからず・・・。経験者の皆様、もっと簡単に作る方法をご存知でしたら、ぜひ教えてください。よろしく~
 。では、ウキ作りのスタートです
。では、ウキ作りのスタートです 。
。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【Part1:カヤ切削】
まずカヤを今回は6cmにカット。前回東京では10cmでやりました。転がしながらカッターで切り、切り口はヤスリで整えました。前回絞り部分を切りこむのに苦労したので、トップと脚ともに絞り予定部分(+α)にテープを貼り、洗面所からメイク用ハサミをこっそり取り出し
 、それで切って仕上げることを考えましたが、実験するとやはりカヤが割れてしまいましたので、その方法は却下。
、それで切って仕上げることを考えましたが、実験するとやはりカヤが割れてしまいましたので、その方法は却下。そこで、テープは鉛筆で線を引けるようにマスキング用テープに変え、普通にカッターで切ることにしました(カッターは極薄刃でないと素材が割れます)。今回は、トップの絞りを8mm、脚の絞りを30mmにしました。

一般的には、テープは貼らずに青線部分のように4分割してから、赤線のところまで、少しずつカッターや紙やすりで整えていくようですが、マスキングテープにきっちりと図面を描いているので、いきなり赤線のところを斜めに刃を入れて切っていきました。少しずつ慎重に削らなくてよい上に、テープで刃が滑らず簡単に切れたので、作業時間は少なく済みました
 。おまけに面倒なので、定規などは使わずフリーハンドで線を描いてます
。おまけに面倒なので、定規などは使わずフリーハンドで線を描いてます 。。(【後日談】:定規あるいはプラスティックの板等を使用して、線をきっちり描くと、隙間も少なく、仕上がりがかなりきれいになりますので、こちらがお勧めです。)
。。(【後日談】:定規あるいはプラスティックの板等を使用して、線をきっちり描くと、隙間も少なく、仕上がりがかなりきれいになりますので、こちらがお勧めです。)これが切った直後の写真です。かなり適当なことがお分かりいただけるでしょう・・・(笑)。

次に溝部分に紙やすりを差し込んで側面にもあてながら前後に軽く往復して削っていきました。

まったく力を入れる必要はなく、無理にワタを取ろうとしなくても簡単に削れました。そして、紙やすりを反対向きにして、反対面も・・・。そして90度回して同様に。深さが予定の絞り幅の線に達するところまで削ります。
削り終えるとこんな感じになりました
 。
。
意外とうまくいきました
 。
。脚側の絞りも同様にカッターで切って、紙やすりを差し込んで削って、カヤ切削の工程はあっという間に終了しました
 。
。~ 【Part2:ボディー成型】に続く ~
タグ :浮子