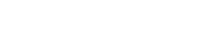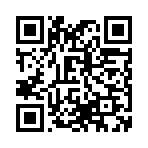2012年07月10日
テーパーと調子
7月10日(火)
昨日完成した5号竿 。4号竿とは違い、3本継ぎにしました。一般的には8尺は3本継ぎだとは思いますが、最初に3号竿を作った際に4本継ぎにしました。これは、使っていた竹がホームセンターで売っている園芸の支柱用の女竹だったこともあり、強度に期待ができないので、短く継ぐとしっかりするのではないかという理由で4本にしたのです。
。4号竿とは違い、3本継ぎにしました。一般的には8尺は3本継ぎだとは思いますが、最初に3号竿を作った際に4本継ぎにしました。これは、使っていた竹がホームセンターで売っている園芸の支柱用の女竹だったこともあり、強度に期待ができないので、短く継ぐとしっかりするのではないかという理由で4本にしたのです。
4号竿も強い竿を目指したので、同じく4本継ぎにしましたが、4本継ぎにすると1本1本が短くなってしまうため、それぞれの竹にはテーパーがほとんどつかず、継ぐことによってその口径差でテーパーをつけているような状態になります。3本継ぎにするとそれぞれの竹が長くなり、素材本来のテーパーを活かすことになるので、それによって調子に違いがでるのでは・・・ということで、今回の5号竿は3本継ぎにしたわけです。写真は上が5号竿、下が4号竿です。

バンブーロッドのサイトを見ていると、テーパーをグラフにしているのをいくつか見つけたので、試しにやってみました 。
。

赤い線だと2ヶ所、青い線だと3ヶ所、グラフ中に縦に1mm分ほどの直線部がありますが、ここが継ぎ部分になります。この1mmが、先の竿と手前の竿の口径差を示しています。青い線は4号竿で4本継ぎなので、継ぎ部分は3ヶ所、赤い線は5号竿で3本継ぎなので2ヶ所です。
穂先の細さ(約1.2mm)も手元の太さ(9.9と9.8mm)もほぼ同じなので、全体としてのテーパーは変わりません。近似曲線は4号竿と5号竿はほとんど同じになります(線だらけになるので表示してません)。なので、同じような調子かもしれませんが、個別に見ると異なります。穂先は5号竿の方が、テーパーがやや緩くしかも長いので、少ししなやかになるのではと想像しています。一方、手元は5号竿のテーパーがかなり強くなります。徐々に手元に乗ってくるような感じになるのかなと・・・。
・・・と数字で遊んでみましたが、実際には矢竹(3番、4番)、高野竹(穂持ち)、真竹(穂先)と竹の種類も違うため、粘りや強度なども異なり、その影響もあるでしょうから、数字をどのように解釈していいかわかりません。ならば、実際に曲げてみるのが一番だということで、糸をつけてペットボトルに水を入れて、曲げてみました 。
。
まずは4号竿 。
。

穂持ちと3番の継ぎ目近くが一番よく曲がってます。これ以上強くすると3番が曲がって行きますので、完全に胴調子という感じでしょうか・・・。
そして5号竿 。こちらの方がやや硬式のようなので、4号竿より少し強く負荷をかけました。
。こちらの方がやや硬式のようなので、4号竿より少し強く負荷をかけました。

4号竿と比べると明らかに先よりの調子です。穂先と穂持ちの継ぎ部分(〇印)で大きく曲がっており、この部分にかなり負担がかかっていそうです。上のグラフではしなやかと表現しましたが、穂先が負けていると言った方が正しいのでしょうか・・・。手元と穂持ちの継ぎ目(矢印部分)は非常にナチュラルです。手元の竹のテーパーがあるのがうまく活かされているのでしょうか・・・。
・・・と実際に曲げて、いろいろと想像してみましたが、やはり実際に釣って確かめたいところです。なので、今度5号竿を試してきます 。
。
こういうことを繰り返していると、だんだんとテーパーとか調子のコントロールの仕方ががわかってくるのでしょうか・・・ 。
。
昨日完成した5号竿
 。4号竿とは違い、3本継ぎにしました。一般的には8尺は3本継ぎだとは思いますが、最初に3号竿を作った際に4本継ぎにしました。これは、使っていた竹がホームセンターで売っている園芸の支柱用の女竹だったこともあり、強度に期待ができないので、短く継ぐとしっかりするのではないかという理由で4本にしたのです。
。4号竿とは違い、3本継ぎにしました。一般的には8尺は3本継ぎだとは思いますが、最初に3号竿を作った際に4本継ぎにしました。これは、使っていた竹がホームセンターで売っている園芸の支柱用の女竹だったこともあり、強度に期待ができないので、短く継ぐとしっかりするのではないかという理由で4本にしたのです。4号竿も強い竿を目指したので、同じく4本継ぎにしましたが、4本継ぎにすると1本1本が短くなってしまうため、それぞれの竹にはテーパーがほとんどつかず、継ぐことによってその口径差でテーパーをつけているような状態になります。3本継ぎにするとそれぞれの竹が長くなり、素材本来のテーパーを活かすことになるので、それによって調子に違いがでるのでは・・・ということで、今回の5号竿は3本継ぎにしたわけです。写真は上が5号竿、下が4号竿です。

バンブーロッドのサイトを見ていると、テーパーをグラフにしているのをいくつか見つけたので、試しにやってみました
 。
。
赤い線だと2ヶ所、青い線だと3ヶ所、グラフ中に縦に1mm分ほどの直線部がありますが、ここが継ぎ部分になります。この1mmが、先の竿と手前の竿の口径差を示しています。青い線は4号竿で4本継ぎなので、継ぎ部分は3ヶ所、赤い線は5号竿で3本継ぎなので2ヶ所です。
穂先の細さ(約1.2mm)も手元の太さ(9.9と9.8mm)もほぼ同じなので、全体としてのテーパーは変わりません。近似曲線は4号竿と5号竿はほとんど同じになります(線だらけになるので表示してません)。なので、同じような調子かもしれませんが、個別に見ると異なります。穂先は5号竿の方が、テーパーがやや緩くしかも長いので、少ししなやかになるのではと想像しています。一方、手元は5号竿のテーパーがかなり強くなります。徐々に手元に乗ってくるような感じになるのかなと・・・。
・・・と数字で遊んでみましたが、実際には矢竹(3番、4番)、高野竹(穂持ち)、真竹(穂先)と竹の種類も違うため、粘りや強度なども異なり、その影響もあるでしょうから、数字をどのように解釈していいかわかりません。ならば、実際に曲げてみるのが一番だということで、糸をつけてペットボトルに水を入れて、曲げてみました
 。
。まずは4号竿
 。
。
穂持ちと3番の継ぎ目近くが一番よく曲がってます。これ以上強くすると3番が曲がって行きますので、完全に胴調子という感じでしょうか・・・。
そして5号竿
 。こちらの方がやや硬式のようなので、4号竿より少し強く負荷をかけました。
。こちらの方がやや硬式のようなので、4号竿より少し強く負荷をかけました。
4号竿と比べると明らかに先よりの調子です。穂先と穂持ちの継ぎ部分(〇印)で大きく曲がっており、この部分にかなり負担がかかっていそうです。上のグラフではしなやかと表現しましたが、穂先が負けていると言った方が正しいのでしょうか・・・。手元と穂持ちの継ぎ目(矢印部分)は非常にナチュラルです。手元の竹のテーパーがあるのがうまく活かされているのでしょうか・・・。
・・・と実際に曲げて、いろいろと想像してみましたが、やはり実際に釣って確かめたいところです。なので、今度5号竿を試してきます
 。
。こういうことを繰り返していると、だんだんとテーパーとか調子のコントロールの仕方ががわかってくるのでしょうか・・・
 。
。 2012年07月09日
5号竿完成!
7月9日(月)
やっとこさ5号竿が完成しました 。・・・といっても期間は半月ほど、3度の週末を要しました。塗りの乾燥を待つのは、とっても長時間に感じるんです。まあ、無事に折れることもなく、ここまで育ってくれたので、よかったです
。・・・といっても期間は半月ほど、3度の週末を要しました。塗りの乾燥を待つのは、とっても長時間に感じるんです。まあ、無事に折れることもなく、ここまで育ってくれたので、よかったです 。
。

穂持ちは、口巻きだけ黒であとは竹肌をそのまま出したかったのですが、3番目の節の芽にクラックらしきものを見つけたので、念のため節を糸で巻いて補強、上の節も同様に糸を巻いて、黒塗りにしました。穂先は基本は黒ですが、継いだ時に少しだけ竹肌の部分が出るように塗っています。こうするとどこから穂先かがはっきりと見え、竿がどこで曲がっているかよくわかるんです。
握り手ですが・・・ 。
。

よく見ると、羽根が入っているんです 。部屋のハタキから、パラッと落ちた羽根を見て、「これだ!」と思い、入れてみましたが、下地の色が濃いので、ほとんど羽根が見えません
。部屋のハタキから、パラッと落ちた羽根を見て、「これだ!」と思い、入れてみましたが、下地の色が濃いので、ほとんど羽根が見えません 。無駄な努力だったかも・・・
。無駄な努力だったかも・・・ 。
。
最初はもっと明るい緑を入れていたんです。

こっちの方がシンプルでよかったという声が聞こえます。だんだん濃くしてしまって・・・ 。「過ぎたるは猶及ばざるが如し」っていうやつでしょうか・・・
。「過ぎたるは猶及ばざるが如し」っていうやつでしょうか・・・ 。
。
さて、竿作りですが、5本目になりました。最初の2本は竿とは呼べるようなものではありませんでしたが、3本目は何となく竿らしくなり、4本目からは見た目だけはへら竿っぽくなってきました。しか~し、難しいです・・・ 、特に火入れと矯め
、特に火入れと矯め 。
。
焦がす直前まで(・・・と本人は思っている)火に入れて、竹をくにゃくにゃにして、矯めていきます(真っ直ぐにしていく)。もちろん、完璧ではありませんが、ほぼ真っ直ぐだなと思って、その後作業をすすめ、塗りをして、ふと竹をみると、元のとおりまではいきませんが、かなり戻しています 。そして再度火入れをして修正、仕上げの時にも竿を繋いでまたまた火入れをして真っ直ぐにします。
。そして再度火入れをして修正、仕上げの時にも竿を繋いでまたまた火入れをして真っ直ぐにします。
そして、釣りに行き、帰って見てみると、また戻しています・・・ 。4号竿も徐々にマシにはなっていますが、釣りをして帰る度に火入れと調整をしないといけません
。4号竿も徐々にマシにはなっていますが、釣りをして帰る度に火入れと調整をしないといけません 。
。
最初の火入れは強くできるのですが、その後は塗装がすでにのっているので、強くできません。特にウレタンが塗ってあると、塗装が浮きます。浮いてしまうと胴塗りもやり直しになります。うるし(合成)の方が、まだ熱には強いように思います。フライの丸竹ロッドの製作などをインターネットで見ていると、もう少し弱火で長時間炙っています。こんどそういう方法も試してみます・・・。
さて、明日は4号竿と5号竿の比較をしてみようと思います。課題は「テーパーと調子」です。ではでは・・・ 。
。
やっとこさ5号竿が完成しました
 。・・・といっても期間は半月ほど、3度の週末を要しました。塗りの乾燥を待つのは、とっても長時間に感じるんです。まあ、無事に折れることもなく、ここまで育ってくれたので、よかったです
。・・・といっても期間は半月ほど、3度の週末を要しました。塗りの乾燥を待つのは、とっても長時間に感じるんです。まあ、無事に折れることもなく、ここまで育ってくれたので、よかったです 。
。
穂持ちは、口巻きだけ黒であとは竹肌をそのまま出したかったのですが、3番目の節の芽にクラックらしきものを見つけたので、念のため節を糸で巻いて補強、上の節も同様に糸を巻いて、黒塗りにしました。穂先は基本は黒ですが、継いだ時に少しだけ竹肌の部分が出るように塗っています。こうするとどこから穂先かがはっきりと見え、竿がどこで曲がっているかよくわかるんです。
握り手ですが・・・
 。
。
よく見ると、羽根が入っているんです
 。部屋のハタキから、パラッと落ちた羽根を見て、「これだ!」と思い、入れてみましたが、下地の色が濃いので、ほとんど羽根が見えません
。部屋のハタキから、パラッと落ちた羽根を見て、「これだ!」と思い、入れてみましたが、下地の色が濃いので、ほとんど羽根が見えません 。無駄な努力だったかも・・・
。無駄な努力だったかも・・・ 。
。最初はもっと明るい緑を入れていたんです。

こっちの方がシンプルでよかったという声が聞こえます。だんだん濃くしてしまって・・・
 。「過ぎたるは猶及ばざるが如し」っていうやつでしょうか・・・
。「過ぎたるは猶及ばざるが如し」っていうやつでしょうか・・・ 。
。さて、竿作りですが、5本目になりました。最初の2本は竿とは呼べるようなものではありませんでしたが、3本目は何となく竿らしくなり、4本目からは見た目だけはへら竿っぽくなってきました。しか~し、難しいです・・・
 、特に火入れと矯め
、特に火入れと矯め 。
。焦がす直前まで(・・・と本人は思っている)火に入れて、竹をくにゃくにゃにして、矯めていきます(真っ直ぐにしていく)。もちろん、完璧ではありませんが、ほぼ真っ直ぐだなと思って、その後作業をすすめ、塗りをして、ふと竹をみると、元のとおりまではいきませんが、かなり戻しています
 。そして再度火入れをして修正、仕上げの時にも竿を繋いでまたまた火入れをして真っ直ぐにします。
。そして再度火入れをして修正、仕上げの時にも竿を繋いでまたまた火入れをして真っ直ぐにします。そして、釣りに行き、帰って見てみると、また戻しています・・・
 。4号竿も徐々にマシにはなっていますが、釣りをして帰る度に火入れと調整をしないといけません
。4号竿も徐々にマシにはなっていますが、釣りをして帰る度に火入れと調整をしないといけません 。
。最初の火入れは強くできるのですが、その後は塗装がすでにのっているので、強くできません。特にウレタンが塗ってあると、塗装が浮きます。浮いてしまうと胴塗りもやり直しになります。うるし(合成)の方が、まだ熱には強いように思います。フライの丸竹ロッドの製作などをインターネットで見ていると、もう少し弱火で長時間炙っています。こんどそういう方法も試してみます・・・。
さて、明日は4号竿と5号竿の比較をしてみようと思います。課題は「テーパーと調子」です。ではでは・・・
 。
。タグ :5号竿
2012年07月03日
4号竿の改造(節巻き)
7月2日(月)
悩んでいました4号竿・・・やっぱり節を補強するために節巻きに改造することにしました 。
。
まず、節周りがかなり薄くなっているので、削るよりも前に凹んだところをエポキシパテで埋めて固めてから、平ヤスリで慎重に削りました。何とかうまくいきました・・・ 。そして、糸を巻くところをテープで区切り、その範囲の竹の表面をさっと小刀で削って行きます。糸がすべらないようにするためです。
。そして、糸を巻くところをテープで区切り、その範囲の竹の表面をさっと小刀で削って行きます。糸がすべらないようにするためです。

そして、糸を巻いていきます。

節巻きは、このように続けて巻いていってよいようです。軽くとめているマスキングテープは、巻いている最中に糸が緩まないようにするためです。糸決め(糸を固めること)のウレタンを塗ったあと、不要な糸は切って行きます。
そして乾燥したら、うるし塗りです。際はマスキングテープを貼って、うるしを塗ってからすぐにはがすと、きれいに仕上がります。ただ、節巻きは細い隙間があるので、マスキングテープを細く切って貼っていくなど、手間がかかります。
マスキングテープは粘着力が弱いため通常は塗装が剥がれたりすることにはならないのですが、今回は数カ所剥がれてしまいました 。
。

下地処理が不足していて、塗装が十分にのっていなかったのかもしれません。通常は塗装する前に竹を400番程度のサンドペーパーで荒らしてから塗っていますが、軽く擦っているだけなので、不十分だったのかもしれません。このせいで、胴塗りの補修もやらなくてはいけなくなりました 。
。
そして最後はコンパウンドで磨いて、節巻きへの改造が完了です 。
。

何とか今週末の釣りには間に合いました・・・ 。改造前のBeforeはこちらです。
。改造前のBeforeはこちらです。

問題は、これでほんとに節周りの補強になったのでしょうか・・・ 。実釣が楽しみです
。実釣が楽しみです 。
。
ところで、5号竿ですが、削りなどは完了。現在色塗りの最中です。竿自体がまだまだ未熟なのに塗装工程(塗装の回数と乾燥時間)に日数がかかり過ぎるので、今後は何とか早くする方法を検討しないといけません。まずは、うるしの代わりにウレタンを多用するのと、握り手をシンプルな糸か籐巻きにすることかと・・・ 。
。
悩んでいました4号竿・・・やっぱり節を補強するために節巻きに改造することにしました
 。
。まず、節周りがかなり薄くなっているので、削るよりも前に凹んだところをエポキシパテで埋めて固めてから、平ヤスリで慎重に削りました。何とかうまくいきました・・・
 。そして、糸を巻くところをテープで区切り、その範囲の竹の表面をさっと小刀で削って行きます。糸がすべらないようにするためです。
。そして、糸を巻くところをテープで区切り、その範囲の竹の表面をさっと小刀で削って行きます。糸がすべらないようにするためです。
そして、糸を巻いていきます。

節巻きは、このように続けて巻いていってよいようです。軽くとめているマスキングテープは、巻いている最中に糸が緩まないようにするためです。糸決め(糸を固めること)のウレタンを塗ったあと、不要な糸は切って行きます。
そして乾燥したら、うるし塗りです。際はマスキングテープを貼って、うるしを塗ってからすぐにはがすと、きれいに仕上がります。ただ、節巻きは細い隙間があるので、マスキングテープを細く切って貼っていくなど、手間がかかります。
マスキングテープは粘着力が弱いため通常は塗装が剥がれたりすることにはならないのですが、今回は数カ所剥がれてしまいました
 。
。
下地処理が不足していて、塗装が十分にのっていなかったのかもしれません。通常は塗装する前に竹を400番程度のサンドペーパーで荒らしてから塗っていますが、軽く擦っているだけなので、不十分だったのかもしれません。このせいで、胴塗りの補修もやらなくてはいけなくなりました
 。
。そして最後はコンパウンドで磨いて、節巻きへの改造が完了です
 。
。
何とか今週末の釣りには間に合いました・・・
 。改造前のBeforeはこちらです。
。改造前のBeforeはこちらです。
問題は、これでほんとに節周りの補強になったのでしょうか・・・
 。実釣が楽しみです
。実釣が楽しみです 。
。ところで、5号竿ですが、削りなどは完了。現在色塗りの最中です。竿自体がまだまだ未熟なのに塗装工程(塗装の回数と乾燥時間)に日数がかかり過ぎるので、今後は何とか早くする方法を検討しないといけません。まずは、うるしの代わりにウレタンを多用するのと、握り手をシンプルな糸か籐巻きにすることかと・・・
 。
。2012年07月01日
エサトレイ
7月1日(日)
先週は軽い食中毒になってしまい、しばらく苦しんでおりましたが、何とか復活 。この季節はバイ菌君も活性が高いそうなので、皆様もご注意ください
。この季節はバイ菌君も活性が高いそうなので、皆様もご注意ください 。
。
さて、病み上がりでまだ無理もしたくないところにお天気は雨 。ということで、週末の釣りはお休み
。ということで、週末の釣りはお休み 。なので、工作をやりまくっております・・・
。なので、工作をやりまくっております・・・ 。
。
まずは15分で完了するもっとも簡単なやつから・・・。準備したものはこちら。

100円ショップで見つけたトレイと机面の下に引く緑色のやつ、そしてホームセンターでステイと20mmM5のネジと蝶ナットを購入。あとはカッター、ものさしと瞬間接着剤、そして写真には写ってないですが、5mmの穴をあけるドリル。
まず、トレイの底面にあわせて、緑色のシートをカット、トレイの端の方に穴をあけて、シートを瞬間接着剤で張り付け、ステイとネジでとめるだけ・・・そしてもう完成 。
。

お膳というのか、うどん皿と呼ぶのかよくわかりませんので、エサトレイと呼んでおきます。ステイを万力と角木の隙間にはさんで締めるだけ。うどんだけでなく、ダンゴでも次のエサを置いておくのに便利ですよね 。
。
仕舞う時はネジを緩めて、ステイをトレイの下に格納。

以上です。
なお、ステイを厚みのあるものにしたのですが、ステンレスの薄いものの方がベターだと思います。またトレイはウレタンらしい塗装がすでにされていますので、塗装の必要もなさそうです 。
。
先週は軽い食中毒になってしまい、しばらく苦しんでおりましたが、何とか復活
 。この季節はバイ菌君も活性が高いそうなので、皆様もご注意ください
。この季節はバイ菌君も活性が高いそうなので、皆様もご注意ください 。
。さて、病み上がりでまだ無理もしたくないところにお天気は雨
 。ということで、週末の釣りはお休み
。ということで、週末の釣りはお休み 。なので、工作をやりまくっております・・・
。なので、工作をやりまくっております・・・ 。
。まずは15分で完了するもっとも簡単なやつから・・・。準備したものはこちら。

100円ショップで見つけたトレイと机面の下に引く緑色のやつ、そしてホームセンターでステイと20mmM5のネジと蝶ナットを購入。あとはカッター、ものさしと瞬間接着剤、そして写真には写ってないですが、5mmの穴をあけるドリル。
まず、トレイの底面にあわせて、緑色のシートをカット、トレイの端の方に穴をあけて、シートを瞬間接着剤で張り付け、ステイとネジでとめるだけ・・・そしてもう完成
 。
。
お膳というのか、うどん皿と呼ぶのかよくわかりませんので、エサトレイと呼んでおきます。ステイを万力と角木の隙間にはさんで締めるだけ。うどんだけでなく、ダンゴでも次のエサを置いておくのに便利ですよね
 。
。仕舞う時はネジを緩めて、ステイをトレイの下に格納。

以上です。
なお、ステイを厚みのあるものにしたのですが、ステンレスの薄いものの方がベターだと思います。またトレイはウレタンらしい塗装がすでにされていますので、塗装の必要もなさそうです
 。
。 タグ :エサトレイ