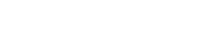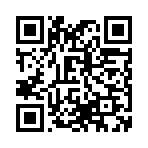2012年05月30日
職人技
5月30日(水)
最近へら釣り用に竹竿作りを始めたばかりですが、YouTubeで関連動画がないかと調べているとへら竿の製作に関するものはあまり出てきませんが、和竿ではいろいろと出てきます。その中でもひとつご紹介したいと思います。
これを見ると製作中に疑問に思っていたところが、一目瞭然でした。百聞は一見にしかず 。それにしてもスゴイ技です。穂先削りなんて、カンナでなくて小刀でそのまま削ってるし・・・
。それにしてもスゴイ技です。穂先削りなんて、カンナでなくて小刀でそのまま削ってるし・・・ 。
。
【下町に息づく伝統の技 江戸和竿1/3】
続きはこちらから・・・
【下町に息づく伝統の技 江戸和竿2/3 】
【下町に息づく伝統の技 江戸和竿3/3】
竹の火入れだとか、処理を調べていると、和竿や丸竹フライロッドなどの釣り関連以外に竹笛や弓矢の製作に関するものが出てきます。昔は下級武士が弓矢を作っていたそうですが、道具や材料が同じなので、竹笛や釣り竿も同時に作っていたのではないでしょうか・・・。こちらの動画は弓矢の製作ですが、これを見ると、製作工程や技が釣り竿作りと共通であることがわかります。なかなか興味深いです。
【弓矢1/3】
続きはこちらから・・・
【弓矢2/3】
【弓矢3/3】
和竿も弓矢作りも奥深いものですが、技術の継承者は多くはないでしょうから、どうなっていくのでしょうか・・・。こういった伝統工芸がなくならいように願っています。
最近へら釣り用に竹竿作りを始めたばかりですが、YouTubeで関連動画がないかと調べているとへら竿の製作に関するものはあまり出てきませんが、和竿ではいろいろと出てきます。その中でもひとつご紹介したいと思います。
これを見ると製作中に疑問に思っていたところが、一目瞭然でした。百聞は一見にしかず
 。それにしてもスゴイ技です。穂先削りなんて、カンナでなくて小刀でそのまま削ってるし・・・
。それにしてもスゴイ技です。穂先削りなんて、カンナでなくて小刀でそのまま削ってるし・・・ 。
。【下町に息づく伝統の技 江戸和竿1/3】
続きはこちらから・・・
【下町に息づく伝統の技 江戸和竿2/3 】
【下町に息づく伝統の技 江戸和竿3/3】
竹の火入れだとか、処理を調べていると、和竿や丸竹フライロッドなどの釣り関連以外に竹笛や弓矢の製作に関するものが出てきます。昔は下級武士が弓矢を作っていたそうですが、道具や材料が同じなので、竹笛や釣り竿も同時に作っていたのではないでしょうか・・・。こちらの動画は弓矢の製作ですが、これを見ると、製作工程や技が釣り竿作りと共通であることがわかります。なかなか興味深いです。
【弓矢1/3】
続きはこちらから・・・
【弓矢2/3】
【弓矢3/3】
和竿も弓矢作りも奥深いものですが、技術の継承者は多くはないでしょうから、どうなっていくのでしょうか・・・。こういった伝統工芸がなくならいように願っています。
2012年05月23日
削り穂改良
5月22日(火)
先日真ん中でパキッと逝った穂先ですが、まずは塗装をはがしてみました。

やはりここかと・・・ 。ここは節のすぐ下で、電動ドリルにはさんで紙ヤスリで削った時に削り過ぎたところなんです。節の部分を削ろうと紙ヤスリをあてていると節は硬いので、その周辺のやわらかいところが、どんどん削れてしまっていました・・・
。ここは節のすぐ下で、電動ドリルにはさんで紙ヤスリで削った時に削り過ぎたところなんです。節の部分を削ろうと紙ヤスリをあてていると節は硬いので、その周辺のやわらかいところが、どんどん削れてしまっていました・・・ 。その結果、節より細く弱そうなので気になっていました。
。その結果、節より細く弱そうなので気になっていました。
おまけにインターネットで調べていると、通常は真竹の最良の部分でない限り、折れやすい節前後は糸を巻いて補強するのだということもわかりました。更に、わたしの使っている孟宗竹は真竹と似ているが、ポキポキとよく折れるため、竹細工などには向かない・・・ ・・・そうです。
・・・そうです。
・・・といっても真竹は今は持ってないので、手持ちの孟宗竹で再度挑戦。前回はドリルに咥えさせて60番の紙ヤスリを使った時に削りすぎたので、今回は400番を使った仕上げだけにしました。仕上げ直前まで削り金具と平ヤスリで丁寧に削り込みました。下の写真の削り金具ですが、今回は刃をダイヤモンドヤスリでさらに磨くと、数段削りやすくなりました。

節前後は糸を巻いて補強。火入れは三度ほど。元側の太い部分はいつものガスコンロで、そして穂先の細い部分はヘアアイロンでじっくりと(温度管理ができる)慎重にやりました。

塗りはまずウレタンで糸決め、再度ウレタンを塗り、その上から黒のうるしを4度塗り、さらに仕上げにウレタンを塗って完成としました
 。
。
「あっ、・・・ 」
」

「・・・・・・・ 」
」
そう、一旦完成はしたんです。そして、金属磨き粉のピカットで磨いて、テカりを落とそうとしたんです。古いTシャツにピカットを少量とり、下から上へゴシゴシと・・・ 。Tシャツの袖が穂先にひっかかっているのも知らず、ゴシゴシと・・・
。Tシャツの袖が穂先にひっかかっているのも知らず、ゴシゴシと・・・
「ポキッ 」
」
一度も使わずに折れました・・・ 。心も折れそうになりましたが、熱い怒り
。心も折れそうになりましたが、熱い怒り のエネルギーが燃え盛る内に次の穂先の仕込みに突入し、一気にここまで仕上げました。作業が慣れてきて早くなったので、ついでに予備も途中まで削りました。ただ前回より、さすがに手抜きです・・・
のエネルギーが燃え盛る内に次の穂先の仕込みに突入し、一気にここまで仕上げました。作業が慣れてきて早くなったので、ついでに予備も途中まで削りました。ただ前回より、さすがに手抜きです・・・ 。
。

穂先が硬いと折れやすい気がしたので、今回は今までで一番細くしてみました。また、折れるのか・・・これでダメなら次はさすがに真竹だな・・・ 。
。
先日真ん中でパキッと逝った穂先ですが、まずは塗装をはがしてみました。

やはりここかと・・・
 。ここは節のすぐ下で、電動ドリルにはさんで紙ヤスリで削った時に削り過ぎたところなんです。節の部分を削ろうと紙ヤスリをあてていると節は硬いので、その周辺のやわらかいところが、どんどん削れてしまっていました・・・
。ここは節のすぐ下で、電動ドリルにはさんで紙ヤスリで削った時に削り過ぎたところなんです。節の部分を削ろうと紙ヤスリをあてていると節は硬いので、その周辺のやわらかいところが、どんどん削れてしまっていました・・・ 。その結果、節より細く弱そうなので気になっていました。
。その結果、節より細く弱そうなので気になっていました。おまけにインターネットで調べていると、通常は真竹の最良の部分でない限り、折れやすい節前後は糸を巻いて補強するのだということもわかりました。更に、わたしの使っている孟宗竹は真竹と似ているが、ポキポキとよく折れるため、竹細工などには向かない・・・
 ・・・そうです。
・・・そうです。・・・といっても真竹は今は持ってないので、手持ちの孟宗竹で再度挑戦。前回はドリルに咥えさせて60番の紙ヤスリを使った時に削りすぎたので、今回は400番を使った仕上げだけにしました。仕上げ直前まで削り金具と平ヤスリで丁寧に削り込みました。下の写真の削り金具ですが、今回は刃をダイヤモンドヤスリでさらに磨くと、数段削りやすくなりました。

節前後は糸を巻いて補強。火入れは三度ほど。元側の太い部分はいつものガスコンロで、そして穂先の細い部分はヘアアイロンでじっくりと(温度管理ができる)慎重にやりました。

塗りはまずウレタンで糸決め、再度ウレタンを塗り、その上から黒のうるしを4度塗り、さらに仕上げにウレタンを塗って完成としました

 。
。「あっ、・・・
 」
」
「・・・・・・・
 」
」そう、一旦完成はしたんです。そして、金属磨き粉のピカットで磨いて、テカりを落とそうとしたんです。古いTシャツにピカットを少量とり、下から上へゴシゴシと・・・
 。Tシャツの袖が穂先にひっかかっているのも知らず、ゴシゴシと・・・
。Tシャツの袖が穂先にひっかかっているのも知らず、ゴシゴシと・・・「ポキッ
 」
」一度も使わずに折れました・・・
 。心も折れそうになりましたが、熱い怒り
。心も折れそうになりましたが、熱い怒り のエネルギーが燃え盛る内に次の穂先の仕込みに突入し、一気にここまで仕上げました。作業が慣れてきて早くなったので、ついでに予備も途中まで削りました。ただ前回より、さすがに手抜きです・・・
のエネルギーが燃え盛る内に次の穂先の仕込みに突入し、一気にここまで仕上げました。作業が慣れてきて早くなったので、ついでに予備も途中まで削りました。ただ前回より、さすがに手抜きです・・・ 。
。
穂先が硬いと折れやすい気がしたので、今回は今までで一番細くしてみました。また、折れるのか・・・これでダメなら次はさすがに真竹だな・・・
 。
。 タグ :穂先
2012年05月17日
造り節(お試し編)
5月17日(木)
竿掛けや玉網の柄など、小節の竹が好まれますが、なかなか入手することはできません。仮に竹材店で購入できたとしても希少価値もあり、かなりお高いです 。
。
先日購入した本です。合成竿、ウキ、万力、玉枠、竿掛けなど、へら道具の作り方が書いてあります。これ一冊ですべて作れるということはないかもしれませんが、自作を始めた人にとってはヒントがたくさん書いてあり、すごく役に立っています。

この本の中で、造り節という手法が紹介されています。竹の節のないところに人工的に節を作るんです。難しいかなと思いましたが、ちょっとお試しに作ってみると・・・

想像以上にうまくできてしまいました 。
。
竹の芽の部分も削ってつくりました。節部分の盛り上げたところをきれいに見せるために、今回は合成うるしの「透」色を塗って下が透けないようにしました。
本番で使うにはまだ改善余地がありそうです 。
。
竿掛けや玉網の柄など、小節の竹が好まれますが、なかなか入手することはできません。仮に竹材店で購入できたとしても希少価値もあり、かなりお高いです
 。
。先日購入した本です。合成竿、ウキ、万力、玉枠、竿掛けなど、へら道具の作り方が書いてあります。これ一冊ですべて作れるということはないかもしれませんが、自作を始めた人にとってはヒントがたくさん書いてあり、すごく役に立っています。

この本の中で、造り節という手法が紹介されています。竹の節のないところに人工的に節を作るんです。難しいかなと思いましたが、ちょっとお試しに作ってみると・・・


想像以上にうまくできてしまいました
 。
。竹の芽の部分も削ってつくりました。節部分の盛り上げたところをきれいに見せるために、今回は合成うるしの「透」色を塗って下が透けないようにしました。
本番で使うにはまだ改善余地がありそうです
 。
。 タグ :造り節
2012年05月15日
ポンプ絞り台の製作
5月13日(日)
先日工作予定を書いた中で、玉網の枠は終了しましたので、次はポンプ絞り台の製作です。
土台と柱の材料は先日玉網の枠に使った割れやすい栂(ツガ)です 。ハンドル部は家に余っていたヒノキの端切れです。土台部分は幅60mm・厚さ24mm・長さ150mmで、底面が30×30mmの角柱を差し込むための穴と、ポンプを置く穴(写真では浅いですが、実際には深い穴、直径40mm)をあけました。写真左は前回の玉枠製作中のものです。
。ハンドル部は家に余っていたヒノキの端切れです。土台部分は幅60mm・厚さ24mm・長さ150mmで、底面が30×30mmの角柱を差し込むための穴と、ポンプを置く穴(写真では浅いですが、実際には深い穴、直径40mm)をあけました。写真左は前回の玉枠製作中のものです。

そして、穴に角柱を差し込んでみると・・・ ・・・角柱の底面が正方形ではなくひし形に歪んでいるではありませんか・・・
・・・角柱の底面が正方形ではなくひし形に歪んでいるではありませんか・・・ 。購入の際にきちんと調べるべきでした。仕方ないので、角柱を削り入るようにして、おがくずとエポキシボンドで大きな隙間を埋めました
。購入の際にきちんと調べるべきでした。仕方ないので、角柱を削り入るようにして、おがくずとエポキシボンドで大きな隙間を埋めました 。
。

可動部分ですが、木に直接ボルトを刺すと木が削れて劣化が早いので、角柱とハンドル部分には5mmの穴をあけて、アルミパイプ(外径5mm、内径4mm)を通しました。芯材は4mmのステンレスボルトと蝶ネジを使用します。仮組みしてみました 。
。

ドリルを手に持って穴をあけているので、穴をまっすぐにあけるのが大変でしたが、少し芯材のボルトの中央部分を削るとスムーズに動くようになりました 。
。
そして次は色塗りです。下の写真はすでに3度塗りを終えたところですが、ハンドル部分と土台部分の色がかなり違います。同じ塗料を塗っているので、おそらく素材の色が少し違うせいだと思います。最終的には5度塗り+ウレタン塗装しましたが、少し色を変えてあわせていきました。

話は少し脱線しますが、わたしが塗りをする時には写真の①~⑥のものを準備しています。これがあるとかなり作業がはかどります。
①風呂のフタの上で塗りをしていますので、新聞紙や広告を広げます。
②絵皿を掃除する際、また万一のはみ出しにも即対応できるようにキッチンペーパーを準備。
③使用後のキッチンペーパーは溶剤の臭いとうるしがついているので、即ビニール袋で処理。
④絵皿で混ぜます。これがあれば後の筆の掃除も楽です。
⑤スポイトを使用するようになってから、無駄もなくなり、濃さの調整も簡単に!
⑥どこを持って塗るか、またどのように乾かすかを事前に決めておきます。そのために必要な持ち手や洗濯バサミ、かける糸なども準備万端にしておく必要があります。これ最重要 。
。
塗りが終わった後は、絵皿や筆を溶剤できれいにして、キッチンペーパーでふき取って終了です。そして出来上がったのがこちら。底面には滑り止めのゴムを貼りました。

ポンプの差し込み穴の底には水抜き穴もあけました。

一番下まで降ろした時の感じです。

対して、こちらは一番上まであげた時。

ヤスリがけで手を抜いてしまったので、少々デコボコがあり、塗装をテカらせると波打って美しくないので、金属磨きのピッカトでつや消しにしました。とりあえず、これで完成です 。
。
今回角柱を使いましたが、市販品と同様に円柱を使った方が簡単だと思います。角柱だとぴったりの穴を土台にあけるのに苦労しますが、円柱だとそのサイズのドリルを買ってしまえば簡単です。おまけにハンドル取り付けの際に側面の抵抗が少ないので、若干穴が曲がっていても問題なく可動すると思います。まあ、次に作ることは当分なさそうですが・・・ 。
。
次の工作は折れた穂先の検証と新たな穂先作りからです・・・ 。
。
先日工作予定を書いた中で、玉網の枠は終了しましたので、次はポンプ絞り台の製作です。
土台と柱の材料は先日玉網の枠に使った割れやすい栂(ツガ)です
 。ハンドル部は家に余っていたヒノキの端切れです。土台部分は幅60mm・厚さ24mm・長さ150mmで、底面が30×30mmの角柱を差し込むための穴と、ポンプを置く穴(写真では浅いですが、実際には深い穴、直径40mm)をあけました。写真左は前回の玉枠製作中のものです。
。ハンドル部は家に余っていたヒノキの端切れです。土台部分は幅60mm・厚さ24mm・長さ150mmで、底面が30×30mmの角柱を差し込むための穴と、ポンプを置く穴(写真では浅いですが、実際には深い穴、直径40mm)をあけました。写真左は前回の玉枠製作中のものです。
そして、穴に角柱を差し込んでみると・・・
 ・・・角柱の底面が正方形ではなくひし形に歪んでいるではありませんか・・・
・・・角柱の底面が正方形ではなくひし形に歪んでいるではありませんか・・・ 。購入の際にきちんと調べるべきでした。仕方ないので、角柱を削り入るようにして、おがくずとエポキシボンドで大きな隙間を埋めました
。購入の際にきちんと調べるべきでした。仕方ないので、角柱を削り入るようにして、おがくずとエポキシボンドで大きな隙間を埋めました 。
。
可動部分ですが、木に直接ボルトを刺すと木が削れて劣化が早いので、角柱とハンドル部分には5mmの穴をあけて、アルミパイプ(外径5mm、内径4mm)を通しました。芯材は4mmのステンレスボルトと蝶ネジを使用します。仮組みしてみました
 。
。
ドリルを手に持って穴をあけているので、穴をまっすぐにあけるのが大変でしたが、少し芯材のボルトの中央部分を削るとスムーズに動くようになりました
 。
。そして次は色塗りです。下の写真はすでに3度塗りを終えたところですが、ハンドル部分と土台部分の色がかなり違います。同じ塗料を塗っているので、おそらく素材の色が少し違うせいだと思います。最終的には5度塗り+ウレタン塗装しましたが、少し色を変えてあわせていきました。

話は少し脱線しますが、わたしが塗りをする時には写真の①~⑥のものを準備しています。これがあるとかなり作業がはかどります。
①風呂のフタの上で塗りをしていますので、新聞紙や広告を広げます。
②絵皿を掃除する際、また万一のはみ出しにも即対応できるようにキッチンペーパーを準備。
③使用後のキッチンペーパーは溶剤の臭いとうるしがついているので、即ビニール袋で処理。
④絵皿で混ぜます。これがあれば後の筆の掃除も楽です。
⑤スポイトを使用するようになってから、無駄もなくなり、濃さの調整も簡単に!
⑥どこを持って塗るか、またどのように乾かすかを事前に決めておきます。そのために必要な持ち手や洗濯バサミ、かける糸なども準備万端にしておく必要があります。これ最重要
 。
。塗りが終わった後は、絵皿や筆を溶剤できれいにして、キッチンペーパーでふき取って終了です。そして出来上がったのがこちら。底面には滑り止めのゴムを貼りました。

ポンプの差し込み穴の底には水抜き穴もあけました。

一番下まで降ろした時の感じです。

対して、こちらは一番上まであげた時。

ヤスリがけで手を抜いてしまったので、少々デコボコがあり、塗装をテカらせると波打って美しくないので、金属磨きのピッカトでつや消しにしました。とりあえず、これで完成です
 。
。今回角柱を使いましたが、市販品と同様に円柱を使った方が簡単だと思います。角柱だとぴったりの穴を土台にあけるのに苦労しますが、円柱だとそのサイズのドリルを買ってしまえば簡単です。おまけにハンドル取り付けの際に側面の抵抗が少ないので、若干穴が曲がっていても問題なく可動すると思います。まあ、次に作ることは当分なさそうですが・・・
 。
。次の工作は折れた穂先の検証と新たな穂先作りからです・・・
 。
。タグ :ポンプ絞り台
2012年05月08日
へら玉枠の製作
5月7日(火)
以前に工作予定を書いた中で、玉網の枠と絞り台の作業をGW中に進めて、まず玉網の枠が完成しました。絞り台はもう少しですので、今回は玉網の枠の製作過程を少々記録しておきます(絞り台はこちら)。
まず、材料ですが、工作予定に書いたように100円で購入した玉枠の輪の部分と木から削って作る込みの部分を合体させることにしました。いわゆる合成木枠というやつです。
込みの部分の木は、ホームセンターで見つけた栂(ツガ)。特にこだわったわけではなく、単に思っていたサイズの木材がこれしかなかったからなんですが、作業を進めていくとどうやら割れやすい材質のようで、カンナをかけてひっかかると簡単に割れてしまいました。それゆえ、結構苦労することに・・・・ 。とにかく、この木材をだいたいの形にのこぎりで切りました(右は絞り台用です)。
。とにかく、この木材をだいたいの形にのこぎりで切りました(右は絞り台用です)。

次にカンナ、平ヤスリ、ナイフを使って形を整えていきます。

そして、穴をあけて輪の部品を差し込み合体 。接着はエポキシボンドを使用しました。単純に差し込んだだけですが、隙間をすべてエポキシで埋めたこともあり、結構な強度があるような気がします
。接着はエポキシボンドを使用しました。単純に差し込んだだけですが、隙間をすべてエポキシで埋めたこともあり、結構な強度があるような気がします 。
。

込みの部分をアップにした写真ですが、ここも割れました。瞬間接着剤で補修しています。これ以外にも細かい部分がパキパキと・・・ 。そのために予定より横幅が小さくなりました。輪の部分との段差を小さくして継ぎ目をスムーズにするつもりだったのですが、これだけパキパキと割れると間違いなく更に割れそうだったので、強度重視で厚みを残しました
。そのために予定より横幅が小さくなりました。輪の部分との段差を小さくして継ぎ目をスムーズにするつもりだったのですが、これだけパキパキと割れると間違いなく更に割れそうだったので、強度重視で厚みを残しました 。
。

そして、塗りですが、まずウレタンで下塗りしてから、うるしの紅溜(ベニダメ)を3度、そして仕上げに再度ウレタンを塗り、竿同様に金属磨きのピカットで表面のざらつきを取り、コンパウンドで磨いて仕上げました 。
。

そして、網を取りつけて完了です。この玉網枠の強度もわからないので、網はとりあえず安価なもの(確か600円程度だったかと・・・)を使っています。取り付け糸は、イカリ印竿巻糸の2号(中)が家にあったので、それを使用。

輪部分との段差を目立たなくするために境目に籐を巻こうかと思っていましたが、強度には関係ないので、まずはシンプルにこのままで使ってみようと思います。ただ、この枠に合う玉網の柄を作らないとデビューできないのですが・・・ 。
。
以前に工作予定を書いた中で、玉網の枠と絞り台の作業をGW中に進めて、まず玉網の枠が完成しました。絞り台はもう少しですので、今回は玉網の枠の製作過程を少々記録しておきます(絞り台はこちら)。
まず、材料ですが、工作予定に書いたように100円で購入した玉枠の輪の部分と木から削って作る込みの部分を合体させることにしました。いわゆる合成木枠というやつです。
込みの部分の木は、ホームセンターで見つけた栂(ツガ)。特にこだわったわけではなく、単に思っていたサイズの木材がこれしかなかったからなんですが、作業を進めていくとどうやら割れやすい材質のようで、カンナをかけてひっかかると簡単に割れてしまいました。それゆえ、結構苦労することに・・・・
 。とにかく、この木材をだいたいの形にのこぎりで切りました(右は絞り台用です)。
。とにかく、この木材をだいたいの形にのこぎりで切りました(右は絞り台用です)。
次にカンナ、平ヤスリ、ナイフを使って形を整えていきます。

そして、穴をあけて輪の部品を差し込み合体
 。接着はエポキシボンドを使用しました。単純に差し込んだだけですが、隙間をすべてエポキシで埋めたこともあり、結構な強度があるような気がします
。接着はエポキシボンドを使用しました。単純に差し込んだだけですが、隙間をすべてエポキシで埋めたこともあり、結構な強度があるような気がします 。
。
込みの部分をアップにした写真ですが、ここも割れました。瞬間接着剤で補修しています。これ以外にも細かい部分がパキパキと・・・
 。そのために予定より横幅が小さくなりました。輪の部分との段差を小さくして継ぎ目をスムーズにするつもりだったのですが、これだけパキパキと割れると間違いなく更に割れそうだったので、強度重視で厚みを残しました
。そのために予定より横幅が小さくなりました。輪の部分との段差を小さくして継ぎ目をスムーズにするつもりだったのですが、これだけパキパキと割れると間違いなく更に割れそうだったので、強度重視で厚みを残しました 。
。
そして、塗りですが、まずウレタンで下塗りしてから、うるしの紅溜(ベニダメ)を3度、そして仕上げに再度ウレタンを塗り、竿同様に金属磨きのピカットで表面のざらつきを取り、コンパウンドで磨いて仕上げました
 。
。
そして、網を取りつけて完了です。この玉網枠の強度もわからないので、網はとりあえず安価なもの(確か600円程度だったかと・・・)を使っています。取り付け糸は、イカリ印竿巻糸の2号(中)が家にあったので、それを使用。

輪部分との段差を目立たなくするために境目に籐を巻こうかと思っていましたが、強度には関係ないので、まずはシンプルにこのままで使ってみようと思います。ただ、この枠に合う玉網の柄を作らないとデビューできないのですが・・・
 。
。 タグ :玉枠
2012年05月02日
工作予定
5月2日(水)
最近釣り具の自作にはまっておりますが、作りたいものの待ちの列がずらーっと・・・ 。その一部をご紹介
。その一部をご紹介 。
。
【絞り台】
まずはポンプの絞り台。今はとりあえずのものを作って使っているのですが、もう少しかっこいいやつを作りたいと思っています。適当に木を切って作ろうかと思いましたが、削る工程なども多く、失敗すると時間の無駄になってしまうので、少しだけ下準備を・・・ 。
。

手元にある木材の大きさにあわせて牛乳パックを切って、基本構造の確認です。面倒だったので、かなり適当ですが、イメージはわきました。高さを調整できるようにしようかと思っていましたが、1日の釣りで大量にインスタントウドンを作ることもないので、必要なさそうです。
【平キリ】
以前に作った平キリですが、3号竿を製作/補修するのに必要なサイズのみ作ったので、虫食い状態です。2mmから12mm程度まで0.2mm単位で揃えようと準備中です。8mmまでの不足分はすでに熱して叩いて平らにしています 。
。

太い物は、熱して叩くのも大変なので、後回しになっています。とりあえず、写真の平らにしたものを削って、焼き入れをして、刃を付けることからやろうと思っています。
【玉網の枠】
現在使用しているものは、インターネットの写真と店で実物を見て、適当に考えて作ったものですが、このまえ誤って踏んでしまい、込みの上部に割れが入ってしまいました 。まずはそれを修理してます。
。まずはそれを修理してます。

割れの入った部分に糸を巻いて補強。まあ、そもそも糸を巻いていなかったのが失敗なのですが、製作当時の1月は竹で物を作ることを始めたばかりでしたので、いまいち扱いがわかっていませんでした。あとは網を取り付けている糸を結びなおして、終了です。
最近こどもとも一緒にヘラに行っていることもあり、もうひとつ予備枠を作っておこうと準備中です。

こちらは、上○屋で見つけた100円の玉網の枠(割れが入っていたり、かなりショボい作りのものです)を材料にして、製作予定です。枠が大きすぎるので、柄の部分を切り取り、直径を30cmにして、新たに柄の部分を別の木で作りなおして完成させる予定です。
【その他】
これ以外にも、お膳(すでに万力部分の部品は入手)とか、玉網の柄の作りなおしとか、針はずしとか・・・・いっぱいあり過ぎてどうしていいかわかりません・・・ 。
。
最近釣り具の自作にはまっておりますが、作りたいものの待ちの列がずらーっと・・・
 。その一部をご紹介
。その一部をご紹介 。
。【絞り台】
まずはポンプの絞り台。今はとりあえずのものを作って使っているのですが、もう少しかっこいいやつを作りたいと思っています。適当に木を切って作ろうかと思いましたが、削る工程なども多く、失敗すると時間の無駄になってしまうので、少しだけ下準備を・・・
 。
。
手元にある木材の大きさにあわせて牛乳パックを切って、基本構造の確認です。面倒だったので、かなり適当ですが、イメージはわきました。高さを調整できるようにしようかと思っていましたが、1日の釣りで大量にインスタントウドンを作ることもないので、必要なさそうです。
【平キリ】
以前に作った平キリですが、3号竿を製作/補修するのに必要なサイズのみ作ったので、虫食い状態です。2mmから12mm程度まで0.2mm単位で揃えようと準備中です。8mmまでの不足分はすでに熱して叩いて平らにしています
 。
。
太い物は、熱して叩くのも大変なので、後回しになっています。とりあえず、写真の平らにしたものを削って、焼き入れをして、刃を付けることからやろうと思っています。
【玉網の枠】
現在使用しているものは、インターネットの写真と店で実物を見て、適当に考えて作ったものですが、このまえ誤って踏んでしまい、込みの上部に割れが入ってしまいました
 。まずはそれを修理してます。
。まずはそれを修理してます。
割れの入った部分に糸を巻いて補強。まあ、そもそも糸を巻いていなかったのが失敗なのですが、製作当時の1月は竹で物を作ることを始めたばかりでしたので、いまいち扱いがわかっていませんでした。あとは網を取り付けている糸を結びなおして、終了です。
最近こどもとも一緒にヘラに行っていることもあり、もうひとつ予備枠を作っておこうと準備中です。

こちらは、上○屋で見つけた100円の玉網の枠(割れが入っていたり、かなりショボい作りのものです)を材料にして、製作予定です。枠が大きすぎるので、柄の部分を切り取り、直径を30cmにして、新たに柄の部分を別の木で作りなおして完成させる予定です。
【その他】
これ以外にも、お膳(すでに万力部分の部品は入手)とか、玉網の柄の作りなおしとか、針はずしとか・・・・いっぱいあり過ぎてどうしていいかわかりません・・・
 。
。