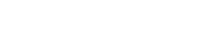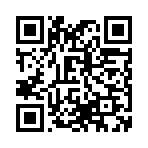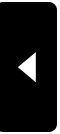2012年05月08日
へら玉枠の製作
5月7日(火)
以前に工作予定を書いた中で、玉網の枠と絞り台の作業をGW中に進めて、まず玉網の枠が完成しました。絞り台はもう少しですので、今回は玉網の枠の製作過程を少々記録しておきます(絞り台はこちら)。
まず、材料ですが、工作予定に書いたように100円で購入した玉枠の輪の部分と木から削って作る込みの部分を合体させることにしました。いわゆる合成木枠というやつです。
込みの部分の木は、ホームセンターで見つけた栂(ツガ)。特にこだわったわけではなく、単に思っていたサイズの木材がこれしかなかったからなんですが、作業を進めていくとどうやら割れやすい材質のようで、カンナをかけてひっかかると簡単に割れてしまいました。それゆえ、結構苦労することに・・・・ 。とにかく、この木材をだいたいの形にのこぎりで切りました(右は絞り台用です)。
。とにかく、この木材をだいたいの形にのこぎりで切りました(右は絞り台用です)。

次にカンナ、平ヤスリ、ナイフを使って形を整えていきます。

そして、穴をあけて輪の部品を差し込み合体 。接着はエポキシボンドを使用しました。単純に差し込んだだけですが、隙間をすべてエポキシで埋めたこともあり、結構な強度があるような気がします
。接着はエポキシボンドを使用しました。単純に差し込んだだけですが、隙間をすべてエポキシで埋めたこともあり、結構な強度があるような気がします 。
。

込みの部分をアップにした写真ですが、ここも割れました。瞬間接着剤で補修しています。これ以外にも細かい部分がパキパキと・・・ 。そのために予定より横幅が小さくなりました。輪の部分との段差を小さくして継ぎ目をスムーズにするつもりだったのですが、これだけパキパキと割れると間違いなく更に割れそうだったので、強度重視で厚みを残しました
。そのために予定より横幅が小さくなりました。輪の部分との段差を小さくして継ぎ目をスムーズにするつもりだったのですが、これだけパキパキと割れると間違いなく更に割れそうだったので、強度重視で厚みを残しました 。
。

そして、塗りですが、まずウレタンで下塗りしてから、うるしの紅溜(ベニダメ)を3度、そして仕上げに再度ウレタンを塗り、竿同様に金属磨きのピカットで表面のざらつきを取り、コンパウンドで磨いて仕上げました 。
。

そして、網を取りつけて完了です。この玉網枠の強度もわからないので、網はとりあえず安価なもの(確か600円程度だったかと・・・)を使っています。取り付け糸は、イカリ印竿巻糸の2号(中)が家にあったので、それを使用。

輪部分との段差を目立たなくするために境目に籐を巻こうかと思っていましたが、強度には関係ないので、まずはシンプルにこのままで使ってみようと思います。ただ、この枠に合う玉網の柄を作らないとデビューできないのですが・・・ 。
。
以前に工作予定を書いた中で、玉網の枠と絞り台の作業をGW中に進めて、まず玉網の枠が完成しました。絞り台はもう少しですので、今回は玉網の枠の製作過程を少々記録しておきます(絞り台はこちら)。
まず、材料ですが、工作予定に書いたように100円で購入した玉枠の輪の部分と木から削って作る込みの部分を合体させることにしました。いわゆる合成木枠というやつです。
込みの部分の木は、ホームセンターで見つけた栂(ツガ)。特にこだわったわけではなく、単に思っていたサイズの木材がこれしかなかったからなんですが、作業を進めていくとどうやら割れやすい材質のようで、カンナをかけてひっかかると簡単に割れてしまいました。それゆえ、結構苦労することに・・・・
 。とにかく、この木材をだいたいの形にのこぎりで切りました(右は絞り台用です)。
。とにかく、この木材をだいたいの形にのこぎりで切りました(右は絞り台用です)。
次にカンナ、平ヤスリ、ナイフを使って形を整えていきます。

そして、穴をあけて輪の部品を差し込み合体
 。接着はエポキシボンドを使用しました。単純に差し込んだだけですが、隙間をすべてエポキシで埋めたこともあり、結構な強度があるような気がします
。接着はエポキシボンドを使用しました。単純に差し込んだだけですが、隙間をすべてエポキシで埋めたこともあり、結構な強度があるような気がします 。
。
込みの部分をアップにした写真ですが、ここも割れました。瞬間接着剤で補修しています。これ以外にも細かい部分がパキパキと・・・
 。そのために予定より横幅が小さくなりました。輪の部分との段差を小さくして継ぎ目をスムーズにするつもりだったのですが、これだけパキパキと割れると間違いなく更に割れそうだったので、強度重視で厚みを残しました
。そのために予定より横幅が小さくなりました。輪の部分との段差を小さくして継ぎ目をスムーズにするつもりだったのですが、これだけパキパキと割れると間違いなく更に割れそうだったので、強度重視で厚みを残しました 。
。
そして、塗りですが、まずウレタンで下塗りしてから、うるしの紅溜(ベニダメ)を3度、そして仕上げに再度ウレタンを塗り、竿同様に金属磨きのピカットで表面のざらつきを取り、コンパウンドで磨いて仕上げました
 。
。
そして、網を取りつけて完了です。この玉網枠の強度もわからないので、網はとりあえず安価なもの(確か600円程度だったかと・・・)を使っています。取り付け糸は、イカリ印竿巻糸の2号(中)が家にあったので、それを使用。

輪部分との段差を目立たなくするために境目に籐を巻こうかと思っていましたが、強度には関係ないので、まずはシンプルにこのままで使ってみようと思います。ただ、この枠に合う玉網の柄を作らないとデビューできないのですが・・・
 。
。 タグ :玉枠
2012年05月02日
工作予定
5月2日(水)
最近釣り具の自作にはまっておりますが、作りたいものの待ちの列がずらーっと・・・ 。その一部をご紹介
。その一部をご紹介 。
。
【絞り台】
まずはポンプの絞り台。今はとりあえずのものを作って使っているのですが、もう少しかっこいいやつを作りたいと思っています。適当に木を切って作ろうかと思いましたが、削る工程なども多く、失敗すると時間の無駄になってしまうので、少しだけ下準備を・・・ 。
。

手元にある木材の大きさにあわせて牛乳パックを切って、基本構造の確認です。面倒だったので、かなり適当ですが、イメージはわきました。高さを調整できるようにしようかと思っていましたが、1日の釣りで大量にインスタントウドンを作ることもないので、必要なさそうです。
【平キリ】
以前に作った平キリですが、3号竿を製作/補修するのに必要なサイズのみ作ったので、虫食い状態です。2mmから12mm程度まで0.2mm単位で揃えようと準備中です。8mmまでの不足分はすでに熱して叩いて平らにしています 。
。

太い物は、熱して叩くのも大変なので、後回しになっています。とりあえず、写真の平らにしたものを削って、焼き入れをして、刃を付けることからやろうと思っています。
【玉網の枠】
現在使用しているものは、インターネットの写真と店で実物を見て、適当に考えて作ったものですが、このまえ誤って踏んでしまい、込みの上部に割れが入ってしまいました 。まずはそれを修理してます。
。まずはそれを修理してます。

割れの入った部分に糸を巻いて補強。まあ、そもそも糸を巻いていなかったのが失敗なのですが、製作当時の1月は竹で物を作ることを始めたばかりでしたので、いまいち扱いがわかっていませんでした。あとは網を取り付けている糸を結びなおして、終了です。
最近こどもとも一緒にヘラに行っていることもあり、もうひとつ予備枠を作っておこうと準備中です。

こちらは、上○屋で見つけた100円の玉網の枠(割れが入っていたり、かなりショボい作りのものです)を材料にして、製作予定です。枠が大きすぎるので、柄の部分を切り取り、直径を30cmにして、新たに柄の部分を別の木で作りなおして完成させる予定です。
【その他】
これ以外にも、お膳(すでに万力部分の部品は入手)とか、玉網の柄の作りなおしとか、針はずしとか・・・・いっぱいあり過ぎてどうしていいかわかりません・・・ 。
。
最近釣り具の自作にはまっておりますが、作りたいものの待ちの列がずらーっと・・・
 。その一部をご紹介
。その一部をご紹介 。
。【絞り台】
まずはポンプの絞り台。今はとりあえずのものを作って使っているのですが、もう少しかっこいいやつを作りたいと思っています。適当に木を切って作ろうかと思いましたが、削る工程なども多く、失敗すると時間の無駄になってしまうので、少しだけ下準備を・・・
 。
。
手元にある木材の大きさにあわせて牛乳パックを切って、基本構造の確認です。面倒だったので、かなり適当ですが、イメージはわきました。高さを調整できるようにしようかと思っていましたが、1日の釣りで大量にインスタントウドンを作ることもないので、必要なさそうです。
【平キリ】
以前に作った平キリですが、3号竿を製作/補修するのに必要なサイズのみ作ったので、虫食い状態です。2mmから12mm程度まで0.2mm単位で揃えようと準備中です。8mmまでの不足分はすでに熱して叩いて平らにしています
 。
。
太い物は、熱して叩くのも大変なので、後回しになっています。とりあえず、写真の平らにしたものを削って、焼き入れをして、刃を付けることからやろうと思っています。
【玉網の枠】
現在使用しているものは、インターネットの写真と店で実物を見て、適当に考えて作ったものですが、このまえ誤って踏んでしまい、込みの上部に割れが入ってしまいました
 。まずはそれを修理してます。
。まずはそれを修理してます。
割れの入った部分に糸を巻いて補強。まあ、そもそも糸を巻いていなかったのが失敗なのですが、製作当時の1月は竹で物を作ることを始めたばかりでしたので、いまいち扱いがわかっていませんでした。あとは網を取り付けている糸を結びなおして、終了です。
最近こどもとも一緒にヘラに行っていることもあり、もうひとつ予備枠を作っておこうと準備中です。

こちらは、上○屋で見つけた100円の玉網の枠(割れが入っていたり、かなりショボい作りのものです)を材料にして、製作予定です。枠が大きすぎるので、柄の部分を切り取り、直径を30cmにして、新たに柄の部分を別の木で作りなおして完成させる予定です。
【その他】
これ以外にも、お膳(すでに万力部分の部品は入手)とか、玉網の柄の作りなおしとか、針はずしとか・・・・いっぱいあり過ぎてどうしていいかわかりません・・・
 。
。 2012年04月30日
削り穂製作
4月30日(月)
3号竿の穂先の根元が折れたので(ついでに穂持ちの継ぎ口も割ってしまいましたが・・・)、再度穂先(+穂持ち)作りなおしです。今回折れた部分をよく見ると、火入れを失敗して焦げている部分でした。固着を恐れて、しっかり差し込まなかったこともあり、この焦げた部分がちょうど一番力のかかる口の部分にあたっていたようです。細い竹は、火入れをしていると急激に温度が上がるためだと思いますが、突然焦げるので、弱火でゆっくりやらないとだめですね・・・ 。
。
さて、穂先製作ですが、以前作り方を詳細に記録するのを忘れたので、今回は記録しておきます。まず、材料ですがホームセンターで真竹の切ったものを購入。前回の写真ですが、これです。

実は真竹と思っていたのですが、調べると節が一重なのは孟宗竹(竿作りにはB級品?)だそうです 。まあ、とりあえず使えるし、手近で安価なのでOKでしょう。
。まあ、とりあえず使えるし、手近で安価なのでOKでしょう。
この竹を1cm程度に細く切って(割ろうと思ったのですが、なかなかうまく割れないので、のこぎりで切りました)、ざっとカンナを掛けたのが上の写真の真ん中のものです。節の出っ張りはざっと削りましたが、その後何度か火入れを行うとともに、節部分を火で炙って万力に軽く挟み、繊維が通るように圧縮しておきました。
そして、カンナを使って、竹の表面は残すようにまず四角柱を作っていきます。この四角柱をまっすぐにしかも太さを安定して作ると後が楽になります。四角柱ができたら、まず火入れをしてから、次に四角推にカンナで削りました。ここで作ったものがほぼそのまま穂先のイメージなので、特に慎重にまっすぐとテーパーを意識して削ります。穂先1.2mm程度、元部分4mm程度を目途にしていますので、四角推は1mm程度加えた穂先一辺2.5mm、元一辺5mm程度に仕上げました。
カンナを使う時の注意ですが、竹の繊維が手に刺さりやすいので、素手や軍手は危険です(一度刺さりました・・・ )。わたしはスキー用の手袋をはめてやってます。四角推ができた後には、またまた火入れをしてまっすぐにしておきました。
)。わたしはスキー用の手袋をはめてやってます。四角推ができた後には、またまた火入れをしてまっすぐにしておきました。

今度は、四角推から八角錐にします。木に彫刻刀でV字の溝を掘りそこに四角推の角を置いて、八角錐に削ります。カンナでも良いのですが、わたしの場合余分が1mmしかないので、つい削り過ぎてしまいそうなので、平ヤスリを使って削りました。

今度は八角錐から円錐にします。100円ショップで購入した園芸用道具(土を掘り起こすもののように見えますが、何かは知りません)にダイヤモンド丸ヤスリでU字に溝をつけ、それを万力に挟んで、竹を溝に入れて手前に引くと角が取れて円錐ができます。

下がこの段階でできあがった円錐ですが、竹の表皮の部分はできるだけ削らないようにしています(表皮に強度があるらしいです)。

この作業がほば完了という時に先っぽを20cmほどポキッとやってしまいました。慣れてきたので調子に乗って勢いよく往復でゴシゴシ削っていたせいです・・・ 。でも手元側に余裕があったので、予定より仕上がりを3~4cm短くすれば何とかなりそうです。ただ、穂先の全長の中に節がひとつだけの予定が二つ入ってしまいます。そして、元部分から少々削りなおしを余儀なくされましたが、なんとか作業は終了
。でも手元側に余裕があったので、予定より仕上がりを3~4cm短くすれば何とかなりそうです。ただ、穂先の全長の中に節がひとつだけの予定が二つ入ってしまいます。そして、元部分から少々削りなおしを余儀なくされましたが、なんとか作業は終了 。
。
そして、再び火入れ。それからドリルチャックに元部分を噛ませ、回転させながらサンドペーパーの60番、150番、240番と使って削りを終了。全体にさっとウレタンで下塗りして乾燥させ、先にリリアンをはめて糸で巻いて固定。その上にウレタンを塗って糸決めしました。

そして、今度は黒のうるしを2度塗り、軽くサンドペーパーの600番で水研ぎして、仕上げにうるしの本透明に透明を混ぜたものを塗り、金属磨きのピカットでテカりと表面を均すために軽く磨き、コンパウンドで磨いて完成しました 。
。

穂持ちも同時に完成したので、3号竿の復活です 。前回の3号竿より、穂持ちも少し太く、穂先の元径も太いので、穂先のテーパーはきつくなっています。硬調子の予定です。さて、実釣が楽しみです・・・
。前回の3号竿より、穂持ちも少し太く、穂先の元径も太いので、穂先のテーパーはきつくなっています。硬調子の予定です。さて、実釣が楽しみです・・・ 。
。
ところで、この3号竿、製作中に3番の穂持ち下を割ってしまったので、代わりの竹を使い、今回1番の穂先を折り、2番の穂持ちを割ったので、作り直しを余儀なくされました。つまり、最初設計段階から生き延びているのは、4番の手元だけだったりします・・・ 。
。
3号竿の穂先の根元が折れたので(ついでに穂持ちの継ぎ口も割ってしまいましたが・・・)、再度穂先(+穂持ち)作りなおしです。今回折れた部分をよく見ると、火入れを失敗して焦げている部分でした。固着を恐れて、しっかり差し込まなかったこともあり、この焦げた部分がちょうど一番力のかかる口の部分にあたっていたようです。細い竹は、火入れをしていると急激に温度が上がるためだと思いますが、突然焦げるので、弱火でゆっくりやらないとだめですね・・・
 。
。さて、穂先製作ですが、以前作り方を詳細に記録するのを忘れたので、今回は記録しておきます。まず、材料ですがホームセンターで真竹の切ったものを購入。前回の写真ですが、これです。

実は真竹と思っていたのですが、調べると節が一重なのは孟宗竹(竿作りにはB級品?)だそうです
 。まあ、とりあえず使えるし、手近で安価なのでOKでしょう。
。まあ、とりあえず使えるし、手近で安価なのでOKでしょう。この竹を1cm程度に細く切って(割ろうと思ったのですが、なかなかうまく割れないので、のこぎりで切りました)、ざっとカンナを掛けたのが上の写真の真ん中のものです。節の出っ張りはざっと削りましたが、その後何度か火入れを行うとともに、節部分を火で炙って万力に軽く挟み、繊維が通るように圧縮しておきました。
そして、カンナを使って、竹の表面は残すようにまず四角柱を作っていきます。この四角柱をまっすぐにしかも太さを安定して作ると後が楽になります。四角柱ができたら、まず火入れをしてから、次に四角推にカンナで削りました。ここで作ったものがほぼそのまま穂先のイメージなので、特に慎重にまっすぐとテーパーを意識して削ります。穂先1.2mm程度、元部分4mm程度を目途にしていますので、四角推は1mm程度加えた穂先一辺2.5mm、元一辺5mm程度に仕上げました。
カンナを使う時の注意ですが、竹の繊維が手に刺さりやすいので、素手や軍手は危険です(一度刺さりました・・・
 )。わたしはスキー用の手袋をはめてやってます。四角推ができた後には、またまた火入れをしてまっすぐにしておきました。
)。わたしはスキー用の手袋をはめてやってます。四角推ができた後には、またまた火入れをしてまっすぐにしておきました。
今度は、四角推から八角錐にします。木に彫刻刀でV字の溝を掘りそこに四角推の角を置いて、八角錐に削ります。カンナでも良いのですが、わたしの場合余分が1mmしかないので、つい削り過ぎてしまいそうなので、平ヤスリを使って削りました。

今度は八角錐から円錐にします。100円ショップで購入した園芸用道具(土を掘り起こすもののように見えますが、何かは知りません)にダイヤモンド丸ヤスリでU字に溝をつけ、それを万力に挟んで、竹を溝に入れて手前に引くと角が取れて円錐ができます。

下がこの段階でできあがった円錐ですが、竹の表皮の部分はできるだけ削らないようにしています(表皮に強度があるらしいです)。

この作業がほば完了という時に先っぽを20cmほどポキッとやってしまいました。慣れてきたので調子に乗って勢いよく往復でゴシゴシ削っていたせいです・・・
 。でも手元側に余裕があったので、予定より仕上がりを3~4cm短くすれば何とかなりそうです。ただ、穂先の全長の中に節がひとつだけの予定が二つ入ってしまいます。そして、元部分から少々削りなおしを余儀なくされましたが、なんとか作業は終了
。でも手元側に余裕があったので、予定より仕上がりを3~4cm短くすれば何とかなりそうです。ただ、穂先の全長の中に節がひとつだけの予定が二つ入ってしまいます。そして、元部分から少々削りなおしを余儀なくされましたが、なんとか作業は終了 。
。そして、再び火入れ。それからドリルチャックに元部分を噛ませ、回転させながらサンドペーパーの60番、150番、240番と使って削りを終了。全体にさっとウレタンで下塗りして乾燥させ、先にリリアンをはめて糸で巻いて固定。その上にウレタンを塗って糸決めしました。

そして、今度は黒のうるしを2度塗り、軽くサンドペーパーの600番で水研ぎして、仕上げにうるしの本透明に透明を混ぜたものを塗り、金属磨きのピカットでテカりと表面を均すために軽く磨き、コンパウンドで磨いて完成しました
 。
。
穂持ちも同時に完成したので、3号竿の復活です
 。前回の3号竿より、穂持ちも少し太く、穂先の元径も太いので、穂先のテーパーはきつくなっています。硬調子の予定です。さて、実釣が楽しみです・・・
。前回の3号竿より、穂持ちも少し太く、穂先の元径も太いので、穂先のテーパーはきつくなっています。硬調子の予定です。さて、実釣が楽しみです・・・ 。
。ところで、この3号竿、製作中に3番の穂持ち下を割ってしまったので、代わりの竹を使い、今回1番の穂先を折り、2番の穂持ちを割ったので、作り直しを余儀なくされました。つまり、最初設計段階から生き延びているのは、4番の手元だけだったりします・・・
 。
。2012年04月25日
竿掛けの製作 (後編)
4月25日(水)
さて、竿掛けの後編(前編はこちら)です。
【塗装3日目】
この前乾漆粉がうまくいかなかったので、再挑戦です。今度は、黒色の乾漆粉も作りました。作り方は黄色の時と同じです。これで下地の黒が乾漆粉の隙間から見えなくとも、色に黒が混じります。事前にすべての色を混ぜました。金粉も少し多めに・・・ 。
。

そして、乾漆粉の接着材としての役割の黒うるしですが、これも今回は一液性の透明ウレタンに変えてやってみることにしました。うまく着いたような気がします 。
。

【塗装4日目】
翌日の朝には乾漆粉の隙間を埋めるためにウレタンを塗って、昼には乾いていたので、もう一度塗りました。そして、夕方に400番で水研ぎ。そしてその上から、再度ウレタンを塗って本日終了。
【塗装5日目】
次の日の朝、まずは400番で水研ぎです。

曇ったようになった部分はほぼ平らになっているところです。赤マル部分には光った部分がありますが、これはまだ段差がある部分です。機能的には問題ないのですが、もう少しきれいに仕上げるために、あと1~2回は塗装と水研ぎをやる必要がありそうです。
水研ぎで籐の部分の色が少し剥げすぎましたので、うるしを指先につけて塗布。それ以外の竿全体にうるしの本透明を塗りました。そして夜になり、乾燥しているようなので、早速1000番のサンドペーパーで軽く水研ぎをするとまだ少し段差がありますが、この程度でOKでしょ・・・ということで、仕上げにうるしの本透明を竿全体に塗って就寝 。
。
【塗装6日目】
いよいよ最終仕上げです。このままだとピカピカ過ぎるので、七分程度程に上品に 光らせようと、家にあった金属磨きのピカット(よく皆さんがつかっているにはピカールというもののようです)でさーっとこすると簡単につや消しになりました。このままでも結構いい感じなのですが、もう少し光沢を出すために研磨フィルムの4000番と8000番で水研ぎ(今回は研磨フィルムを使いましたが、竹はデコボコのある曲面なのでコンパウンドの方が使いやすいです)。そして、塗装はこれにて完了。最後に口栓は竹を2重にして木工用ボンドで接着し、削って作成。竿掛けの完成です
光らせようと、家にあった金属磨きのピカット(よく皆さんがつかっているにはピカールというもののようです)でさーっとこすると簡単につや消しになりました。このままでも結構いい感じなのですが、もう少し光沢を出すために研磨フィルムの4000番と8000番で水研ぎ(今回は研磨フィルムを使いましたが、竹はデコボコのある曲面なのでコンパウンドの方が使いやすいです)。そして、塗装はこれにて完了。最後に口栓は竹を2重にして木工用ボンドで接着し、削って作成。竿掛けの完成です 。
。
まずは全体像の写真 。
。

そして手元のアップの写真 。
。

3号竿の持ち手と同じ色目にする予定ではなかったのですが、やはり赤色は塗装をしていくと存在感がなくなってしまい、3号竿の時とほぼ同じになってしまいましたので、並べて写真を撮りました。少し暗い赤を使っているからでしょう。次の機会にはもう少し派手な赤を混ぜてみたいと思います。
口糸を巻いた部分ですが、糸決めでウレタン1回、糸目を消すために黒色うるしを3回、乾漆粉を接着するのにウレタン1回、隙間を埋めるのに2回、そして水研ぎ、さらにウレタンを1回と水研ぎ、そして仕上げにうるしの本透明を2回と水研ぎ・・・と合計で10回も塗ったことになります。かなり手間がかかりました 。
。
わたしのように乾燥が待てない人は、薄く塗ること(薄く何度も塗る方が厚く塗るより乾燥もはるかに早いし、仕上げもきれいです)とウレタンを要所要所で使うことで(うるしよりも乾燥が早いので)、少しは早く仕上がります。でも乾燥する前に重ね塗りすると塗装がしわになったりするようなので、ご注意ください。塗装も慣れてくると、一回の作業が準備から片づけまで10~15分ほどしかかかりませんので、朝と夜に塗って、昼と夜中に乾燥させれば、作業が結構進みます。
ところでこの竿掛けはテーパーのない竹なので、どちらかというと玉網の柄向きだったかもしれません。改造しようかな・・・ 。
。
さて、竿掛けの後編(前編はこちら)です。
【塗装3日目】
この前乾漆粉がうまくいかなかったので、再挑戦です。今度は、黒色の乾漆粉も作りました。作り方は黄色の時と同じです。これで下地の黒が乾漆粉の隙間から見えなくとも、色に黒が混じります。事前にすべての色を混ぜました。金粉も少し多めに・・・
 。
。
そして、乾漆粉の接着材としての役割の黒うるしですが、これも今回は一液性の透明ウレタンに変えてやってみることにしました。うまく着いたような気がします
 。
。
【塗装4日目】
翌日の朝には乾漆粉の隙間を埋めるためにウレタンを塗って、昼には乾いていたので、もう一度塗りました。そして、夕方に400番で水研ぎ。そしてその上から、再度ウレタンを塗って本日終了。
【塗装5日目】
次の日の朝、まずは400番で水研ぎです。

曇ったようになった部分はほぼ平らになっているところです。赤マル部分には光った部分がありますが、これはまだ段差がある部分です。機能的には問題ないのですが、もう少しきれいに仕上げるために、あと1~2回は塗装と水研ぎをやる必要がありそうです。
水研ぎで籐の部分の色が少し剥げすぎましたので、うるしを指先につけて塗布。それ以外の竿全体にうるしの本透明を塗りました。そして夜になり、乾燥しているようなので、早速1000番のサンドペーパーで軽く水研ぎをするとまだ少し段差がありますが、この程度でOKでしょ・・・ということで、仕上げにうるしの本透明を竿全体に塗って就寝
 。
。【塗装6日目】
いよいよ最終仕上げです。このままだとピカピカ過ぎるので、七分程度程に上品に
 光らせようと、家にあった金属磨きのピカット(よく皆さんがつかっているにはピカールというもののようです)でさーっとこすると簡単につや消しになりました。このままでも結構いい感じなのですが、もう少し光沢を出すために研磨フィルムの4000番と8000番で水研ぎ(今回は研磨フィルムを使いましたが、竹はデコボコのある曲面なのでコンパウンドの方が使いやすいです)。そして、塗装はこれにて完了。最後に口栓は竹を2重にして木工用ボンドで接着し、削って作成。竿掛けの完成です
光らせようと、家にあった金属磨きのピカット(よく皆さんがつかっているにはピカールというもののようです)でさーっとこすると簡単につや消しになりました。このままでも結構いい感じなのですが、もう少し光沢を出すために研磨フィルムの4000番と8000番で水研ぎ(今回は研磨フィルムを使いましたが、竹はデコボコのある曲面なのでコンパウンドの方が使いやすいです)。そして、塗装はこれにて完了。最後に口栓は竹を2重にして木工用ボンドで接着し、削って作成。竿掛けの完成です 。
。まずは全体像の写真
 。
。
そして手元のアップの写真
 。
。
3号竿の持ち手と同じ色目にする予定ではなかったのですが、やはり赤色は塗装をしていくと存在感がなくなってしまい、3号竿の時とほぼ同じになってしまいましたので、並べて写真を撮りました。少し暗い赤を使っているからでしょう。次の機会にはもう少し派手な赤を混ぜてみたいと思います。
口糸を巻いた部分ですが、糸決めでウレタン1回、糸目を消すために黒色うるしを3回、乾漆粉を接着するのにウレタン1回、隙間を埋めるのに2回、そして水研ぎ、さらにウレタンを1回と水研ぎ、そして仕上げにうるしの本透明を2回と水研ぎ・・・と合計で10回も塗ったことになります。かなり手間がかかりました
 。
。わたしのように乾燥が待てない人は、薄く塗ること(薄く何度も塗る方が厚く塗るより乾燥もはるかに早いし、仕上げもきれいです)とウレタンを要所要所で使うことで(うるしよりも乾燥が早いので)、少しは早く仕上がります。でも乾燥する前に重ね塗りすると塗装がしわになったりするようなので、ご注意ください。塗装も慣れてくると、一回の作業が準備から片づけまで10~15分ほどしかかかりませんので、朝と夜に塗って、昼と夜中に乾燥させれば、作業が結構進みます。
ところでこの竿掛けはテーパーのない竹なので、どちらかというと玉網の柄向きだったかもしれません。改造しようかな・・・
 。
。 2012年04月18日
竿掛けの製作 (前編)
4月17日(火)
へら釣りを始めたのが年末の12月、そしてへら道具の製作を始めたのも12月。何もわからない中、始めて作ったのがこちらの竿掛けです。がんばって作ったのですが、今見ると、竹の曲がりは上手く取れてないし、火入れの焼きもムラだらけ。節は抜いてないので重く、込みの作りもガタつきあり。その上、塗りも適当、選んだ竹も節間が長く、節も出っぱっていてブサイク・・・と、まあ使っているのもはずかしくなってきました ・・・ので、新しく作ることにしました
・・・ので、新しく作ることにしました 。
。
管理池用に90cm程度の短めのものを製作したいと思います。万力との継ぎ口の塗装は、前回3号竿の握り手に籐と乾漆粉(本漆ではなく合成うるしの粉)を使いましたが、いくつか改善できそうな点があったので、それを試してみたいと思います。
【竹材選定】
竹材は、前回購入したホームセンター竹(直径15mm程度、篠竹10本入350円程度)の残りから探しました。そして、表面は少々傷みがあり、テーパーがほとんどないのが難点ですが、節間も長くなく、節も低い矢竹のような一本を発見 。90cmで6節なので、まあ良い感じです。
。90cmで6節なので、まあ良い感じです。
【火入れ】
弓型に曲がっていましたので、火入れは結構苦労しましたが、三度やって、なんとか使える程度にはまっすぐに。曲がりを取るには、竹を火で炙ってやわらかくしてから、矯め木(下写真)という道具を使って矯正するのですが、なかなか難しい作業です。まずすべて節間をまっすぐに、その後節前後の曲がりを取ると上手くいくようです。

この矯め木、作るのは簡単です。竹の太さに合わせて何種類か必要になります。太い用は木もしっかりしたものを選ばないと折れそうになります。ちなみにわたしのは折れそうです・・・ 。
。
火入れはキッチンの普通のガスコンロの上に耐火レンガを二つ乗せてやってます。下の写真のような感じです(写真の竹は今回のものではありません)。

【節抜き】
火入れのあとは節抜きです。錐をベンチバイス(万力)に挟んで、竹を両手のひらで挟み、キリモミのようにすると簡単に節が抜けます。この節抜き用の錐は先日記事にした平キリ製作とまったく作り方は同じですが、長さ1m、直径2.5~3mmのピアノ線を使い、両端に0.5mm差で刃を付けています。刃の形は平キリよりも穴を開けやすいように細長く作りました。4.5mm~8mmまで、0.5mm毎に8タイプ(4本)製作しました(8mmのものは3mmのピアノ線では細くてたたくと薄くなり過ぎるので、作りやすい平キリと同じ刃型になっています)。

【下処理】
枝が出ていた節の芽を電動ルーターを使ってきれいに、そして塗装がのるように竹全体の表面を600番程度のサンドペーパーでさっと水研ぎしました。また、糸を巻くところをナイフを使って、竹表面を削ります。削ると言っても、刃をあててスーッとこする感じです。キシャギというそうです。
【糸巻きと込み口削り】
面倒なので仮巻きはせずに、本番の糸や籐を巻いて、マスキングテープでほどけないように端をとめてから、込み口を削りました。込み口は、弓と万力の込みにあわせて開けますが、前回作成した平キリは、竿用に7.6mm程度までしか作っていなかったので、今回は木工用ドリルと棒ヤスリを使って削りました。

【塗装1日目】
本来なら下塗りのウレタン塗装から始めるのですが、籐部分は隙間にウレタンが入りこむと籐の隙間にうるしを入れ込むスペースがなくなり、3号竿の時のように塗りにムラがでるので、先に籐部分から塗りました。うるしは透と本透明に少量の黒を混ぜました。両サイドをマスキングテープでとめて、2時間ほどして表面が固まってきた頃にテープを剥がし、つまようじを使って際の処理をしました。結構きれいにできました。

次に続けて、糸巻き部分は糸決め(糸を固める目的)のために、竹表面がでている胴部分は下塗りのためにウレタンを薄く塗りました。ウレタンは一般的には2液性が良いとのことですが、面倒なので、1液性を愛用しています。そして数時間乾燥させてから(薄塗りなのですぐ乾く)、口糸巻き部分と節の芽部分には黒色のうるしを塗り、1日程度乾燥です。なお、塗装や乾燥は風呂場を使っています。ホコリが少ない上に換気扇もあり、また浴室乾燥をONにすると乾きも早く最高です 。
。

【塗装2日目】
そして、2日目の塗装です。今回は口糸巻き部分と籐部分に前回同様の色を、そして胴部分に透明と本透明のうるしを混ぜたものを塗りました。なんとなく雰囲気がでてきました。

本当は、1日待つつもりだったのですが、いつもの如く、待てず・・・ 。半日乾燥させたので、まず胴に透明を塗りました。そして次に口糸巻き部分にまず黒色を塗り、その上から乾漆粉を混ぜたものをパラパラと・・・。最後は紙で押さえて、しっかりと粉をうるしにつけます。
。半日乾燥させたので、まず胴に透明を塗りました。そして次に口糸巻き部分にまず黒色を塗り、その上から乾漆粉を混ぜたものをパラパラと・・・。最後は紙で押さえて、しっかりと粉をうるしにつけます。

見てお分かりのように、色が超ケバイ 。前回、赤色が少な過ぎて、イメージと違ったので、今回は赤を大量に入れたんですが、入れ過ぎたかも・・・。おまけに丁寧に粉を撒きすぎて隙間がなく、下地の黒色が見えない・・・
。前回、赤色が少な過ぎて、イメージと違ったので、今回は赤を大量に入れたんですが、入れ過ぎたかも・・・。おまけに丁寧に粉を撒きすぎて隙間がなく、下地の黒色が見えない・・・ 。でも、これはこれでええっか~と、しばらく乾燥させました。・・・が、少し下地を出せないかなと表面をそっと擦ると、なんとボロボロと粉が落ちるではありませんか・・・
。でも、これはこれでええっか~と、しばらく乾燥させました。・・・が、少し下地を出せないかなと表面をそっと擦ると、なんとボロボロと粉が落ちるではありませんか・・・ 。どうやら黒のうるしを少し薄めて塗ったのがいけなかったようで、粘度が落ちてしっかりとひっついていないようです。
。どうやら黒のうるしを少し薄めて塗ったのがいけなかったようで、粘度が落ちてしっかりとひっついていないようです。
少しハゲてしまった場所もあり、「もうこうなったら、全部落としたろ~ 」とやってしまいました
」とやってしまいました 。そして、全部は取れなかったので、サンドペーパーで水研ぎしました。
。そして、全部は取れなかったので、サンドペーパーで水研ぎしました。

まだ少し粉が残ってますが、これ以上研ぐと糸まで到達してしまうので、ここらでやめて、再度黒色を塗って原状回復。ちょっと焦りましたが、何とか元通りになりました 。
。
さて、続きをやりたいところですが、しばらく時間がないので、週末以降に・・・ 。後編はこちら。
。後編はこちら。
へら釣りを始めたのが年末の12月、そしてへら道具の製作を始めたのも12月。何もわからない中、始めて作ったのがこちらの竿掛けです。がんばって作ったのですが、今見ると、竹の曲がりは上手く取れてないし、火入れの焼きもムラだらけ。節は抜いてないので重く、込みの作りもガタつきあり。その上、塗りも適当、選んだ竹も節間が長く、節も出っぱっていてブサイク・・・と、まあ使っているのもはずかしくなってきました
 ・・・ので、新しく作ることにしました
・・・ので、新しく作ることにしました 。
。管理池用に90cm程度の短めのものを製作したいと思います。万力との継ぎ口の塗装は、前回3号竿の握り手に籐と乾漆粉(本漆ではなく合成うるしの粉)を使いましたが、いくつか改善できそうな点があったので、それを試してみたいと思います。
【竹材選定】
竹材は、前回購入したホームセンター竹(直径15mm程度、篠竹10本入350円程度)の残りから探しました。そして、表面は少々傷みがあり、テーパーがほとんどないのが難点ですが、節間も長くなく、節も低い矢竹のような一本を発見
 。90cmで6節なので、まあ良い感じです。
。90cmで6節なので、まあ良い感じです。【火入れ】
弓型に曲がっていましたので、火入れは結構苦労しましたが、三度やって、なんとか使える程度にはまっすぐに。曲がりを取るには、竹を火で炙ってやわらかくしてから、矯め木(下写真)という道具を使って矯正するのですが、なかなか難しい作業です。まずすべて節間をまっすぐに、その後節前後の曲がりを取ると上手くいくようです。

この矯め木、作るのは簡単です。竹の太さに合わせて何種類か必要になります。太い用は木もしっかりしたものを選ばないと折れそうになります。ちなみにわたしのは折れそうです・・・
 。
。火入れはキッチンの普通のガスコンロの上に耐火レンガを二つ乗せてやってます。下の写真のような感じです(写真の竹は今回のものではありません)。

【節抜き】
火入れのあとは節抜きです。錐をベンチバイス(万力)に挟んで、竹を両手のひらで挟み、キリモミのようにすると簡単に節が抜けます。この節抜き用の錐は先日記事にした平キリ製作とまったく作り方は同じですが、長さ1m、直径2.5~3mmのピアノ線を使い、両端に0.5mm差で刃を付けています。刃の形は平キリよりも穴を開けやすいように細長く作りました。4.5mm~8mmまで、0.5mm毎に8タイプ(4本)製作しました(8mmのものは3mmのピアノ線では細くてたたくと薄くなり過ぎるので、作りやすい平キリと同じ刃型になっています)。

【下処理】
枝が出ていた節の芽を電動ルーターを使ってきれいに、そして塗装がのるように竹全体の表面を600番程度のサンドペーパーでさっと水研ぎしました。また、糸を巻くところをナイフを使って、竹表面を削ります。削ると言っても、刃をあててスーッとこする感じです。キシャギというそうです。
【糸巻きと込み口削り】
面倒なので仮巻きはせずに、本番の糸や籐を巻いて、マスキングテープでほどけないように端をとめてから、込み口を削りました。込み口は、弓と万力の込みにあわせて開けますが、前回作成した平キリは、竿用に7.6mm程度までしか作っていなかったので、今回は木工用ドリルと棒ヤスリを使って削りました。

【塗装1日目】
本来なら下塗りのウレタン塗装から始めるのですが、籐部分は隙間にウレタンが入りこむと籐の隙間にうるしを入れ込むスペースがなくなり、3号竿の時のように塗りにムラがでるので、先に籐部分から塗りました。うるしは透と本透明に少量の黒を混ぜました。両サイドをマスキングテープでとめて、2時間ほどして表面が固まってきた頃にテープを剥がし、つまようじを使って際の処理をしました。結構きれいにできました。

次に続けて、糸巻き部分は糸決め(糸を固める目的)のために、竹表面がでている胴部分は下塗りのためにウレタンを薄く塗りました。ウレタンは一般的には2液性が良いとのことですが、面倒なので、1液性を愛用しています。そして数時間乾燥させてから(薄塗りなのですぐ乾く)、口糸巻き部分と節の芽部分には黒色のうるしを塗り、1日程度乾燥です。なお、塗装や乾燥は風呂場を使っています。ホコリが少ない上に換気扇もあり、また浴室乾燥をONにすると乾きも早く最高です
 。
。
【塗装2日目】
そして、2日目の塗装です。今回は口糸巻き部分と籐部分に前回同様の色を、そして胴部分に透明と本透明のうるしを混ぜたものを塗りました。なんとなく雰囲気がでてきました。

本当は、1日待つつもりだったのですが、いつもの如く、待てず・・・
 。半日乾燥させたので、まず胴に透明を塗りました。そして次に口糸巻き部分にまず黒色を塗り、その上から乾漆粉を混ぜたものをパラパラと・・・。最後は紙で押さえて、しっかりと粉をうるしにつけます。
。半日乾燥させたので、まず胴に透明を塗りました。そして次に口糸巻き部分にまず黒色を塗り、その上から乾漆粉を混ぜたものをパラパラと・・・。最後は紙で押さえて、しっかりと粉をうるしにつけます。
見てお分かりのように、色が超ケバイ
 。前回、赤色が少な過ぎて、イメージと違ったので、今回は赤を大量に入れたんですが、入れ過ぎたかも・・・。おまけに丁寧に粉を撒きすぎて隙間がなく、下地の黒色が見えない・・・
。前回、赤色が少な過ぎて、イメージと違ったので、今回は赤を大量に入れたんですが、入れ過ぎたかも・・・。おまけに丁寧に粉を撒きすぎて隙間がなく、下地の黒色が見えない・・・ 。でも、これはこれでええっか~と、しばらく乾燥させました。・・・が、少し下地を出せないかなと表面をそっと擦ると、なんとボロボロと粉が落ちるではありませんか・・・
。でも、これはこれでええっか~と、しばらく乾燥させました。・・・が、少し下地を出せないかなと表面をそっと擦ると、なんとボロボロと粉が落ちるではありませんか・・・ 。どうやら黒のうるしを少し薄めて塗ったのがいけなかったようで、粘度が落ちてしっかりとひっついていないようです。
。どうやら黒のうるしを少し薄めて塗ったのがいけなかったようで、粘度が落ちてしっかりとひっついていないようです。少しハゲてしまった場所もあり、「もうこうなったら、全部落としたろ~
 」とやってしまいました
」とやってしまいました 。そして、全部は取れなかったので、サンドペーパーで水研ぎしました。
。そして、全部は取れなかったので、サンドペーパーで水研ぎしました。
まだ少し粉が残ってますが、これ以上研ぐと糸まで到達してしまうので、ここらでやめて、再度黒色を塗って原状回復。ちょっと焦りましたが、何とか元通りになりました
 。
。さて、続きをやりたいところですが、しばらく時間がないので、週末以降に・・・
 。後編はこちら。
。後編はこちら。 2012年04月10日
3号竿完成
4月10日(火)
先日より作っていた3号竿ですが・・・
3番「穂持ち下」を節抜きの最中に割るというアクシデント にもめげず
にもめげず 、なんとか代わりの竹を探して、最後まで完成できました
、なんとか代わりの竹を探して、最後まで完成できました 。
。
ホームセンターで売っている園芸用の竹で作った、いわゆる園芸竿です 。これでも普通に魚は釣れるんです
。これでも普通に魚は釣れるんです 。まずは全体写真
。まずは全体写真 。
。

穂持ち下の3番と手元の4番は竹の表面がかなり荒れていたのと、ヒビらしきものがあったので、中間部分にも糸を巻き「アラ隠し兼補強」としました。
穂持ちの2番は節を削って、その部分は糸を巻き補強、上3/4は黒塗りにしました。穂先は2号竿のものを短く切って流用、ただし込み部分を作る際に竹の表皮を残そうと片側に偏って削ったために、穂持ちに少し傾いて刺さってしまいます 。ま、愛嬌です
。ま、愛嬌です 。しばらく使ってみて、まだまだ使えそうな竿だと思ったら、後に穂先を新調します。
。しばらく使ってみて、まだまだ使えそうな竿だと思ったら、後に穂先を新調します。
次に上部の写真 です。
です。

割ってしまった穂持ち下の3番はまっすぐで良い竹だったんでが、なんとか選んだ代わりの竹は、写真の矢印のところで節がずれているのがわかると思います 。これは火入れをしてもまっすぐにできないやつなので、仕方ないです。このせいで節も抜けませんので、穂先のみ手元に収納する3本仕舞いになってます。
。これは火入れをしてもまっすぐにできないやつなので、仕方ないです。このせいで節も抜けませんので、穂先のみ手元に収納する3本仕舞いになってます。
最後に握り手の写真です 。
。

作り方はこの前の記事で書きましたが、乾漆粉を使ってみました。赤色がもう少しでるはずだったのですが、混ぜる量が少な過ぎて、ほとんどわかりません・・・ 。あと、籐を巻く時に強化のために下にエポキシボンドを塗ってから巻いたのですが、そのエポキシが籐の隙間に一部入ってしまい、後ほど上から黒うるしを塗っても隙間に色がつかず、まだらになってしまいました・・・
。あと、籐を巻く時に強化のために下にエポキシボンドを塗ってから巻いたのですが、そのエポキシが籐の隙間に一部入ってしまい、後ほど上から黒うるしを塗っても隙間に色がつかず、まだらになってしまいました・・・ 。
。
まだまだ人に見せられるレベルではありませんが、ボチボチと工具も揃ってきたし、竹も集めつつあるので、その内に4号竿も作りたいと思います 。ま、その前にタモの柄と竿掛けですが、前回は竿作りの練習も兼ねて、適当に作ってみたので、もう少しましなやつを作りなおしたいと思っています。
。ま、その前にタモの柄と竿掛けですが、前回は竿作りの練習も兼ねて、適当に作ってみたので、もう少しましなやつを作りなおしたいと思っています。
竿作り、なかなかおもしろいです 。
。
先日より作っていた3号竿ですが・・・

3番「穂持ち下」を節抜きの最中に割るというアクシデント
 にもめげず
にもめげず 、なんとか代わりの竹を探して、最後まで完成できました
、なんとか代わりの竹を探して、最後まで完成できました 。
。ホームセンターで売っている園芸用の竹で作った、いわゆる園芸竿です
 。これでも普通に魚は釣れるんです
。これでも普通に魚は釣れるんです 。まずは全体写真
。まずは全体写真 。
。
穂持ち下の3番と手元の4番は竹の表面がかなり荒れていたのと、ヒビらしきものがあったので、中間部分にも糸を巻き「アラ隠し兼補強」としました。
穂持ちの2番は節を削って、その部分は糸を巻き補強、上3/4は黒塗りにしました。穂先は2号竿のものを短く切って流用、ただし込み部分を作る際に竹の表皮を残そうと片側に偏って削ったために、穂持ちに少し傾いて刺さってしまいます
 。ま、愛嬌です
。ま、愛嬌です 。しばらく使ってみて、まだまだ使えそうな竿だと思ったら、後に穂先を新調します。
。しばらく使ってみて、まだまだ使えそうな竿だと思ったら、後に穂先を新調します。次に上部の写真
 です。
です。
割ってしまった穂持ち下の3番はまっすぐで良い竹だったんでが、なんとか選んだ代わりの竹は、写真の矢印のところで節がずれているのがわかると思います
 。これは火入れをしてもまっすぐにできないやつなので、仕方ないです。このせいで節も抜けませんので、穂先のみ手元に収納する3本仕舞いになってます。
。これは火入れをしてもまっすぐにできないやつなので、仕方ないです。このせいで節も抜けませんので、穂先のみ手元に収納する3本仕舞いになってます。最後に握り手の写真です
 。
。
作り方はこの前の記事で書きましたが、乾漆粉を使ってみました。赤色がもう少しでるはずだったのですが、混ぜる量が少な過ぎて、ほとんどわかりません・・・
 。あと、籐を巻く時に強化のために下にエポキシボンドを塗ってから巻いたのですが、そのエポキシが籐の隙間に一部入ってしまい、後ほど上から黒うるしを塗っても隙間に色がつかず、まだらになってしまいました・・・
。あと、籐を巻く時に強化のために下にエポキシボンドを塗ってから巻いたのですが、そのエポキシが籐の隙間に一部入ってしまい、後ほど上から黒うるしを塗っても隙間に色がつかず、まだらになってしまいました・・・ 。
。まだまだ人に見せられるレベルではありませんが、ボチボチと工具も揃ってきたし、竹も集めつつあるので、その内に4号竿も作りたいと思います
 。ま、その前にタモの柄と竿掛けですが、前回は竿作りの練習も兼ねて、適当に作ってみたので、もう少しましなやつを作りなおしたいと思っています。
。ま、その前にタモの柄と竿掛けですが、前回は竿作りの練習も兼ねて、適当に作ってみたので、もう少しましなやつを作りなおしたいと思っています。竿作り、なかなかおもしろいです
 。
。 タグ :3号竿
2012年04月04日
3号竿 握り手
4月4日(水)
3号竿の握り手ですが、シンプルに籐と糸巻きでいこうと思っていたのですが、ネットを見ていると乾漆粉というのを使った塗りがあり、なかなか魅力的だったので、試してみることにしました 。
。
赤・黄・緑の乾漆粉をお店で探しましたが、赤と緑しか見つけられず 。黄色も欲しかったので、本漆の乾漆粉の作り方を調べて真似して作ることに・・・・。適当なガラス板がなかったので、お酒のワンカップのビンを使用して、合成うるしの黄色を薄く塗り、翌日にある程度乾燥後、お湯に付けてから(必要ないかもしれません)、そーっと鉄定規で剥がすといとも簡単に・・・
。黄色も欲しかったので、本漆の乾漆粉の作り方を調べて真似して作ることに・・・・。適当なガラス板がなかったので、お酒のワンカップのビンを使用して、合成うるしの黄色を薄く塗り、翌日にある程度乾燥後、お湯に付けてから(必要ないかもしれません)、そーっと鉄定規で剥がすといとも簡単に・・・ 。
。

接着面はまだベトツキ感がありましたので、半日ほど乾燥させ、これを粉々に砕いて、完成 。今回使う粉は金粉も含めて以下のとおり。
。今回使う粉は金粉も含めて以下のとおり。

乾漆粉を塗る前の握り手は下の写真のような感じです。すでに両サイドの籐には、黒うるしを3度ほど塗って乾燥させた後、平らになるようにサンドペーパーで水研ぎしてます。中央部分は、糸を巻き、その上から糸目が見えなくなるまで、黒うるしを4度塗っています。この部分に乾漆粉を付けることにしてます。

まず、籐部分にマスキングテープを張ります。そして、中央部分に接着剤の役割&背景色のために黒うるしを塗り、表面が乾く前に、乾漆粉を振りかけます。乾漆粉は事前に混ぜておきました。緑10に対して、赤・黄・金、すべて2の割合で入れました。混ぜたときには赤も結構目立っていたのですが、実際に塗るとほとんど見えなくなってしまいました 。写真では金色はあまり光っていないようですが、実際には金色がピカピカそして黄色が目立ちます(ケバイです・・・
。写真では金色はあまり光っていないようですが、実際には金色がピカピカそして黄色が目立ちます(ケバイです・・・ )。
)。

そして、1日乾燥後、ウレタンを上から塗って定着させます。そして、また乾燥。1日は待てず 、12時間程度で、マスキングテープをはずし、水研ぎ。
、12時間程度で、マスキングテープをはずし、水研ぎ。

そして、両サイドの籐の部分にうるしの透明に黒を少し混ぜて塗りました。

もう、完成間近です 。ややアンティークな雰囲気になってきました。赤がもう少し出てるとイメージどおりだったのですが、まあ次回の課題です。これからは、あともう一度籐部分に透明を塗って乾燥、そして握り手全体にウレタンを2度ほどかけて、最後にウレタンのテカテカを少し曇らせて出来上がりって感じです。乾漆粉の部分にもう少し透明感がでることになるので、どんな感じになるか楽しみです。この続きは、竿の完成の時に・・・
。ややアンティークな雰囲気になってきました。赤がもう少し出てるとイメージどおりだったのですが、まあ次回の課題です。これからは、あともう一度籐部分に透明を塗って乾燥、そして握り手全体にウレタンを2度ほどかけて、最後にウレタンのテカテカを少し曇らせて出来上がりって感じです。乾漆粉の部分にもう少し透明感がでることになるので、どんな感じになるか楽しみです。この続きは、竿の完成の時に・・・ 。
。
3号竿の握り手ですが、シンプルに籐と糸巻きでいこうと思っていたのですが、ネットを見ていると乾漆粉というのを使った塗りがあり、なかなか魅力的だったので、試してみることにしました
 。
。赤・黄・緑の乾漆粉をお店で探しましたが、赤と緑しか見つけられず
 。黄色も欲しかったので、本漆の乾漆粉の作り方を調べて真似して作ることに・・・・。適当なガラス板がなかったので、お酒のワンカップのビンを使用して、合成うるしの黄色を薄く塗り、翌日にある程度乾燥後、お湯に付けてから(必要ないかもしれません)、そーっと鉄定規で剥がすといとも簡単に・・・
。黄色も欲しかったので、本漆の乾漆粉の作り方を調べて真似して作ることに・・・・。適当なガラス板がなかったので、お酒のワンカップのビンを使用して、合成うるしの黄色を薄く塗り、翌日にある程度乾燥後、お湯に付けてから(必要ないかもしれません)、そーっと鉄定規で剥がすといとも簡単に・・・ 。
。
接着面はまだベトツキ感がありましたので、半日ほど乾燥させ、これを粉々に砕いて、完成
 。今回使う粉は金粉も含めて以下のとおり。
。今回使う粉は金粉も含めて以下のとおり。
乾漆粉を塗る前の握り手は下の写真のような感じです。すでに両サイドの籐には、黒うるしを3度ほど塗って乾燥させた後、平らになるようにサンドペーパーで水研ぎしてます。中央部分は、糸を巻き、その上から糸目が見えなくなるまで、黒うるしを4度塗っています。この部分に乾漆粉を付けることにしてます。

まず、籐部分にマスキングテープを張ります。そして、中央部分に接着剤の役割&背景色のために黒うるしを塗り、表面が乾く前に、乾漆粉を振りかけます。乾漆粉は事前に混ぜておきました。緑10に対して、赤・黄・金、すべて2の割合で入れました。混ぜたときには赤も結構目立っていたのですが、実際に塗るとほとんど見えなくなってしまいました
 。写真では金色はあまり光っていないようですが、実際には金色がピカピカそして黄色が目立ちます(ケバイです・・・
。写真では金色はあまり光っていないようですが、実際には金色がピカピカそして黄色が目立ちます(ケバイです・・・ )。
)。
そして、1日乾燥後、ウレタンを上から塗って定着させます。そして、また乾燥。1日は待てず
 、12時間程度で、マスキングテープをはずし、水研ぎ。
、12時間程度で、マスキングテープをはずし、水研ぎ。
そして、両サイドの籐の部分にうるしの透明に黒を少し混ぜて塗りました。

もう、完成間近です
 。ややアンティークな雰囲気になってきました。赤がもう少し出てるとイメージどおりだったのですが、まあ次回の課題です。これからは、あともう一度籐部分に透明を塗って乾燥、そして握り手全体にウレタンを2度ほどかけて、最後にウレタンのテカテカを少し曇らせて出来上がりって感じです。乾漆粉の部分にもう少し透明感がでることになるので、どんな感じになるか楽しみです。この続きは、竿の完成の時に・・・
。ややアンティークな雰囲気になってきました。赤がもう少し出てるとイメージどおりだったのですが、まあ次回の課題です。これからは、あともう一度籐部分に透明を塗って乾燥、そして握り手全体にウレタンを2度ほどかけて、最後にウレタンのテカテカを少し曇らせて出来上がりって感じです。乾漆粉の部分にもう少し透明感がでることになるので、どんな感じになるか楽しみです。この続きは、竿の完成の時に・・・ 。
。 2012年03月28日
3号竿のその後
3月28日(水)
先日、バキッといった製作中の3号竿ですが、結局へなへなの在庫竹を再度見直し、なんとか使えそうなものを見つけて、3番(穂持ち下)のみの入れ替えができることになりました 。ただし、手元の4番との込みはサイズが合っているのですが、穂持ちの2番の込みに対しては、少し先径が太いです。前回の竹よりテーパーが小さいんですが、まあいっか~ということで・・・
。ただし、手元の4番との込みはサイズが合っているのですが、穂持ちの2番の込みに対しては、少し先径が太いです。前回の竹よりテーパーが小さいんですが、まあいっか~ということで・・・ 。
。
ただ、節が一部裂けていたり 、また竹表面がかなり傷んでいるので
、また竹表面がかなり傷んでいるので 、そこを隠すためにも節を削り、節巻きにしました。それにあわせて手元の4番も糸を巻きました。糸を巻く作業は大変なんですが、糸巻きの治具を作ったので、作業も結構スムーズにいきました。そして、握り手を新聞紙で作り、瞬間接着剤で固めて、その上から籐と糸を巻きました。あとは塗装をするだけです
、そこを隠すためにも節を削り、節巻きにしました。それにあわせて手元の4番も糸を巻きました。糸を巻く作業は大変なんですが、糸巻きの治具を作ったので、作業も結構スムーズにいきました。そして、握り手を新聞紙で作り、瞬間接着剤で固めて、その上から籐と糸を巻きました。あとは塗装をするだけです 。
。

2番の穂持ちは上部2/3はすべて黒うるしで塗る予定です。握り手は、どんな装飾にしようかと考えていますが、シンプルにそのままいってしまうかもしれません。
まあ、一歩前進ということで・・・
先日、バキッといった製作中の3号竿ですが、結局へなへなの在庫竹を再度見直し、なんとか使えそうなものを見つけて、3番(穂持ち下)のみの入れ替えができることになりました
 。ただし、手元の4番との込みはサイズが合っているのですが、穂持ちの2番の込みに対しては、少し先径が太いです。前回の竹よりテーパーが小さいんですが、まあいっか~ということで・・・
。ただし、手元の4番との込みはサイズが合っているのですが、穂持ちの2番の込みに対しては、少し先径が太いです。前回の竹よりテーパーが小さいんですが、まあいっか~ということで・・・ 。
。ただ、節が一部裂けていたり
 、また竹表面がかなり傷んでいるので
、また竹表面がかなり傷んでいるので 、そこを隠すためにも節を削り、節巻きにしました。それにあわせて手元の4番も糸を巻きました。糸を巻く作業は大変なんですが、糸巻きの治具を作ったので、作業も結構スムーズにいきました。そして、握り手を新聞紙で作り、瞬間接着剤で固めて、その上から籐と糸を巻きました。あとは塗装をするだけです
、そこを隠すためにも節を削り、節巻きにしました。それにあわせて手元の4番も糸を巻きました。糸を巻く作業は大変なんですが、糸巻きの治具を作ったので、作業も結構スムーズにいきました。そして、握り手を新聞紙で作り、瞬間接着剤で固めて、その上から籐と糸を巻きました。あとは塗装をするだけです 。
。
2番の穂持ちは上部2/3はすべて黒うるしで塗る予定です。握り手は、どんな装飾にしようかと考えていますが、シンプルにそのままいってしまうかもしれません。
まあ、一歩前進ということで・・・

タグ :3号竿
2012年03月23日
3号竿が・・・
3月23日(金)
明日もまた雨で荒れ模様。ここのところ土曜日はずっと荒れ模様なので、全然磯にいけてません。そろそろグレも一旦終了なので、行ってみたかったのですが・・・ 。
。
=======================================
さて、この前の祝日の火曜日ですが、日曜に平キリを作ったので、3号竿の製作に実際に使用してみました 。
。
まず♂の込みの方を平ヤスリで削ってはノギスで測りを繰り返して、予定通りのテーパーに仕上げました。平ヤスリは金属用を使っていますが、よく切れるというやつを1500円程度で先日購入しましたが、やはりよく切れるのは、作業がやりやすいです。
そして、次に込み口の製作です。糸巻きはすでに終わっていますので、平キリを使って細いのから順に穴を開けていきました。そして込みの先径と同じ大きさで穴をあけた後は、それより0.2mm大きいもので、4/5の深さまで、さらに0.2mm大きいもので3/5、・・・と段をつけます。最後に棒ヤスリで段差を削り、テーパーがある穴が完成します。最後に込みを差し、調整して完成です 。
。


ここまでほんとスムーズに作業がすすみました。全部を継いでみて、若干の曲がりを火入れして修正。あとは、握り手を作るのと塗りをするだけです 。
。
しかし、ここにきて欲がでました 。予定では穂先を4番の中に収め、2番、3番はそのままで3本仕舞いとすことにしていましたが、あまりにスムーズにここまできたので、2番を4番に収め、1番を3番に収める一般的な2本仕舞いにしたくなったのです。そして、3番の節抜きをすることにしました。これも順調に進み、後1節ぬけば終了となりました。・・・が、そこで油断してしまい、強引に力を入れたために、
。予定では穂先を4番の中に収め、2番、3番はそのままで3本仕舞いとすことにしていましたが、あまりにスムーズにここまできたので、2番を4番に収め、1番を3番に収める一般的な2本仕舞いにしたくなったのです。そして、3番の節抜きをすることにしました。これも順調に進み、後1節ぬけば終了となりました。・・・が、そこで油断してしまい、強引に力を入れたために、
「バキッ・・・ 」
」
ここで落ち着いて節抜き用のキリを抜けば、まだ被害は少なかったのですが、あせってしまい これまた強引に引き抜いてしまいました
これまた強引に引き抜いてしまいました 。すると再び、
。すると再び、
「バキバキッ・・・ 」
」
暗がりで作業をしていたのですが、家の中に持って入ってよく見ると、竹にヒビが2箇所も、しかも節を超えてほぼ端から端まで・・・ 。
。
これがまだ手元の4番だったら、適当な竹を見つけてやり直せばいいのですが、3番というのは上は2番と、下は4番とサイズをミリ以下の単位で合わせているので、上下両方のサイズに合う同じような太さとテーパーの竹を探すのは無理です。家にあるヘナヘナの竹を何度もみましたが、フィットするものはやはりなし。この3番は小節で特に気に入っていたので、ダメージ大です
 。
。
方法は2つ。3番、4番と2本入れ替えるか、割れの入った3番を糸でぐるぐる巻きにして修理するかです。どちらにするか現在、悩み中です 。
。
明日もまた雨で荒れ模様。ここのところ土曜日はずっと荒れ模様なので、全然磯にいけてません。そろそろグレも一旦終了なので、行ってみたかったのですが・・・
 。
。=======================================
さて、この前の祝日の火曜日ですが、日曜に平キリを作ったので、3号竿の製作に実際に使用してみました
 。
。まず♂の込みの方を平ヤスリで削ってはノギスで測りを繰り返して、予定通りのテーパーに仕上げました。平ヤスリは金属用を使っていますが、よく切れるというやつを1500円程度で先日購入しましたが、やはりよく切れるのは、作業がやりやすいです。
そして、次に込み口の製作です。糸巻きはすでに終わっていますので、平キリを使って細いのから順に穴を開けていきました。そして込みの先径と同じ大きさで穴をあけた後は、それより0.2mm大きいもので、4/5の深さまで、さらに0.2mm大きいもので3/5、・・・と段をつけます。最後に棒ヤスリで段差を削り、テーパーがある穴が完成します。最後に込みを差し、調整して完成です
 。
。

ここまでほんとスムーズに作業がすすみました。全部を継いでみて、若干の曲がりを火入れして修正。あとは、握り手を作るのと塗りをするだけです
 。
。しかし、ここにきて欲がでました
 。予定では穂先を4番の中に収め、2番、3番はそのままで3本仕舞いとすことにしていましたが、あまりにスムーズにここまできたので、2番を4番に収め、1番を3番に収める一般的な2本仕舞いにしたくなったのです。そして、3番の節抜きをすることにしました。これも順調に進み、後1節ぬけば終了となりました。・・・が、そこで油断してしまい、強引に力を入れたために、
。予定では穂先を4番の中に収め、2番、3番はそのままで3本仕舞いとすことにしていましたが、あまりにスムーズにここまできたので、2番を4番に収め、1番を3番に収める一般的な2本仕舞いにしたくなったのです。そして、3番の節抜きをすることにしました。これも順調に進み、後1節ぬけば終了となりました。・・・が、そこで油断してしまい、強引に力を入れたために、「バキッ・・・
 」
」ここで落ち着いて節抜き用のキリを抜けば、まだ被害は少なかったのですが、あせってしまい
 これまた強引に引き抜いてしまいました
これまた強引に引き抜いてしまいました 。すると再び、
。すると再び、「バキバキッ・・・
 」
」暗がりで作業をしていたのですが、家の中に持って入ってよく見ると、竹にヒビが2箇所も、しかも節を超えてほぼ端から端まで・・・
 。
。これがまだ手元の4番だったら、適当な竹を見つけてやり直せばいいのですが、3番というのは上は2番と、下は4番とサイズをミリ以下の単位で合わせているので、上下両方のサイズに合う同じような太さとテーパーの竹を探すのは無理です。家にあるヘナヘナの竹を何度もみましたが、フィットするものはやはりなし。この3番は小節で特に気に入っていたので、ダメージ大です

 。
。方法は2つ。3番、4番と2本入れ替えるか、割れの入った3番を糸でぐるぐる巻きにして修理するかです。どちらにするか現在、悩み中です
 。
。タグ :3号竿
2012年03月21日
平キリの製作
3月18日(日)
今週末は雨 &荒れ模様
&荒れ模様 。その上に風邪菌がお腹に入り、トイレから離れられません
。その上に風邪菌がお腹に入り、トイレから離れられません 。そうです、こんな時は無理に釣りに行かず、家族サービスのチャンス到来
。そうです、こんな時は無理に釣りに行かず、家族サービスのチャンス到来 ・・・ということで、嫁さんの実家へ行きました。一応、暇つぶしに(・・・
・・・ということで、嫁さんの実家へ行きました。一応、暇つぶしに(・・・ )工作道具も持って行きました。そして・・・
)工作道具も持って行きました。そして・・・
こんなものを作ってしまいました 。
。

平キリ(葉錐)セットです。これを電動ドリルにセットして竿の込み口を削るのに使います。3号竿に必要なサイズを2mm0.2mm毎に作りました。
使用した材料と工具類はこちらです。

上から、材料のドリルロッド棒(SK-4、1mm~4mm)、ノギス、ダイアモンドヤスリ(平型)、電動ルーター(ダイヤモンドヤスリをセット)、トーチ、ハンマー、万力(アンビル付)です。これを嫁さんの実家にもって行き、雨 が降る中、屋根のある駐車場にて、トーチで鉄を焼き、ハンマーで叩き、電動ルーターで削るという作業をひっそりと行いました
が降る中、屋根のある駐車場にて、トーチで鉄を焼き、ハンマーで叩き、電動ルーターで削るという作業をひっそりと行いました (焼き入れと焼きなましは家に戻ってやりました)。
(焼き入れと焼きなましは家に戻ってやりました)。
雨が止んだ後は、子供を連れて近くまでお散歩
 。
。

前回来た時にちょっとした竹やぶを見つけていたので、そちらへ行ってみました 。・・・が、へら竿に使えそうな竹ではなさそうでした。
。・・・が、へら竿に使えそうな竹ではなさそうでした。
・・・ってことで、なかなか充実した家族サービスでした・・・ (自分へのサービスか・・・
(自分へのサービスか・・・ )。
)。
今週末は雨
 &荒れ模様
&荒れ模様 。その上に風邪菌がお腹に入り、トイレから離れられません
。その上に風邪菌がお腹に入り、トイレから離れられません 。そうです、こんな時は無理に釣りに行かず、家族サービスのチャンス到来
。そうです、こんな時は無理に釣りに行かず、家族サービスのチャンス到来 ・・・ということで、嫁さんの実家へ行きました。一応、暇つぶしに(・・・
・・・ということで、嫁さんの実家へ行きました。一応、暇つぶしに(・・・ )工作道具も持って行きました。そして・・・
)工作道具も持って行きました。そして・・・こんなものを作ってしまいました
 。
。
平キリ(葉錐)セットです。これを電動ドリルにセットして竿の込み口を削るのに使います。3号竿に必要なサイズを
使用した材料と工具類はこちらです。

上から、材料のドリルロッド棒(SK-4、1mm~4mm)、ノギス、ダイアモンドヤスリ(平型)、電動ルーター(ダイヤモンドヤスリをセット)、トーチ、ハンマー、万力(アンビル付)です。これを嫁さんの実家にもって行き、雨
 が降る中、屋根のある駐車場にて、トーチで鉄を焼き、ハンマーで叩き、電動ルーターで削るという作業をひっそりと行いました
が降る中、屋根のある駐車場にて、トーチで鉄を焼き、ハンマーで叩き、電動ルーターで削るという作業をひっそりと行いました (焼き入れと焼きなましは家に戻ってやりました)。
(焼き入れと焼きなましは家に戻ってやりました)。雨が止んだ後は、子供を連れて近くまでお散歩

 。
。
前回来た時にちょっとした竹やぶを見つけていたので、そちらへ行ってみました
 。・・・が、へら竿に使えそうな竹ではなさそうでした。
。・・・が、へら竿に使えそうな竹ではなさそうでした。・・・ってことで、なかなか充実した家族サービスでした・・・
 (自分へのサービスか・・・
(自分へのサービスか・・・ )。
)。 2012年03月13日
3号竿プロジェクト始動
3月13日(火)
先日修理した竿2号ですが、その後一度使用し、問題なく使えました。ただ、やはり竹がやわらかすぎるので、どこまで耐えられるか家でテストしてたんです。すると再び同じ込みのところが、
「バキッ ・・・
・・・ 」
」
もう、修理するより新たな竿を作ることにしました。竿3号プロジェクトの始動です 。
。
今回も8尺です。前回の敗因はまず素材にあり ・・・ということで、素材を厳選しました
・・・ということで、素材を厳選しました 。ただし、高級な竿用の竹素材ではなく、いつもの園芸用のちょっと干からびた竹+嫁さんの実家近くで拾った細い竹(おそらく普通の女竹)です
。ただし、高級な竿用の竹素材ではなく、いつもの園芸用のちょっと干からびた竹+嫁さんの実家近くで拾った細い竹(おそらく普通の女竹)です 。できるだけ節間の詰まったもので、節から出ていた枝の切り後が目立たない部分を選びました。また、あまりテーパーの効いてない竹なので、前回のように3本継ぎではなく、4本継ぎにして、全体としてテーパーがでるようにしました。穂先は竿2号のものを流用し、短く切って使うことにしました。
。できるだけ節間の詰まったもので、節から出ていた枝の切り後が目立たない部分を選びました。また、あまりテーパーの効いてない竹なので、前回のように3本継ぎではなく、4本継ぎにして、全体としてテーパーがでるようにしました。穂先は竿2号のものを流用し、短く切って使うことにしました。

火入れ、生地組み、中抜きまで、完了しました 。中抜きは3番の竹を割るのを恐れたので、現時点ではとりあえず手元の4番だけにして、穂持ち(2番)の収納はあきらめ、穂先(1番)のみ納めることにしました。写真の手元用の竹ですが、竿尻側が欲しい長さより少し短かったので、尻栓を長めに竹で作り、印籠継ぎとしました(どうせ握りで隠れる部分なので)。また、ほぼ中央部分にひび割れと疑われる縦傷がありましたので、念のためこの部分には上からエポキシを塗って、糸を巻いて補強する予定です
。中抜きは3番の竹を割るのを恐れたので、現時点ではとりあえず手元の4番だけにして、穂持ち(2番)の収納はあきらめ、穂先(1番)のみ納めることにしました。写真の手元用の竹ですが、竿尻側が欲しい長さより少し短かったので、尻栓を長めに竹で作り、印籠継ぎとしました(どうせ握りで隠れる部分なので)。また、ほぼ中央部分にひび割れと疑われる縦傷がありましたので、念のためこの部分には上からエポキシを塗って、糸を巻いて補強する予定です 。
。
これからまだ口糸巻き、込みや握り手の作り、塗りとまだまだ工程があります・・・。最後まで大きな失敗をすることなく、進めばいいのですが、失敗すると竹から探さないといけません。もう家に残っている竹はひょろひょろのJUNKばかりです・・・ 。
。
成功を祈って、今宵は前祝いだ~
 。
。
=======================================
以下、自身の記録のために竿サイズの詳細のメモです。
※ 予定竿長: 710+710+620+600-(90+80+70)=2,400(8尺)
※ 込み元径: 手元は握り手の先部分、他は各々の竿尻部から込み長さ戻った部分の太さ。
※ 込み先径: 各々の込みを削った時の竿尻部の太さ(目標)。
先日修理した竿2号ですが、その後一度使用し、問題なく使えました。ただ、やはり竹がやわらかすぎるので、どこまで耐えられるか家でテストしてたんです。すると再び同じ込みのところが、
「バキッ
 ・・・
・・・ 」
」もう、修理するより新たな竿を作ることにしました。竿3号プロジェクトの始動です
 。
。今回も8尺です。前回の敗因はまず素材にあり
 ・・・ということで、素材を厳選しました
・・・ということで、素材を厳選しました 。ただし、高級な竿用の竹素材ではなく、いつもの園芸用のちょっと干からびた竹+嫁さんの実家近くで拾った細い竹(おそらく普通の女竹)です
。ただし、高級な竿用の竹素材ではなく、いつもの園芸用のちょっと干からびた竹+嫁さんの実家近くで拾った細い竹(おそらく普通の女竹)です 。できるだけ節間の詰まったもので、節から出ていた枝の切り後が目立たない部分を選びました。また、あまりテーパーの効いてない竹なので、前回のように3本継ぎではなく、4本継ぎにして、全体としてテーパーがでるようにしました。穂先は竿2号のものを流用し、短く切って使うことにしました。
。できるだけ節間の詰まったもので、節から出ていた枝の切り後が目立たない部分を選びました。また、あまりテーパーの効いてない竹なので、前回のように3本継ぎではなく、4本継ぎにして、全体としてテーパーがでるようにしました。穂先は竿2号のものを流用し、短く切って使うことにしました。
火入れ、生地組み、中抜きまで、完了しました
 。中抜きは3番の竹を割るのを恐れたので、現時点ではとりあえず手元の4番だけにして、穂持ち(2番)の収納はあきらめ、穂先(1番)のみ納めることにしました。写真の手元用の竹ですが、竿尻側が欲しい長さより少し短かったので、尻栓を長めに竹で作り、印籠継ぎとしました(どうせ握りで隠れる部分なので)。また、ほぼ中央部分にひび割れと疑われる縦傷がありましたので、念のためこの部分には上からエポキシを塗って、糸を巻いて補強する予定です
。中抜きは3番の竹を割るのを恐れたので、現時点ではとりあえず手元の4番だけにして、穂持ち(2番)の収納はあきらめ、穂先(1番)のみ納めることにしました。写真の手元用の竹ですが、竿尻側が欲しい長さより少し短かったので、尻栓を長めに竹で作り、印籠継ぎとしました(どうせ握りで隠れる部分なので)。また、ほぼ中央部分にひび割れと疑われる縦傷がありましたので、念のためこの部分には上からエポキシを塗って、糸を巻いて補強する予定です 。
。これからまだ口糸巻き、込みや握り手の作り、塗りとまだまだ工程があります・・・。最後まで大きな失敗をすることなく、進めばいいのですが、失敗すると竹から探さないといけません。もう家に残っている竹はひょろひょろのJUNKばかりです・・・
 。
。成功を祈って、今宵は前祝いだ~

 。
。=======================================
以下、自身の記録のために竿サイズの詳細のメモです。
| (長さ) | (込み口径) | (込み長) | (込み元径) | (込み先径) | |
| 手元(4番) | 710 | 8.7 | n/a | 10.0 | n/a |
| 穂持ち下(3番) | 710 | 6.6 | 90 | 7.6 | 6.7 |
| 穂持ち(2番) | 620 | 4.4 | 80 | 5.6 | 4.8 |
| 穂先(1番) | 600 | n/a | 70 | 3.6 | 2.9 |
※ 予定竿長: 710+710+620+600-(90+80+70)=2,400(8尺)
※ 込み元径: 手元は握り手の先部分、他は各々の竿尻部から込み長さ戻った部分の太さ。
※ 込み先径: 各々の込みを削った時の竿尻部の太さ(目標)。
タグ :3号竿
2012年03月06日
浮子ケース製作
3月5日(月)
土曜日は、磯の予定、海が荒れていたらへらのつもりでしたが、前夜に突如飲みのお誘いが・・・ 。不覚にも飲み過ぎてしまい、土曜は二日酔い
。不覚にも飲み過ぎてしまい、土曜は二日酔い 。磯は早々にあきらめ、昼まで寝てなんとかへらには行こうと思っていましたが、頭痛と胃の不快感は取れず、釣りはあきらめました
。磯は早々にあきらめ、昼まで寝てなんとかへらには行こうと思っていましたが、頭痛と胃の不快感は取れず、釣りはあきらめました 。せめて、日曜日は子連れでへらに行こうかと思っておりましたが、雨
。せめて、日曜日は子連れでへらに行こうかと思っておりましたが、雨 で、これも実現できず
で、これも実現できず 。
。
・・・ということで、週末は工作することに 。浮子ケースの製作です。木材はホームセンターで、天板および底板用にアガチス600×90×3(長さ・幅・厚さ)を2枚、側面用にヒノキ910×15×9(同)を2本購入。それを切って組み立てました。
。浮子ケースの製作です。木材はホームセンターで、天板および底板用にアガチス600×90×3(長さ・幅・厚さ)を2枚、側面用にヒノキ910×15×9(同)を2本購入。それを切って組み立てました。

写真のように重ねた時の仕上がり寸法は、約380×90×36(長さ・幅・高さ)です。今回側面のヒノキは上下それぞれ15mmのものを使いましたが、本当は30mmのものを使って一旦箱を作り、それを真ん中でフタと底側に切断すると噛み合わせが揃い、また木材のクセが同じ方向になるので、上手く作れるようです。わたしの場合、それを知ったのが材料を購入した後だったこともあり、万力を乗せて、噛み合わせがフィットするように癖をつけました 。
。
天板と底板は木工用ボンドで張り付けただけなんですが、側面は強化するために竹串で2cmほどの釘をつくり、それを打ち込んでいます。

天板の余った材料とマット剤を使い、中の仕切り(ウキ尻を差し込むところやウキのトップを押さえるところ)を作りました。下の写真はウキ尻を差し込む部分です。マット材を2枚に重ねて、上になる方に三角の切りこみ(+縦の切りこみ)を入れています。

これら部材をセットして、木工部分は完了しました 。
。

試しにウキを入れてみると、なかなかいい感じです
 。左右ともに上下7本ずつで合計28本。通常使用で33cmまで、片側の仕切りをはずすと最長35.5cmのウキまで入ります。
。左右ともに上下7本ずつで合計28本。通常使用で33cmまで、片側の仕切りをはずすと最長35.5cmのウキまで入ります。
次に左右の接続ですが、一般的な蝶番と磁石を使おうと思いましたが、蝶番をきれいにつけるのは結構難しい上に、小型の蝶番に合う細い木ネジが見つからなかったので(普通の釘だとすぐに緩んでくるため)、全部磁石で付けることとしました。ただ、使い勝手が悪くなると嫌だなと思って、インターネットで調べてるとプロの作品でも全部磁石のものがあることを発見したので、安心して全部磁石でやることに・・・。使った磁石はこちら 。
。

100円ショップで購入。ピン型になっていますが、ニッパで挟んで力を入れると簡単に割れて、中の磁石だけでてきます。ビニール袋の中に手を入れてこの作業をやらないと、磁石やプラスティックの破片が飛んでいくので、ご注意を 。
。
そして、磁石をつける前に塗装しました。塗装は合成うるしの透と透明を混ぜて1度、本透明を1度、それぞれ拭き塗りをしました。乾燥後、磁石をつけます。一辺3個ずつ左右両面に付けますので、12個の穴を彫刻刀と電動ルーターを使って慎重に開けました。磁石の木部への接着は瞬間接着剤だと不安なので、2液性のエポキシを使いました。水色?緑?のマットは100円ショップの机用マット(発泡材のようなもの)です。

なかなかいい感じに仕上がりました 。磁石の開け閉めも横にずらすようにして開閉するととてもスムーズ。磁石も強力なので、しっかり閉まります。
。磁石の開け閉めも横にずらすようにして開閉するととてもスムーズ。磁石も強力なので、しっかり閉まります。
次におまけですが、ウキもまだ大量に持って行くような釣りもしていないので、片側がハリスケースにもできればいいなと部品を作ってみました。ステンレスのパイプと今回の端材です。

これを組み立ててみるとこんな感じになります 。
。

まずはこれで実戦に投入してみます 。
。
土曜日は、磯の予定、海が荒れていたらへらのつもりでしたが、前夜に突如飲みのお誘いが・・・
 。不覚にも飲み過ぎてしまい、土曜は二日酔い
。不覚にも飲み過ぎてしまい、土曜は二日酔い 。磯は早々にあきらめ、昼まで寝てなんとかへらには行こうと思っていましたが、頭痛と胃の不快感は取れず、釣りはあきらめました
。磯は早々にあきらめ、昼まで寝てなんとかへらには行こうと思っていましたが、頭痛と胃の不快感は取れず、釣りはあきらめました 。せめて、日曜日は子連れでへらに行こうかと思っておりましたが、雨
。せめて、日曜日は子連れでへらに行こうかと思っておりましたが、雨 で、これも実現できず
で、これも実現できず 。
。・・・ということで、週末は工作することに
 。浮子ケースの製作です。木材はホームセンターで、天板および底板用にアガチス600×90×3(長さ・幅・厚さ)を2枚、側面用にヒノキ910×15×9(同)を2本購入。それを切って組み立てました。
。浮子ケースの製作です。木材はホームセンターで、天板および底板用にアガチス600×90×3(長さ・幅・厚さ)を2枚、側面用にヒノキ910×15×9(同)を2本購入。それを切って組み立てました。
写真のように重ねた時の仕上がり寸法は、約380×90×36(長さ・幅・高さ)です。今回側面のヒノキは上下それぞれ15mmのものを使いましたが、本当は30mmのものを使って一旦箱を作り、それを真ん中でフタと底側に切断すると噛み合わせが揃い、また木材のクセが同じ方向になるので、上手く作れるようです。わたしの場合、それを知ったのが材料を購入した後だったこともあり、万力を乗せて、噛み合わせがフィットするように癖をつけました
 。
。天板と底板は木工用ボンドで張り付けただけなんですが、側面は強化するために竹串で2cmほどの釘をつくり、それを打ち込んでいます。

天板の余った材料とマット剤を使い、中の仕切り(ウキ尻を差し込むところやウキのトップを押さえるところ)を作りました。下の写真はウキ尻を差し込む部分です。マット材を2枚に重ねて、上になる方に三角の切りこみ(+縦の切りこみ)を入れています。

これら部材をセットして、木工部分は完了しました
 。
。
試しにウキを入れてみると、なかなかいい感じです

 。左右ともに上下7本ずつで合計28本。通常使用で33cmまで、片側の仕切りをはずすと最長35.5cmのウキまで入ります。
。左右ともに上下7本ずつで合計28本。通常使用で33cmまで、片側の仕切りをはずすと最長35.5cmのウキまで入ります。次に左右の接続ですが、一般的な蝶番と磁石を使おうと思いましたが、蝶番をきれいにつけるのは結構難しい上に、小型の蝶番に合う細い木ネジが見つからなかったので(普通の釘だとすぐに緩んでくるため)、全部磁石で付けることとしました。ただ、使い勝手が悪くなると嫌だなと思って、インターネットで調べてるとプロの作品でも全部磁石のものがあることを発見したので、安心して全部磁石でやることに・・・。使った磁石はこちら
 。
。
100円ショップで購入。ピン型になっていますが、ニッパで挟んで力を入れると簡単に割れて、中の磁石だけでてきます。ビニール袋の中に手を入れてこの作業をやらないと、磁石やプラスティックの破片が飛んでいくので、ご注意を
 。
。そして、磁石をつける前に塗装しました。塗装は合成うるしの透と透明を混ぜて1度、本透明を1度、それぞれ拭き塗りをしました。乾燥後、磁石をつけます。一辺3個ずつ左右両面に付けますので、12個の穴を彫刻刀と電動ルーターを使って慎重に開けました。磁石の木部への接着は瞬間接着剤だと不安なので、2液性のエポキシを使いました。水色?緑?のマットは100円ショップの机用マット(発泡材のようなもの)です。

なかなかいい感じに仕上がりました
 。磁石の開け閉めも横にずらすようにして開閉するととてもスムーズ。磁石も強力なので、しっかり閉まります。
。磁石の開け閉めも横にずらすようにして開閉するととてもスムーズ。磁石も強力なので、しっかり閉まります。次におまけですが、ウキもまだ大量に持って行くような釣りもしていないので、片側がハリスケースにもできればいいなと部品を作ってみました。ステンレスのパイプと今回の端材です。

これを組み立ててみるとこんな感じになります
 。
。
まずはこれで実戦に投入してみます
 。
。 タグ :浮子ケース
2012年03月02日
研ぎ出してみた!
3月2日(金)
前回竹脚のかやウキ2本を下塗りをあわせて6~7回合成うるしを塗った後、乾燥させていましたが、数日そのままにして十分に乾燥させる予定でした。しかし、やはり待ちきれず、「試作だからいいや」と次の日その日の夜には研ぎ出しをやってしまいました・・・ 。水やすりは400番、600番、1000番を使いました。ドキドキしながら・・・
。水やすりは400番、600番、1000番を使いました。ドキドキしながら・・・ 。そして研ぎ出しました。
。そして研ぎ出しました。
「おおーっ、結構いけてるんちゃうん 」
」
思ったより、きれいに模様が出てました 。それから二晩。うるしの本透明を2度塗りして塗りは完了。こちらです。
。それから二晩。うるしの本透明を2度塗りして塗りは完了。こちらです。

ピッカピカ 。前回の竹片の試し塗りとは少し違う塗りをしています。「黒・赤・金
。前回の竹片の試し塗りとは少し違う塗りをしています。「黒・赤・金 」・・・まるで某メーカーのまわし者のようです。
」・・・まるで某メーカーのまわし者のようです。
そして、トップのソリッドを切断の上、パイプトップの内径にあわせてデザインナイフとやすりで削り、ウキを完成させました 。
。

「おー、ワンダフル~! 」
」
ただ、このウキはちょっと傾いてるんです 。こんなに最初からうまくいくはずではなかったので、トップや脚が少し傾いたまま塗装をしてしまいました・・・
。こんなに最初からうまくいくはずではなかったので、トップや脚が少し傾いたまま塗装をしてしまいました・・・ 。
。
脚を瞬間接着剤を使って、いっきに固めるとこんなことになります。せめて接着する前に型をつけるか、あるいはやはり瞬間接着剤ではないものを使って、調整できる余地を残すかが必要です。まあ、次はそうしますです・・・ハイ 。
。
ところで、明日は晴れ 。久しぶりに磯に行きたいのですが、わたしの使っている天気予報では、強風予想・・・
。久しぶりに磯に行きたいのですが、わたしの使っている天気予報では、強風予想・・・ 。この強風予想の時に磯に行くと、だいたいとんでもない目にあうんです
。この強風予想の時に磯に行くと、だいたいとんでもない目にあうんです 。ただ、朝になると強風から弱風に変わっていることもあるので、明朝起きたとき次第かな・・・
。ただ、朝になると強風から弱風に変わっていることもあるので、明朝起きたとき次第かな・・・ 。だめならヘラで、このウキ使ってきます・・・
。だめならヘラで、このウキ使ってきます・・・ 。
。
前回竹脚のかやウキ2本を下塗りをあわせて6~7回合成うるしを塗った後、乾燥させていましたが、数日そのままにして十分に乾燥させる予定でした。しかし、やはり待ちきれず、「試作だからいいや」と
 。水やすりは400番、600番、1000番を使いました。ドキドキしながら・・・
。水やすりは400番、600番、1000番を使いました。ドキドキしながら・・・ 。そして研ぎ出しました。
。そして研ぎ出しました。「おおーっ、結構いけてるんちゃうん
 」
」思ったより、きれいに模様が出てました
 。それから二晩。うるしの本透明を2度塗りして塗りは完了。こちらです。
。それから二晩。うるしの本透明を2度塗りして塗りは完了。こちらです。
ピッカピカ
 。前回の竹片の試し塗りとは少し違う塗りをしています。「黒・赤・金
。前回の竹片の試し塗りとは少し違う塗りをしています。「黒・赤・金 」・・・まるで某メーカーのまわし者のようです。
」・・・まるで某メーカーのまわし者のようです。そして、トップのソリッドを切断の上、パイプトップの内径にあわせてデザインナイフとやすりで削り、ウキを完成させました
 。
。
「おー、ワンダフル~!
 」
」ただ、このウキはちょっと傾いてるんです
 。こんなに最初からうまくいくはずではなかったので、トップや脚が少し傾いたまま塗装をしてしまいました・・・
。こんなに最初からうまくいくはずではなかったので、トップや脚が少し傾いたまま塗装をしてしまいました・・・ 。
。脚を瞬間接着剤を使って、いっきに固めるとこんなことになります。せめて接着する前に型をつけるか、あるいはやはり瞬間接着剤ではないものを使って、調整できる余地を残すかが必要です。まあ、次はそうしますです・・・ハイ
 。
。ところで、明日は晴れ
 。久しぶりに磯に行きたいのですが、わたしの使っている天気予報では、強風予想・・・
。久しぶりに磯に行きたいのですが、わたしの使っている天気予報では、強風予想・・・ 。この強風予想の時に磯に行くと、だいたいとんでもない目にあうんです
。この強風予想の時に磯に行くと、だいたいとんでもない目にあうんです 。ただ、朝になると強風から弱風に変わっていることもあるので、明朝起きたとき次第かな・・・
。ただ、朝になると強風から弱風に変わっていることもあるので、明朝起きたとき次第かな・・・ 。だめならヘラで、このウキ使ってきます・・・
。だめならヘラで、このウキ使ってきます・・・ 。
。 2012年02月28日
ウキを作る ~その後
2月28日(火)
先日作成したウキです。脚を黒く塗ると見た目が少し締まりました 。ウキトップ塗装用の黒いハケ付きラッカーを使いました。
。ウキトップ塗装用の黒いハケ付きラッカーを使いました。

この土日で、すでに実戦にも投入。あたりもばっちりわかりました。ボディー形状はもちろん大切だと思いますが、要はトップの浮力でエサを背負い、あたりを表現するわけなので、素人ウキにはトップの選択が非常に重要だなと思いました。これさえ、間違えなければ、とりあえずあたりを表現できるウキにはなるようです 。
。
さて、機能性は徐々に高めていくこととして、満足度をすぐに高めるには、見た目の改善ですね・・・ 。そこで、まず脚を竹で作成しました。
。そこで、まず脚を竹で作成しました。

左側です。右側はすでに1番目の写真の上端と下端が黒色の長い方のウキに仕上がってます。竹は編み棒0号を削って使いました。竹串でもいいのですが、焼き入れをしたり、曲げをとったりしないといけないので、すでにまっすぐにしてある編み棒は便利です 。
。
そして、やはり塗装です。ウレタン塗っておけば、機能的には問題ないのですが、やはりうるし(合成)を塗ってきれいなウキを作ってみたくなります。単色塗りはすでにやっていますが、研ぎだしなどの塗りはやったことがないので、まずは、不要な竹片で練習がてらに試し塗りをしてみました。

いろいろなホームページを見て、なんとなくこうするのかな?というやり方で実験してみました。とりあえず、それっぽく見えます 。
。
・・・ということで、この手法でいってみようと現在竹脚の2本を乾燥中です。

この次の工程が研ぎだし(水やすりで磨いて、中に重ねた色を出していきます)、それが終わると仕上げ塗りになります。
試し塗りの竹片より丁寧にやってしまったのが、吉と出るか凶と出るか微妙な感じ・・・ 。たぶん、大胆にやる方が、良い結果が生まれそうな気がしてます。
。たぶん、大胆にやる方が、良い結果が生まれそうな気がしてます。
まあ、こればかりは研いでみないとわからないので、後日のお楽しみということで・・・
先日作成したウキです。脚を黒く塗ると見た目が少し締まりました
 。ウキトップ塗装用の黒いハケ付きラッカーを使いました。
。ウキトップ塗装用の黒いハケ付きラッカーを使いました。
この土日で、すでに実戦にも投入。あたりもばっちりわかりました。ボディー形状はもちろん大切だと思いますが、要はトップの浮力でエサを背負い、あたりを表現するわけなので、素人ウキにはトップの選択が非常に重要だなと思いました。これさえ、間違えなければ、とりあえずあたりを表現できるウキにはなるようです
 。
。さて、機能性は徐々に高めていくこととして、満足度をすぐに高めるには、見た目の改善ですね・・・
 。そこで、まず脚を竹で作成しました。
。そこで、まず脚を竹で作成しました。
左側です。右側はすでに1番目の写真の上端と下端が黒色の長い方のウキに仕上がってます。竹は編み棒0号を削って使いました。竹串でもいいのですが、焼き入れをしたり、曲げをとったりしないといけないので、すでにまっすぐにしてある編み棒は便利です
 。
。そして、やはり塗装です。ウレタン塗っておけば、機能的には問題ないのですが、やはりうるし(合成)を塗ってきれいなウキを作ってみたくなります。単色塗りはすでにやっていますが、研ぎだしなどの塗りはやったことがないので、まずは、不要な竹片で練習がてらに試し塗りをしてみました。

いろいろなホームページを見て、なんとなくこうするのかな?というやり方で実験してみました。とりあえず、それっぽく見えます
 。
。・・・ということで、この手法でいってみようと現在竹脚の2本を乾燥中です。

この次の工程が研ぎだし(水やすりで磨いて、中に重ねた色を出していきます)、それが終わると仕上げ塗りになります。
試し塗りの竹片より丁寧にやってしまったのが、吉と出るか凶と出るか微妙な感じ・・・
 。たぶん、大胆にやる方が、良い結果が生まれそうな気がしてます。
。たぶん、大胆にやる方が、良い結果が生まれそうな気がしてます。まあ、こればかりは研いでみないとわからないので、後日のお楽しみということで・・・

2012年02月23日
1日でウキを作る Part3
2月23日(木)
【Part3:塗装】
塗装は、ボディー部だけにします。性能にはほとんど影響ないでしょうから、脚はソリッドむき出しです。パイプトップも今回はすでに着色された既製品を使用することにしました。
まず、上下の絞り部分の溝を隠すために、厚化粧することに・・・ 。合成うるしを塗ればできるのですが、乾燥時間が丸一日かかります。しかも何度か重ね塗りをしなければなりませんので数日かかります。1日でウキを作るのが目標なので、まず家にあったアクリル絵の具を使ってみました。
。合成うるしを塗ればできるのですが、乾燥時間が丸一日かかります。しかも何度か重ね塗りをしなければなりませんので数日かかります。1日でウキを作るのが目標なので、まず家にあったアクリル絵の具を使ってみました。
マスキングをして塗りましたが、マスキングテープとの境目に段差ができてしまうので、乾いてすぐに剥がしました 。でも、あら不思議・・・溝には絵の具がしっかりと入り、パテ埋め状態になってました
。でも、あら不思議・・・溝には絵の具がしっかりと入り、パテ埋め状態になってました (まあ着色する場合には、普通に木材用パテで埋めればいいだけのことなんですけど・・・)。
(まあ着色する場合には、普通に木材用パテで埋めればいいだけのことなんですけど・・・)。

・・・で、もっとも邪道かつ簡単な方法のマジックで塗ることにしました。この前ハンズで購入したCOPICを使いました。自作竿に名入れとかする目的で、衝動買いしたのですが(高いです。1本450円もします・・・ )、水性顔料インクで、乾くと耐水性ということで、製図やマンガを描く人とかが使っているそうです。油性ペンだと塗装と反応して、インク流れが起こるようなので、ご注意ください。ついでにこの段階でウキに名入れをしました。(【後日談】:名入れや水性塗料での着色は、下地用のウレタンを塗って乾燥させ、ヤスリで軽く磨いて、平らにした後がたぶん正解です。)
)、水性顔料インクで、乾くと耐水性ということで、製図やマンガを描く人とかが使っているそうです。油性ペンだと塗装と反応して、インク流れが起こるようなので、ご注意ください。ついでにこの段階でウキに名入れをしました。(【後日談】:名入れや水性塗料での着色は、下地用のウレタンを塗って乾燥させ、ヤスリで軽く磨いて、平らにした後がたぶん正解です。)

水性マジックのため、すぐに乾きますので、次に一番簡単な1液性ウレタン塗料のドブ付けをしました。後ろに写った2本は東京でボディーを作った分です。

早く乾かすために、風呂場の暖房をつけてやりました。2度塗りの予定でしたので、次が塗りたくて我慢してましたが、4時間経ったところで我慢も限界になったので、少し早いかなと思いつつ2度目を・・・。今度はもっと早く乾かしてやろうと暖房用のオイルヒーターの上部に吊るして強制的に乾かしました 。・・・が、同様に4時間待ってウキを見ると表面に泡やブツブツが・・・
。・・・が、同様に4時間待ってウキを見ると表面に泡やブツブツが・・・ 。1度目のが十分に乾いていなかったため、しわが出たのか、熱で気泡でも出てしまったのでしょうか・・・
。1度目のが十分に乾いていなかったため、しわが出たのか、熱で気泡でも出てしまったのでしょうか・・・ 。仕方ないので、表面の泡やぶつぶつを1000番ヤスリで軽く水研ぎし、3度目塗りました。ただ、ちょうど夜でしたので、そのまま就寝しました
。仕方ないので、表面の泡やぶつぶつを1000番ヤスリで軽く水研ぎし、3度目塗りました。ただ、ちょうど夜でしたので、そのまま就寝しました 。
。
そして翌朝になり、しっかりと乾燥しているのを確認。自動車用のコンパウンドで磨き、塗装は完了。次は実際に水に浮かせて最終調整です。そのままだとトップが長すぎてバランスが悪いので、トップを少し切るとともに、もう少しオモリを背負えるように脚も切って、2Bの錘で(フカセマンには、ガンダマがイメージしやすい )バランスするように調整しました。針とサルカンを付けたエサ落ち目盛は、もう1~2目盛上になるでしょうから、ぴったりです。なお、トップを長くし過ぎると、表面張力が勝って、立たないウキになりますので、ご注意ください(石鹸でウキを洗うと大丈夫になるケースもあります)。
)バランスするように調整しました。針とサルカンを付けたエサ落ち目盛は、もう1~2目盛上になるでしょうから、ぴったりです。なお、トップを長くし過ぎると、表面張力が勝って、立たないウキになりますので、ご注意ください(石鹸でウキを洗うと大丈夫になるケースもあります)。

最後にトップを瞬間接着剤でとめて完成です
 。強制乾燥の塗装事故があったので、前日中に完成しませんでしたが、前日は昼から始めたので、24時間以内で完成しました
。強制乾燥の塗装事故があったので、前日中に完成しませんでしたが、前日は昼から始めたので、24時間以内で完成しました 。ウレタン2度塗りなら十分その日の内に完成できたと思います。
。ウレタン2度塗りなら十分その日の内に完成できたと思います。
東京でボディーを作った分は、先週家に戻ってから、エポキシボンドを下塗りと防水のための塗料代わりに、ウレタン薄め液で薄めて塗りました(邪道です )。乾燥させるのに普通10分のものが、丸1日かかりました・・・
)。乾燥させるのに普通10分のものが、丸1日かかりました・・・ )。そして、その上から合成うるしの透と透明を混ぜて、3度塗りしました(3日間)。木工用ボンドを乾かすのにも2晩かかってましたから(最初の接着と修正の接着)、結局約1週間かかったことになります
)。そして、その上から合成うるしの透と透明を混ぜて、3度塗りしました(3日間)。木工用ボンドを乾かすのにも2晩かかってましたから(最初の接着と修正の接着)、結局約1週間かかったことになります 。
。
今回のように瞬間接着剤を使用して製作した場合、失敗すると調整不可で後戻りできませんが、すぐにやり直せるので、作り方に慣れるまではこの方法でやって、上手になったら精度や塗りも意識して、じっくり取り組むのが良いのではと思いました 。
。
以上、「1日でウキを作る」でした。お粗末さまでした 。
。
【Part3:塗装】
塗装は、ボディー部だけにします。性能にはほとんど影響ないでしょうから、脚はソリッドむき出しです。パイプトップも今回はすでに着色された既製品を使用することにしました。
まず、上下の絞り部分の溝を隠すために、厚化粧することに・・・
 。合成うるしを塗ればできるのですが、乾燥時間が丸一日かかります。しかも何度か重ね塗りをしなければなりませんので数日かかります。1日でウキを作るのが目標なので、まず家にあったアクリル絵の具を使ってみました。
。合成うるしを塗ればできるのですが、乾燥時間が丸一日かかります。しかも何度か重ね塗りをしなければなりませんので数日かかります。1日でウキを作るのが目標なので、まず家にあったアクリル絵の具を使ってみました。マスキングをして塗りましたが、マスキングテープとの境目に段差ができてしまうので、乾いてすぐに剥がしました
 。でも、あら不思議・・・溝には絵の具がしっかりと入り、パテ埋め状態になってました
。でも、あら不思議・・・溝には絵の具がしっかりと入り、パテ埋め状態になってました (まあ着色する場合には、普通に木材用パテで埋めればいいだけのことなんですけど・・・)。
(まあ着色する場合には、普通に木材用パテで埋めればいいだけのことなんですけど・・・)。
・・・で、もっとも邪道かつ簡単な方法のマジックで塗ることにしました。この前ハンズで購入したCOPICを使いました。自作竿に名入れとかする目的で、衝動買いしたのですが(高いです。1本450円もします・・・
 )、水性顔料インクで、乾くと耐水性ということで、製図やマンガを描く人とかが使っているそうです。油性ペンだと塗装と反応して、インク流れが起こるようなので、ご注意ください。ついでにこの段階でウキに名入れをしました。(【後日談】:名入れや水性塗料での着色は、下地用のウレタンを塗って乾燥させ、ヤスリで軽く磨いて、平らにした後がたぶん正解です。)
)、水性顔料インクで、乾くと耐水性ということで、製図やマンガを描く人とかが使っているそうです。油性ペンだと塗装と反応して、インク流れが起こるようなので、ご注意ください。ついでにこの段階でウキに名入れをしました。(【後日談】:名入れや水性塗料での着色は、下地用のウレタンを塗って乾燥させ、ヤスリで軽く磨いて、平らにした後がたぶん正解です。)
水性マジックのため、すぐに乾きますので、次に一番簡単な1液性ウレタン塗料のドブ付けをしました。後ろに写った2本は東京でボディーを作った分です。

早く乾かすために、風呂場の暖房をつけてやりました。2度塗りの予定でしたので、次が塗りたくて我慢してましたが、4時間経ったところで我慢も限界になったので、少し早いかなと思いつつ2度目を・・・。今度はもっと早く乾かしてやろうと暖房用のオイルヒーターの上部に吊るして強制的に乾かしました
 。・・・が、同様に4時間待ってウキを見ると表面に泡やブツブツが・・・
。・・・が、同様に4時間待ってウキを見ると表面に泡やブツブツが・・・ 。1度目のが十分に乾いていなかったため、しわが出たのか、熱で気泡でも出てしまったのでしょうか・・・
。1度目のが十分に乾いていなかったため、しわが出たのか、熱で気泡でも出てしまったのでしょうか・・・ 。仕方ないので、表面の泡やぶつぶつを1000番ヤスリで軽く水研ぎし、3度目塗りました。ただ、ちょうど夜でしたので、そのまま就寝しました
。仕方ないので、表面の泡やぶつぶつを1000番ヤスリで軽く水研ぎし、3度目塗りました。ただ、ちょうど夜でしたので、そのまま就寝しました 。
。そして翌朝になり、しっかりと乾燥しているのを確認。自動車用のコンパウンドで磨き、塗装は完了。次は実際に水に浮かせて最終調整です。そのままだとトップが長すぎてバランスが悪いので、トップを少し切るとともに、もう少しオモリを背負えるように脚も切って、2Bの錘で(フカセマンには、ガンダマがイメージしやすい
 )バランスするように調整しました。針とサルカンを付けたエサ落ち目盛は、もう1~2目盛上になるでしょうから、ぴったりです。なお、トップを長くし過ぎると、表面張力が勝って、立たないウキになりますので、ご注意ください(石鹸でウキを洗うと大丈夫になるケースもあります)。
)バランスするように調整しました。針とサルカンを付けたエサ落ち目盛は、もう1~2目盛上になるでしょうから、ぴったりです。なお、トップを長くし過ぎると、表面張力が勝って、立たないウキになりますので、ご注意ください(石鹸でウキを洗うと大丈夫になるケースもあります)。
最後にトップを瞬間接着剤でとめて完成です

 。強制乾燥の塗装事故があったので、前日中に完成しませんでしたが、前日は昼から始めたので、24時間以内で完成しました
。強制乾燥の塗装事故があったので、前日中に完成しませんでしたが、前日は昼から始めたので、24時間以内で完成しました 。ウレタン2度塗りなら十分その日の内に完成できたと思います。
。ウレタン2度塗りなら十分その日の内に完成できたと思います。東京でボディーを作った分は、先週家に戻ってから、エポキシボンドを下塗りと防水のための塗料代わりに、ウレタン薄め液で薄めて塗りました(邪道です
 )。乾燥させるのに普通10分のものが、丸1日かかりました・・・
)。乾燥させるのに普通10分のものが、丸1日かかりました・・・ )。そして、その上から合成うるしの透と透明を混ぜて、3度塗りしました(3日間)。木工用ボンドを乾かすのにも2晩かかってましたから(最初の接着と修正の接着)、結局約1週間かかったことになります
)。そして、その上から合成うるしの透と透明を混ぜて、3度塗りしました(3日間)。木工用ボンドを乾かすのにも2晩かかってましたから(最初の接着と修正の接着)、結局約1週間かかったことになります 。
。今回のように瞬間接着剤を使用して製作した場合、失敗すると調整不可で後戻りできませんが、すぐにやり直せるので、作り方に慣れるまではこの方法でやって、上手になったら精度や塗りも意識して、じっくり取り組むのが良いのではと思いました
 。
。以上、「1日でウキを作る」でした。お粗末さまでした
 。
。 タグ :浮子
2012年02月22日
1日でウキを作る Part2
2月22日(水)
【Part2:ボディー成型】
では、塗装する前までのボディーを成型するところです。まずは、切削が完了したカヤの中心部分にグラスソリッドをゆっくりとまっすぐになるように慎重に差し込んでみます。

今回はウキのボディーが6cmと短いので、通し差しにすることにしましたが、脚には竹やカーボンなど違う素材や違う径のソリッドを使用するケースも多く、おまけにソリッドの通し差しだと少し重くなるので、脚とトップのソリッドは別のものを使うことの方が一般的だと思います。

写真のようにカッティングボードの線などを見ながらやると、わりとまっすぐ入れやすいと思います。なお、写真のカッティングボードはアメリカ在住時に購入したものなので、数字はインチ表示で、cmではありませんのでご注意ください。
次に指し込んだソリッドを一旦抜き、ゼリータイプの瞬間接着剤をボディーの中心部の穴を目がけて垂らします。そしてソリッドを回しながら一気に指し込みます。回しながらすると接着剤が中に入っていきます。ゆっくりやりすぎると途中で瞬間接着剤が固まってしまい、どうしようもなくなります 。わたしは間一髪でした
。わたしは間一髪でした 。
。
そして今度は開いた部分に液体の瞬間接着剤を塗ってから、すばやくタコ糸をグルグル巻きにしました。マスキングテープは巻いたままでOK。糸が滑らないので簡単に巻けます。トップとボトムと順にやります。おそらく状態が見えるからだと思いますが、一般的には細い糸を隙間をあけて巻くようです。太いタコ糸だと状態は見ませんが、瞬間接着剤を使用しているのでいずれにせよ修正は効かないため、全体的に力が入りやすい太いタコ糸を使用しました。

5分もすれば乾いていますので、慎重に糸をほどきます。糸も瞬間接着剤で少し固まっていましたが、それほど苦労せずに取れました。

次にマスキングテープがあるので、それもはずしました。カヤの表面はそれほど瞬間接着剤がついていませんでしたが、少々ガビガビにはなっていました 。
。

そして、全体的に紙やすり400番程度で磨きました。ガビガビは簡単に取れました。・・・が、あわせの部分に隙間がありました。木工用ボンドでつけていると、この程度は瞬間接着剤をつけて再度糸で縛ると簡単に修正できるのですが、最初から瞬間接着剤なので、修正不可です。塗りのところでごまかすことにしました。試しにトップも付けてみました。良い感じです
 。
。

~ 【Part3:塗装】に続く ~
【Part2:ボディー成型】
では、塗装する前までのボディーを成型するところです。まずは、切削が完了したカヤの中心部分にグラスソリッドをゆっくりとまっすぐになるように慎重に差し込んでみます。

今回はウキのボディーが6cmと短いので、通し差しにすることにしましたが、脚には竹やカーボンなど違う素材や違う径のソリッドを使用するケースも多く、おまけにソリッドの通し差しだと少し重くなるので、脚とトップのソリッドは別のものを使うことの方が一般的だと思います。

写真のようにカッティングボードの線などを見ながらやると、わりとまっすぐ入れやすいと思います。なお、写真のカッティングボードはアメリカ在住時に購入したものなので、数字はインチ表示で、cmではありませんのでご注意ください。
次に指し込んだソリッドを一旦抜き、ゼリータイプの瞬間接着剤をボディーの中心部の穴を目がけて垂らします。そしてソリッドを回しながら一気に指し込みます。回しながらすると接着剤が中に入っていきます。ゆっくりやりすぎると途中で瞬間接着剤が固まってしまい、どうしようもなくなります
 。わたしは間一髪でした
。わたしは間一髪でした 。
。そして今度は開いた部分に液体の瞬間接着剤を塗ってから、すばやくタコ糸をグルグル巻きにしました。マスキングテープは巻いたままでOK。糸が滑らないので簡単に巻けます。トップとボトムと順にやります。おそらく状態が見えるからだと思いますが、一般的には細い糸を隙間をあけて巻くようです。太いタコ糸だと状態は見ませんが、瞬間接着剤を使用しているのでいずれにせよ修正は効かないため、全体的に力が入りやすい太いタコ糸を使用しました。

5分もすれば乾いていますので、慎重に糸をほどきます。糸も瞬間接着剤で少し固まっていましたが、それほど苦労せずに取れました。

次にマスキングテープがあるので、それもはずしました。カヤの表面はそれほど瞬間接着剤がついていませんでしたが、少々ガビガビにはなっていました
 。
。
そして、全体的に紙やすり400番程度で磨きました。ガビガビは簡単に取れました。・・・が、あわせの部分に隙間がありました。木工用ボンドでつけていると、この程度は瞬間接着剤をつけて再度糸で縛ると簡単に修正できるのですが、最初から瞬間接着剤なので、修正不可です。塗りのところでごまかすことにしました。試しにトップも付けてみました。良い感じです

 。
。
~ 【Part3:塗装】に続く ~
タグ :浮子
2012年02月21日
1日でウキを作る Part1
2月21日(火)
ヘラ用に竿掛けや玉網、竿まで作ったのだから、やはりウキも作らんとあかんな~と・・・ 。
。
先週ちょっと記事にした通り、東京へ仕事に行っている間にホテルでウキのボディー作りをやってみましたが、結構時間がかかりました。トップと脚の絞り部分の切りだしは刃が一気に入って失敗したり、紙ヤスリで削っているとカヤ素材が割れたりします。その上、木工用ボンドは乾燥に時間がかかるので、修正はしやすいのですが、すぐに次の作業に移れません。釣りをする人は気が短いとよく言いますが、ご多分にもれず、わたしも接着剤や塗装の乾燥待ちが大嫌いです 。
。
もちろん丁寧に作業し、時間も余裕を持って、作る方が良い物ができるのはわかっていますが、もっと簡単に、しかも早く仕上げる方法はないものかと考えながら、1日でウキを作るを目指してみることにしました 。
。
なお、カヤウキ作りの基本は、東邦産業のHPにあるヘラ浮子の作り方を主に参照しました。
まず今回の材料および製作道具です。
・ 5~6mm径のカヤ
・ グラスソリッドの1mm(脚およびパイプトップ固定用ソリッド)
・ 既成のテーパー付き極細パイプトップ(長さ12mm、元外径1.2mm、元内径約0.8mm)
・ 100円ショップの瞬間接着剤(液体とゼリーの2種)
・ OLFAの超極薄0.2mmのカッター(片刃カミソリを見つけられなかったので)
・ マスキング用テープ(医療用の包帯止めるようなやつ)
・ タコ糸
・ 紙ヤスリ(240番、400番、600番、1000番)
・ 1液性ウレタン
・ マジックとアクリル絵の具、定規、はさみ、その他
今回の完成品です 。
。

なお、以下に記載する製作方法はウキ作り初心者によるお試し的なものなので、次回はぜんぜん違う方法で作っているかもしれません。あしからず・・・。経験者の皆様、もっと簡単に作る方法をご存知でしたら、ぜひ教えてください。よろしく~ 。では、ウキ作りのスタートです
。では、ウキ作りのスタートです 。
。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【Part1:カヤ切削】
まずカヤを今回は6cmにカット。前回東京では10cmでやりました。転がしながらカッターで切り、切り口はヤスリで整えました。前回絞り部分を切りこむのに苦労したので、トップと脚ともに絞り予定部分(+α)にテープを貼り、洗面所からメイク用ハサミをこっそり取り出し 、それで切って仕上げることを考えましたが、実験するとやはりカヤが割れてしまいましたので、その方法は却下。
、それで切って仕上げることを考えましたが、実験するとやはりカヤが割れてしまいましたので、その方法は却下。
そこで、テープは鉛筆で線を引けるようにマスキング用テープに変え、普通にカッターで切ることにしました(カッターは極薄刃でないと素材が割れます)。今回は、トップの絞りを8mm、脚の絞りを30mmにしました。

一般的には、テープは貼らずに青線部分のように4分割してから、赤線のところまで、少しずつカッターや紙やすりで整えていくようですが、マスキングテープにきっちりと図面を描いているので、いきなり赤線のところを斜めに刃を入れて切っていきました。少しずつ慎重に削らなくてよい上に、テープで刃が滑らず簡単に切れたので、作業時間は少なく済みました 。おまけに面倒なので、定規などは使わずフリーハンドで線を描いてます
。おまけに面倒なので、定規などは使わずフリーハンドで線を描いてます 。。(【後日談】:定規あるいはプラスティックの板等を使用して、線をきっちり描くと、隙間も少なく、仕上がりがかなりきれいになりますので、こちらがお勧めです。)
。。(【後日談】:定規あるいはプラスティックの板等を使用して、線をきっちり描くと、隙間も少なく、仕上がりがかなりきれいになりますので、こちらがお勧めです。)
これが切った直後の写真です。かなり適当なことがお分かりいただけるでしょう・・・(笑)。

次に溝部分に紙やすりを差し込んで側面にもあてながら前後に軽く往復して削っていきました。

まったく力を入れる必要はなく、無理にワタを取ろうとしなくても簡単に削れました。そして、紙やすりを反対向きにして、反対面も・・・。そして90度回して同様に。深さが予定の絞り幅の線に達するところまで削ります。
削り終えるとこんな感じになりました 。
。

意外とうまくいきました 。
。
脚側の絞りも同様にカッターで切って、紙やすりを差し込んで削って、カヤ切削の工程はあっという間に終了しました 。
。
~ 【Part2:ボディー成型】に続く ~
ヘラ用に竿掛けや玉網、竿まで作ったのだから、やはりウキも作らんとあかんな~と・・・
 。
。先週ちょっと記事にした通り、東京へ仕事に行っている間にホテルでウキのボディー作りをやってみましたが、結構時間がかかりました。トップと脚の絞り部分の切りだしは刃が一気に入って失敗したり、紙ヤスリで削っているとカヤ素材が割れたりします。その上、木工用ボンドは乾燥に時間がかかるので、修正はしやすいのですが、すぐに次の作業に移れません。釣りをする人は気が短いとよく言いますが、ご多分にもれず、わたしも接着剤や塗装の乾燥待ちが大嫌いです
 。
。もちろん丁寧に作業し、時間も余裕を持って、作る方が良い物ができるのはわかっていますが、もっと簡単に、しかも早く仕上げる方法はないものかと考えながら、1日でウキを作るを目指してみることにしました
 。
。なお、カヤウキ作りの基本は、東邦産業のHPにあるヘラ浮子の作り方を主に参照しました。
まず今回の材料および製作道具です。
・ 5~6mm径のカヤ
・ グラスソリッドの1mm(脚およびパイプトップ固定用ソリッド)
・ 既成のテーパー付き極細パイプトップ(長さ12mm、元外径1.2mm、元内径約0.8mm)
・ 100円ショップの瞬間接着剤(液体とゼリーの2種)
・ OLFAの超極薄0.2mmのカッター(片刃カミソリを見つけられなかったので)
・ マスキング用テープ(医療用の包帯止めるようなやつ)
・ タコ糸
・ 紙ヤスリ(240番、400番、600番、1000番)
・ 1液性ウレタン
・ マジックとアクリル絵の具、定規、はさみ、その他
今回の完成品です
 。
。
なお、以下に記載する製作方法はウキ作り初心者によるお試し的なものなので、次回はぜんぜん違う方法で作っているかもしれません。あしからず・・・。経験者の皆様、もっと簡単に作る方法をご存知でしたら、ぜひ教えてください。よろしく~
 。では、ウキ作りのスタートです
。では、ウキ作りのスタートです 。
。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【Part1:カヤ切削】
まずカヤを今回は6cmにカット。前回東京では10cmでやりました。転がしながらカッターで切り、切り口はヤスリで整えました。前回絞り部分を切りこむのに苦労したので、トップと脚ともに絞り予定部分(+α)にテープを貼り、洗面所からメイク用ハサミをこっそり取り出し
 、それで切って仕上げることを考えましたが、実験するとやはりカヤが割れてしまいましたので、その方法は却下。
、それで切って仕上げることを考えましたが、実験するとやはりカヤが割れてしまいましたので、その方法は却下。そこで、テープは鉛筆で線を引けるようにマスキング用テープに変え、普通にカッターで切ることにしました(カッターは極薄刃でないと素材が割れます)。今回は、トップの絞りを8mm、脚の絞りを30mmにしました。

一般的には、テープは貼らずに青線部分のように4分割してから、赤線のところまで、少しずつカッターや紙やすりで整えていくようですが、マスキングテープにきっちりと図面を描いているので、いきなり赤線のところを斜めに刃を入れて切っていきました。少しずつ慎重に削らなくてよい上に、テープで刃が滑らず簡単に切れたので、作業時間は少なく済みました
 。おまけに面倒なので、定規などは使わずフリーハンドで線を描いてます
。おまけに面倒なので、定規などは使わずフリーハンドで線を描いてます 。。(【後日談】:定規あるいはプラスティックの板等を使用して、線をきっちり描くと、隙間も少なく、仕上がりがかなりきれいになりますので、こちらがお勧めです。)
。。(【後日談】:定規あるいはプラスティックの板等を使用して、線をきっちり描くと、隙間も少なく、仕上がりがかなりきれいになりますので、こちらがお勧めです。)これが切った直後の写真です。かなり適当なことがお分かりいただけるでしょう・・・(笑)。

次に溝部分に紙やすりを差し込んで側面にもあてながら前後に軽く往復して削っていきました。

まったく力を入れる必要はなく、無理にワタを取ろうとしなくても簡単に削れました。そして、紙やすりを反対向きにして、反対面も・・・。そして90度回して同様に。深さが予定の絞り幅の線に達するところまで削ります。
削り終えるとこんな感じになりました
 。
。
意外とうまくいきました
 。
。脚側の絞りも同様にカッターで切って、紙やすりを差し込んで削って、カヤ切削の工程はあっという間に終了しました
 。
。~ 【Part2:ボディー成型】に続く ~
タグ :浮子
2012年02月21日
2号竿緊急入院
2月19日(日)
昨日、釣り場で曲がってしまった自作竿2号。元竿部分が曲がったと思っていたのですが、家に戻り調べてみると、穂持ち(2番目)の元竿へ差し込む凸の部分にひびが入っていました 。
。
固めて補修してもまた折れそうなので、原因を調べるためにひびの入っているところを思い切って切断してみました 。
。

原因がいくつか判明しました 。
。
まず明らかなのが補強芯。ホームセンターの園芸竹ということもあり、テーパーのきちんとした竹はなかなかありません。穂持ちと元竿の長さを合わせることを優先したので、込み(凸)に加工した部分は長い節間のペニャンペニャン部分でした。竹の表皮を削ったこともあり、ますます弱くなっているので、竹串を芯材に入れて補強していたのですが、芯材を入れるために穴をあけるドリルの長さが足らず、芯材を十分に深くまで入れていませんでした。そのせいで、ちょうど継ぎ目の一番力のかかるところに芯材の先端が来てしまい、それより元側は強く、先側は弱くなりますので、強度に差があり、そこで折れてしまったようです 。
。
次に穂持ちに使った竹は、節と節の中間が膨らんでおり、そのまま作ると込み(凸)が太くなりすぎるため、表皮を削って太さを調整していました。その表皮を削り弱くなった部分に元竿の継ぎ口(凹部先端)があたるようになっていたので、気にしてはいたのですが・・・。まさにそこでした 。
。
そして、込み口の作りの甘さ。差し込んで竿を振ると、少しギシギシいってました 。込み口(凹)と込み(凸)のテーパーがきっちりあっていないのだと思います。それゆえ力が分散されず、特定の場所に力が掛かっていたのだと思います。
。込み口(凹)と込み(凸)のテーパーがきっちりあっていないのだと思います。それゆえ力が分散されず、特定の場所に力が掛かっていたのだと思います。
穂先はとてもいいカーブを描いていました。良い感じだったのですが、もしかすると穂先が穂持ちに比べて強すぎたかもしれません。
・・・ということで、竿は少し短くはなりましたが、補強のための竹串を今度は深く入れなおし、表皮を削っていない場所に継ぎ口(凹部先端)があたるように込み(凸部)調整をして、とりあえずの修理としました 。
。

ただ、また折れるかもしれませんので、再度材料を吟味して、3号竿に向けて生地組みからボチボチ開始していこうと思います 。プロの竿は、込み部分の(凸)先端の方に竹の節をおくように生地組みしているケースが多いようです。
。プロの竿は、込み部分の(凸)先端の方に竹の節をおくように生地組みしているケースが多いようです。
昨日、釣り場で曲がってしまった自作竿2号。元竿部分が曲がったと思っていたのですが、家に戻り調べてみると、穂持ち(2番目)の元竿へ差し込む凸の部分にひびが入っていました
 。
。固めて補修してもまた折れそうなので、原因を調べるためにひびの入っているところを思い切って切断してみました
 。
。
原因がいくつか判明しました
 。
。まず明らかなのが補強芯。ホームセンターの園芸竹ということもあり、テーパーのきちんとした竹はなかなかありません。穂持ちと元竿の長さを合わせることを優先したので、込み(凸)に加工した部分は長い節間のペニャンペニャン部分でした。竹の表皮を削ったこともあり、ますます弱くなっているので、竹串を芯材に入れて補強していたのですが、芯材を入れるために穴をあけるドリルの長さが足らず、芯材を十分に深くまで入れていませんでした。そのせいで、ちょうど継ぎ目の一番力のかかるところに芯材の先端が来てしまい、それより元側は強く、先側は弱くなりますので、強度に差があり、そこで折れてしまったようです
 。
。次に穂持ちに使った竹は、節と節の中間が膨らんでおり、そのまま作ると込み(凸)が太くなりすぎるため、表皮を削って太さを調整していました。その表皮を削り弱くなった部分に元竿の継ぎ口(凹部先端)があたるようになっていたので、気にしてはいたのですが・・・。まさにそこでした
 。
。そして、込み口の作りの甘さ。差し込んで竿を振ると、少しギシギシいってました
 。込み口(凹)と込み(凸)のテーパーがきっちりあっていないのだと思います。それゆえ力が分散されず、特定の場所に力が掛かっていたのだと思います。
。込み口(凹)と込み(凸)のテーパーがきっちりあっていないのだと思います。それゆえ力が分散されず、特定の場所に力が掛かっていたのだと思います。穂先はとてもいいカーブを描いていました。良い感じだったのですが、もしかすると穂先が穂持ちに比べて強すぎたかもしれません。
・・・ということで、竿は少し短くはなりましたが、補強のための竹串を今度は深く入れなおし、表皮を削っていない場所に継ぎ口(凹部先端)があたるように込み(凸部)調整をして、とりあえずの修理としました
 。
。
ただ、また折れるかもしれませんので、再度材料を吟味して、3号竿に向けて生地組みからボチボチ開始していこうと思います
 。プロの竿は、込み部分の(凸)先端の方に竹の節をおくように生地組みしているケースが多いようです。
。プロの竿は、込み部分の(凸)先端の方に竹の節をおくように生地組みしているケースが多いようです。タグ :2号竿
2012年02月08日
2号竿改造
2月8日(水)
先日、へら用の2号竿を製作し、実釣に使ってみようと思っていたのですが、その数日後に知り合いから本物の竹のへら竿をいただいてしまい、そのあまりもの違いに愕然として 、自作の2号竿を使えなくなってしまいました
、自作の2号竿を使えなくなってしまいました 。
。
それ以来、本物を参考に穂持ち(穂先の次)を違う竹に変更して組み直し、穂先はカーボンから竹に、塗装もやり直し・・・と作業を進めて2号竿を改造しました。まだ仕上げの拭き塗りをしていませんが、ほぼ完成。8.3尺です。今度こそ、実釣してみたいと思います 。
。
塗装は前回は継ぎ口はエポキシで先に固め、仕上げに全体にウレタンを塗っていたのですが、今回は高級うるしや特製うるしなど、いわゆる合成うるしの類で塗装してみることにしました。継ぎ口は塗装をはがし、糸巻きからやり直しました。また竿の胴部分もウレタン塗装をヤスリで少し削ってからうるしを塗りました。これは本漆ではないので、かぶれないし、色も和竿らしい色がでるのでいい感じです。ただ、エポキシやウレタンに比べると乾燥時間がかかる上に、何度も塗り重ねないといけないのです。面倒で、ついつい分厚く塗ってしまい、こんなことになってしまいました 。
。

まだら模様です・・・ 。本当は「透明」という色を何度も塗ると少し濃い色になっていい感じになるはずだったのですが、一度目に塗ったときにあまりに色が薄かったので、面倒になり「透(すき)」という濃い目の色をしかも分厚く塗ってしまったのです
。本当は「透明」という色を何度も塗ると少し濃い色になっていい感じになるはずだったのですが、一度目に塗ったときにあまりに色が薄かったので、面倒になり「透(すき)」という濃い目の色をしかも分厚く塗ってしまったのです 。乾燥後、あまりにかっこ悪かったので、削ったのですが、もともと凹んでいる部分は、削っても塗装が取れず、これ以上削ると籐自体が削れてしまいそうだったので、あきらめてまだら模様を選択することになったわけです。できあがれば、まあこれはこれでええっか~という感じです。では拡大写真
。乾燥後、あまりにかっこ悪かったので、削ったのですが、もともと凹んでいる部分は、削っても塗装が取れず、これ以上削ると籐自体が削れてしまいそうだったので、あきらめてまだら模様を選択することになったわけです。できあがれば、まあこれはこれでええっか~という感じです。では拡大写真 。
。

中央の黒い部分は、前回エギのアワビシートをあしらってみたのですが、わが息子に「かっこ悪い」と不評でしたので、それを取り除きました。そして、かわりに継ぎ口の糸巻き部とともに金粉を降りかけてみましたが、ちょっと全体にかけ過ぎてどこかのケバいおねえちゃんのネイルのようになってしまいました 。まあ、これも実験ということでOKでしょう。全体的にまだ少しデコボコはありますが、まあドシロートの1作目はこんなもんでしょう
。まあ、これも実験ということでOKでしょう。全体的にまだ少しデコボコはありますが、まあドシロートの1作目はこんなもんでしょう 。
。

こちらは継ぎ口部分です。やはり金粉をいっぱい付けたので、ピカピカ のネイル状態です。拡大写真はこちら
のネイル状態です。拡大写真はこちら 。
。

糸巻きは今回かなり細い糸を使いましたので、盛り上がりも少なくいい感じにできました。ただ、細い糸は巻くのも時間がかかるので面倒です。途中でロッドモーターで竿を回しながら巻く方法を試すと、結構簡単に巻けるようになりましたので、次回からはその方法でいきます 。
。
最後に穂先です。「竹で穂先を作ってやる」、これが今回の改造の大きなテーマでした。ホームセンターで真竹?の平たい割竹を一本購入(確か150円程度)。それを削って作りました 。
。

まずは竹を細く切り、そしてカンナで四角柱を作り、さらに強い表皮部分は残すようにカンナを入れてテーパーをつけた四角錐にします。そして角を取って八角錐に、そこからはヤスリを使い円錐形に、そしてドリルに尻部を挟み、回しながら紙やすりで仕上げていきます。途中火入れを何度もしながらまっすぐにしていきます。まだほんの少し曲がっていますが、OKということにしておきましょう。何とかできましたが、穂先作りはとても大変な作業でした(でも楽しい・・・ )。
)。
竿作り全体を通じての感想は、とにかくとても面倒で根気のいる作業の連続でした。ただ仕上がった時には、達成感と満足感が満タンでした。問題はここからです・・・継ぎ口の部分は調子に乗って削りすぎて、かなり薄いんです。なので、実釣で「ポキッ」っといかないように願うばかりです 。
。
先日、へら用の2号竿を製作し、実釣に使ってみようと思っていたのですが、その数日後に知り合いから本物の竹のへら竿をいただいてしまい、そのあまりもの違いに愕然として
 、自作の2号竿を使えなくなってしまいました
、自作の2号竿を使えなくなってしまいました 。
。それ以来、本物を参考に穂持ち(穂先の次)を違う竹に変更して組み直し、穂先はカーボンから竹に、塗装もやり直し・・・と作業を進めて2号竿を改造しました。まだ仕上げの拭き塗りをしていませんが、ほぼ完成。8.3尺です。今度こそ、実釣してみたいと思います
 。
。塗装は前回は継ぎ口はエポキシで先に固め、仕上げに全体にウレタンを塗っていたのですが、今回は高級うるしや特製うるしなど、いわゆる合成うるしの類で塗装してみることにしました。継ぎ口は塗装をはがし、糸巻きからやり直しました。また竿の胴部分もウレタン塗装をヤスリで少し削ってからうるしを塗りました。これは本漆ではないので、かぶれないし、色も和竿らしい色がでるのでいい感じです。ただ、エポキシやウレタンに比べると乾燥時間がかかる上に、何度も塗り重ねないといけないのです。面倒で、ついつい分厚く塗ってしまい、こんなことになってしまいました
 。
。
まだら模様です・・・
 。本当は「透明」という色を何度も塗ると少し濃い色になっていい感じになるはずだったのですが、一度目に塗ったときにあまりに色が薄かったので、面倒になり「透(すき)」という濃い目の色をしかも分厚く塗ってしまったのです
。本当は「透明」という色を何度も塗ると少し濃い色になっていい感じになるはずだったのですが、一度目に塗ったときにあまりに色が薄かったので、面倒になり「透(すき)」という濃い目の色をしかも分厚く塗ってしまったのです 。乾燥後、あまりにかっこ悪かったので、削ったのですが、もともと凹んでいる部分は、削っても塗装が取れず、これ以上削ると籐自体が削れてしまいそうだったので、あきらめてまだら模様を選択することになったわけです。できあがれば、まあこれはこれでええっか~という感じです。では拡大写真
。乾燥後、あまりにかっこ悪かったので、削ったのですが、もともと凹んでいる部分は、削っても塗装が取れず、これ以上削ると籐自体が削れてしまいそうだったので、あきらめてまだら模様を選択することになったわけです。できあがれば、まあこれはこれでええっか~という感じです。では拡大写真 。
。
中央の黒い部分は、前回エギのアワビシートをあしらってみたのですが、わが息子に「かっこ悪い」と不評でしたので、それを取り除きました。そして、かわりに継ぎ口の糸巻き部とともに金粉を降りかけてみましたが、ちょっと全体にかけ過ぎてどこかのケバいおねえちゃんのネイルのようになってしまいました
 。まあ、これも実験ということでOKでしょう。全体的にまだ少しデコボコはありますが、まあドシロートの1作目はこんなもんでしょう
。まあ、これも実験ということでOKでしょう。全体的にまだ少しデコボコはありますが、まあドシロートの1作目はこんなもんでしょう 。
。
こちらは継ぎ口部分です。やはり金粉をいっぱい付けたので、ピカピカ
 のネイル状態です。拡大写真はこちら
のネイル状態です。拡大写真はこちら 。
。
糸巻きは今回かなり細い糸を使いましたので、盛り上がりも少なくいい感じにできました。ただ、細い糸は巻くのも時間がかかるので面倒です。途中でロッドモーターで竿を回しながら巻く方法を試すと、結構簡単に巻けるようになりましたので、次回からはその方法でいきます
 。
。最後に穂先です。「竹で穂先を作ってやる」、これが今回の改造の大きなテーマでした。ホームセンターで真竹?の平たい割竹を一本購入(確か150円程度)。それを削って作りました
 。
。
まずは竹を細く切り、そしてカンナで四角柱を作り、さらに強い表皮部分は残すようにカンナを入れてテーパーをつけた四角錐にします。そして角を取って八角錐に、そこからはヤスリを使い円錐形に、そしてドリルに尻部を挟み、回しながら紙やすりで仕上げていきます。途中火入れを何度もしながらまっすぐにしていきます。まだほんの少し曲がっていますが、OKということにしておきましょう。何とかできましたが、穂先作りはとても大変な作業でした(でも楽しい・・・
 )。
)。竿作り全体を通じての感想は、とにかくとても面倒で根気のいる作業の連続でした。ただ仕上がった時には、達成感と満足感が満タンでした。問題はここからです・・・継ぎ口の部分は調子に乗って削りすぎて、かなり薄いんです。なので、実釣で「ポキッ」っといかないように願うばかりです
 。
。 タグ :2号竿
2012年01月18日
玉網と玉の柄の自作
1月18日(水)
気合を入れて、玉網と玉の柄一気に作ってしまいました 。
。

枠はゆっくり炙りながら曲げないといけないので、最初にトライした時は強く曲げ過ぎて折れたり 、焦げてしまったりしましたが
、焦げてしまったりしましたが 、直径7~8mm程度の細めの竹を使い、慎重にやるとうまくいきました。籐を巻いている部分の内側にはパテを埋め、またエポキシで固めて更に強化しました。かなり頑丈にできました。
、直径7~8mm程度の細めの竹を使い、慎重にやるとうまくいきました。籐を巻いている部分の内側にはパテを埋め、またエポキシで固めて更に強化しました。かなり頑丈にできました。
網を枠に編んで行くいくのに針のようなものが必要ですが、ちょうど良いサイズの針がなかったので、糸の先を瞬間接着剤で固めてみるとバッチリ 。網はケチって600円くらいの安物にしてしまいましたが、せっかくなのでヘラ用の普通のやつにすればよかったです。でも網だけで5000円くらいするんです
。網はケチって600円くらいの安物にしてしまいましたが、せっかくなのでヘラ用の普通のやつにすればよかったです。でも網だけで5000円くらいするんです 。いくらなんでも高すぎるでしょ
。いくらなんでも高すぎるでしょ 。
。
さて、玉の柄ですが、握り手は木を削って作ってみました(上部の差し込み口は上の写真に写ってます)。

ちょうど使えそうな円筒型の木材をコーナンで見つけたので、穴は竹のサイズに合わせて大きくし、竹も少し削って調整、木工ボンドで接着。外側はカンナで大まかに削り、ヤスリで仕上げ。水性絵具で色付けをして、ウレタンで塗装しました。糸や籐を巻くのとはまた違った雰囲気になります 。
。
思ったよりうまくできました 。まだいろいろと作りたいものがあるのですが、まずは一昨日の竿とあわせて使ってみます(竿の曲がりが不安
。まだいろいろと作りたいものがあるのですが、まずは一昨日の竿とあわせて使ってみます(竿の曲がりが不安 )。
)。
気合を入れて、玉網と玉の柄一気に作ってしまいました
 。
。
枠はゆっくり炙りながら曲げないといけないので、最初にトライした時は強く曲げ過ぎて折れたり
 、焦げてしまったりしましたが
、焦げてしまったりしましたが 、直径7~8mm程度の細めの竹を使い、慎重にやるとうまくいきました。籐を巻いている部分の内側にはパテを埋め、またエポキシで固めて更に強化しました。かなり頑丈にできました。
、直径7~8mm程度の細めの竹を使い、慎重にやるとうまくいきました。籐を巻いている部分の内側にはパテを埋め、またエポキシで固めて更に強化しました。かなり頑丈にできました。網を枠に編んで行くいくのに針のようなものが必要ですが、ちょうど良いサイズの針がなかったので、糸の先を瞬間接着剤で固めてみるとバッチリ
 。網はケチって600円くらいの安物にしてしまいましたが、せっかくなのでヘラ用の普通のやつにすればよかったです。でも網だけで5000円くらいするんです
。網はケチって600円くらいの安物にしてしまいましたが、せっかくなのでヘラ用の普通のやつにすればよかったです。でも網だけで5000円くらいするんです 。いくらなんでも高すぎるでしょ
。いくらなんでも高すぎるでしょ 。
。さて、玉の柄ですが、握り手は木を削って作ってみました(上部の差し込み口は上の写真に写ってます)。

ちょうど使えそうな円筒型の木材をコーナンで見つけたので、穴は竹のサイズに合わせて大きくし、竹も少し削って調整、木工ボンドで接着。外側はカンナで大まかに削り、ヤスリで仕上げ。水性絵具で色付けをして、ウレタンで塗装しました。糸や籐を巻くのとはまた違った雰囲気になります
 。
。思ったよりうまくできました
 。まだいろいろと作りたいものがあるのですが、まずは一昨日の竿とあわせて使ってみます(竿の曲がりが不安
。まだいろいろと作りたいものがあるのですが、まずは一昨日の竿とあわせて使ってみます(竿の曲がりが不安 )。
)。